←←目次に戻る
フレットの摺り合わせ
フレットの摺り合わせは基本的には、とても簡単な作業です。
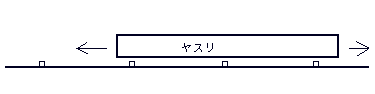 図12
図12
図12のようにヤスリを置いて前後に動かし、各フレットの高さをそろえ
ます。力をあまり入れずに、ヤスリ自体の重さで削るつもりでやれば失敗し
ません。しかし、指板は曲面になっています。したがってフレットも曲面に
する必要が有ります。指板の曲率半径は7.25inchから20inchぐらいまで色々
です。
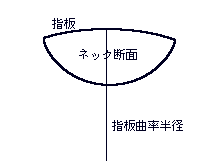 図13
図13
なお、指板のアールの印象はネックのエッジの落としかたで大きく変わり
ます。僕のストラトのアールは7.25なのですが、エッジをかなり落としてあ
ります。あるバンドのレコーディングに貸したとき、そこのギターテクが
「これはアールがきつい」と言ってきました。アールを計るゲージで見ると
ちゃんと7.25なのです。また、ある人がカスタムギターをオーダーする際、
現在所有しているものと同じアールにしたいと相談されました。彼は、アー
ルがきつい気がするといっていましたが、計ってみると7.25ぴったりでした。
そのギターもエッジを少し落としてあったのです。人の感覚は微妙ですが、
時として当てになりません。だまし絵の幾つかが証明するように、信じられ
るのは、ゲージとか、定規とかだったりします。
ギターの調整とは「人間」の印象と「定規」の仲を取り持つことなのかも
知れません。
指板のアールは専用のゲージで計ります。そして、僕たちはそれに合せた
サンドペーパー用台(図14)を持っています。(色々なアールの物を用意し
ている)
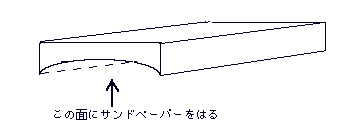 図14
図14
それを使うと指板のアールを出すのは全く簡単ですが、ミュージシャンが
持っているとは考えづらいので、希望を良く伝えてリペアショップに依頼し
ましょう。
また良く慣れた人なら平らなヤスリでこのアールを出すことが出来ます。
でも普通はきっと難しいでしょう。ミュージシャンとしては、基本的にどう
いう作業なのかだけを理解しておいてくれればよいと思います。
補足;摺り合わせは当然弦をはずした状態で行います。その際にネックの状
態が変わってしまうのではないかという疑問が出ると思います。その通りで
す。海外のリペアの文献などを見ますと、弦をはずしてもネックの状態を保
存できるような治具を開発して使用しています。そのような治具を使用しな
い場合にはリペアマンの勘と経験だけが頼りとなります。腕の良いリペアマ
ンと仲よくなるのが一番です。
↑back to top
フレットの修正
上記のようにして削った後のフレットは角張っています。それを図15のよ
うに綺麗な形にします。フレットがすり減ってきても同じ様なことになるわ
けです。これは音が良くないので(不規則倍音が増える)滑らかなものにし
なくてはなりません。安物のギターはフレットを摺り合わせしていなくて高
さがバラバラか、摺り合わせをしていてもその後の整形をしていなくて角が
出ているものが多いです。この作業もまた専用の凹面ヤスリ(図16)が有り
ますので、僕たちは比較的楽にやってます。普通のヤスリでももちろん出来
ますが、ちょっと工夫が必要です。これもショップに依頼した方がよいでしょ
う。
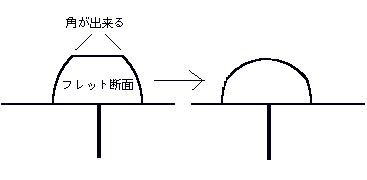 図15
図15
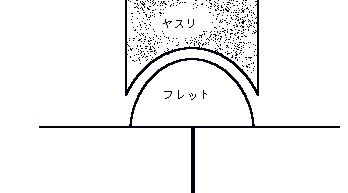 図16
図16
↑back to top(このページの最初に戻る)
←前の章へ
次の章へ→
←←目次に戻る
Copyright(C)1993-2004 Jin TERADA, All Rights Reserved.
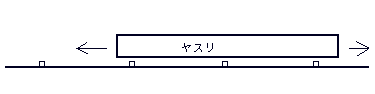 図12
図12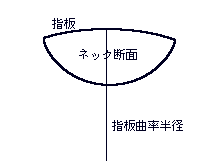 図13
図13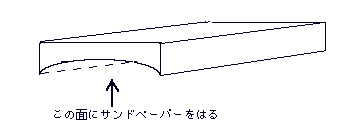 図14
図14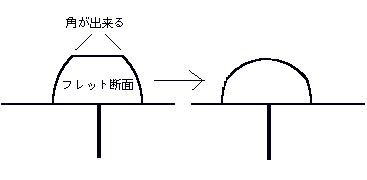 図15
図15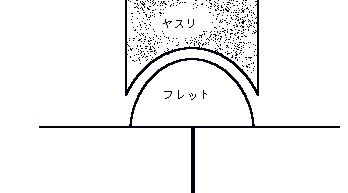 図16
図16