←←目次に戻る
ネックは完璧にまっすぐであることが基本
先ずギターをチューニングしておきます。図8のように定規を当てて、完
璧に直線であることを確認します。反対側に光源を置いて明るくしておくと
見やすいです。
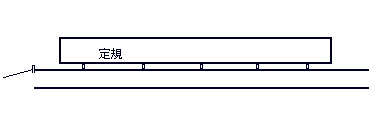 図8
図8
隙間が出来る部分は無いか、良くチェックします。最初に30cmの定規で
大体の傾向をつかんでから15cmの定規で部分的にチェックします。
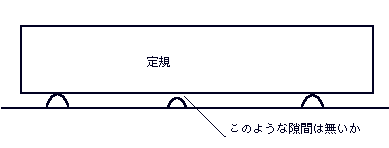 図9
図9
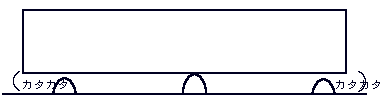 図10
図10
この場合知りたいのは、ネックの「全体の傾向」です。特定のフレット高
のばらつきなどに惑わされないで、全体の傾向を掴むことが大切です。フレッ
トに惑わされないための特殊な定規も存在します。より納得したい方はこれ
を使ってみるのも良いでしょう。
↑back to top
リリーフについて
意図的に「順ぞり」の状態にする調整法も有って、その量を「リリーフ」
と呼びます。しかし、現在のギター/ベースでは特殊なものです。
直線状態を基本に設計された楽器を調整段階の「リリーフ」で具合よくす
るのはとても難しいのです。「リリーフ」の考え方は楽器を設計したときに
採用されるべきものだと思います。そして、例えばワーウィックのベースの
ように、マニュアルに「リリーフ」で設計してあることを明記して、その
「リリーフ量」を指定するのが本来の形だと思います。
直線で調整したギター/ベースのハイフレットの弦高を考えるとき、「リ
リーフ」の考え方が良く解るようになります。
調整になれてきたら「リリーフ」を試してみても良いですが、それに伴う
ピッチ関係のトラブルを覚悟しておいてください。僕は、最初から「リリー
フ」で設計されたもの以外では、やろうとは思いません。
只、残念ながら ワーウィックの例しか知っておりません。もしワーウィッ
ク以外で「リリーフ量」を明記したものが有りましたら是非教えて頂けます
でしょうか。(モデュラスのジェネシスもリリーフで設計されているようで
す。)
↑back to top
ネックを真っ直ぐにする
ネックの大体の傾向が解ったらトラスロッドで出来るだけネックを真っ直
ぐにします。
ポールリードスミスのトラスロッドは回す方向が普通と逆なので注意してく
ださい。
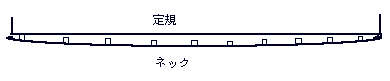 図11
図11
このように真ん中部分に隙間が出来るのが「順ぞり」です(図11)。 逆
の場合は「逆ぞり」です。
順ぞりの場合は、トラスロッドを少し締め込みます。逆ぞりはその逆です。
トラスロッドを締めるときは、いきなり締め込まず、先ず半回転ぐらい緩め
ます。トラスロッドの調整ナットが軽く無理なく回ることを確認します。変
に固かったり、スムースに回らなかった時は、スプレーオイルをほんの少量、
くれぐれもかけ過ぎないように注意して、ネジ部に浸透させ、数分してから
少し回してみます。軽く回るようになったら、定規で直線性を確認しながら、
少しずつ締め込みます。一回に締める量は1/8回転ぐらいです。少しずつゆっ
くり確認しながら、これが基本です。今後ある全ての作業も同様です。急ぐ
必要は全く有りません。
◆トラスロッドを調整するとき、チューニングを緩める必要は特に有りませ
んが、回しにくいギターも有りますので、そのときは、やりやすいように弦
を緩めたり、はずしたりしてください。しかし、直線性のチェックは、あく
まで弦を正しくチューニングした状態で行いますから面倒です。フェンダー
は時期によってネックをはずさないとトラスロッドの調整が出来ませんので
本当に面倒です。
◆トラスロッドが回りにくいときは絶対に無理をしないでください。回りに
くい原因がきっとどこかにあります。ネックの状態をクランプなどを使って
まっすぐにして、それからトラスロッドを回すのが本来のやり方なのかも知
れません。多量の調整が必要なときにはこのほうが上手くいきます。
いずれにしても、自分でやることに不安があったら信頼できるリペアショッ
プに依頼してください。
◆ネックのチェックは季節のかわりめには必ず行うようにします。日本の気
候は楽器にとってとても不利です。ネックは湿度や気温の影響を受けます。
都内の某スタジオは大変空調がきついので、楽器を二日ほど置いておくと全
部狂ってしまいます。その度に調整し直さなければなりません。季節のかわ
りめには同じ様な状態になっていると思われます。一回の調整で一年中良い
調子を保つというのは難しいのです。
アコースティックギターはボディーの状況も変わりますので、なかなか大
変です。湿気が多いとボディーが膨らむので、弦高とかに変化が出てしまい
ます。USAのあるスタジオミュージシャンは、高さの違うブリッジサドル
を数個用意して、ボディーの状況に合せて使い分けているそうです。
ネックが大体まっすぐになったら、もう一度定規を当ててフレットの状態
をチェックします。先程最初にチェックしたときに問題があったフレットの
付近は、特に念入りにチェックします。問題フレットにはマジックインキで
印を付けておくと次の作業のとき便利です。(フレット上面を塗ってしまう。
このインキの残り方がヤスリ掛けの作業具合の目安になる)
↑back to top(このページの最初に戻る)
←前の章へ
次の章へ→
←←目次に戻る
Copyright(C)1993-2004 Jin TERADA, All Rights Reserved.
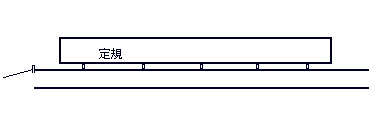 図8
図8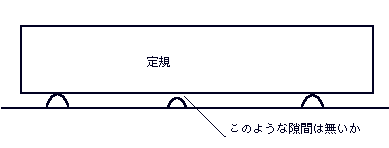 図9
図9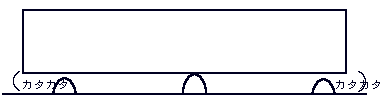 図10
図10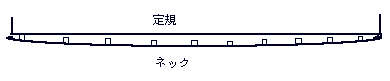 図11
図11