←←目次に戻る
弦の角度、それに伴うETC.
ヘッドやブリッジ部の弦の角度は何度ぐらい必要なのでしょうか?
様々なギターを見てみますと、余白とも言うべき部分(ナットからぺグま
で、ブリッジからテールピースまで)が短ければ5度ぐらいでも十分な場合
が有ります。余白が長いとその部分の余計な振動、アバレが問題となります
ので、もうすこし必要です。ヘッドの共振とかブリッジの構造とか総合的に
考える必要が有ります。
レスポールタイプのブリッジとテールピースの角度はあまりきつくしない
ほうが良いみたいです。テールピースをボディーにつくぐらいまで下げてし
まうと(図25)、ブリッジにかかる前向きの力が大きくなりすぎると思いま
す。
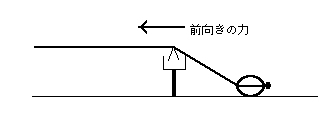 図25
図25
ジェフベックはテールピースに逆から弦を通していますが(図26)、それ
ぐらいの弦角度で丁度良いのではないでしょうか。
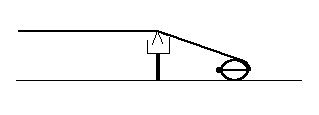 図26
図26
つまりこんな感じ(図27)です。
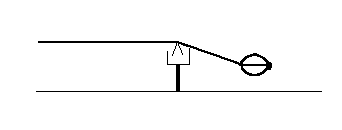 図27
図27
角度がきつい状態で新しい弦を張ってよく見ると、弦がすこし盛り上がっ
ているのが解ります(図28)。時間と共にこの量は減ってきますが、それま
ではどんどんピッチが下がっていくことになります。綺麗に折れると動きは
止まります。ですから早くピッチを安定させたいときはこの部分を下向きに
押して馴染ませます。
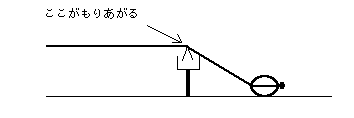 図28
図28
ところで、よく、弦をのばすといって引っ張りますが、実際のところ弦を
のばすというより、ペグでのアソビを減らすのと、この盛り上がりを解消す
るのと、弦のボールエンドのアソビを解消するための作業が主だとおもいま
す。
ひょっとしたらテンション論者はこの盛り上がりによる影響を誤解してい
るのかも知れません。馴染むまで弦高がほんの少し上がる場合が考えられま
すし、倍音も若干影響受けますので余計勘違いするかもしれません。
また、弦が馴染んだときには弦高がわずかですが下がって感じが変わるし、
倍音も変わるので、弦が死んだような印象を受けて、不必要な弦交換をして
しまう恐れも有ります。
(また、弦を引っ張ると弦が死ぬという説もありますが・・・僕は経験した
ことがありません。)
このきつい角度セッティングでの「張りたて」の感じを望むのであれば、
テールピースを上げ、弦高をわずかに上げ、さらに倍音の出方をブリッジの
形状やフレットの形状で調整するというのが良いのではないでしょうか。安
定したサウンドが得られると思います。
ヘッド部の角度も極端には必要有りません。フェンダータイプのストリン
グガイドで必要以上に押さえつけているものを見かけます。ヘッド部の余白
が長い弦はアバレがちですので、ストリングガイドが必要なのですが、ほん
のわずか押さえるだけで目的は達成できます。ペグで、ストリングガイドが
必要ないようにストリングポストの長さを変えた製品が有りますが、要する
にあれぐらいの角度変化で大丈夫なのです。しかもストリングガイドは余白
の丁度真ん中辺につけますので、ヘッドにべったりつける必要などありませ
ん。出来るだけ抵抗を減らして尚且つアバレを押さえられればベストです。
ラージヘッドのストラトの場合、ヘッドの動きがスモールヘッドに較べて
大きいみたいで第3弦にもガイドが必要になるようです。都合上第4弦にもつ
く形になります。
このストリングガイドに要求されることは、
◆がたつきが無いこと
◆よく滑ること
です。グラフテック社から出ているストリングガイドは非常に満足できる
ものです。お勧め品です。他社からもローラーがついたタイプなど抵抗を減
らす工夫を施したものが各種発表されています。ルックスにも影響するもの
なので、性能とスタイルで好みのものを選べばよいでしょう。
←前の章へ
次の章へ→
Copyright(C)1993-2004 Jin TERADA, All Rights Reserved.
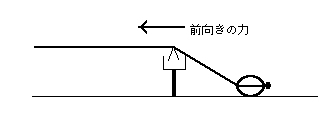 図25
図25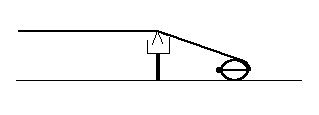 図26
図26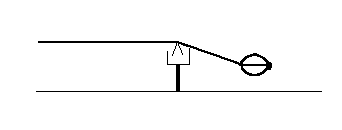 図27
図27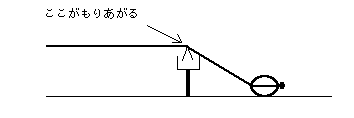 図28
図28