←←目次に戻る
前説ー1 チューニングが合わないギター
世の中には、チューニング(特にローポジションで)が全く合わないギター
が多く存在します。試しに、クロマチックチューナーで全弦の開放から最終
フレットまでピッチを確認してみてください。ある種の設計のギターはおお
むね次のような結果になると思います。
開放とオクターブ調整は正しく合せているとします。そこで、第1フレッ
トを押さえてメーターを見ると、シャープしている場合が多々有ります。そ
して、シャープの度合いは12フレットに近づくにつれ少なくなります。12フ
レットを越えると今度はフラットし始めます。フラットの度合いがだんだん
大きくなって、最終フレットに到達します。
もし、こうならないギターを持っている人はラッキーです。往々にして多
くの国産のギターは上記のような状態になっています。(店頭でチェックし
た範囲では約半数)
この現象はどうして起きるのでしょう?ピッチが全てのフレットでぴった
り合うようには出来ないのでしょうか?
ご安心下さい。ちょっとしたことでぴったり合うように出来るのです。現
に海外のちゃんとしたメーカーの物はぴったり合います。原因を良く考えな
いメーカーやリペアマンは「ギターはチューニングが合わないものなんです」
とか「直線のフレットではこんなものです」とか訳の解らないことをいって
逃げてしまいます。(直線フレット云々については別項で説明します。)
チューニングが合わない主な理由として二つのことが考えられます。
@@ナット高が高すぎる(ナットの切り方が悪い)
@@ナットの位置が悪い
最初の「ナット高が高い」場合にはゲージを使って切り直せば改善される
のでわりと簡単です(ナット高については後述しております)。しかしそれ
だけでは完璧に合わないことが多いのです。ナットの位置そのものが悪い場
合が有るのです。
ナット位置の問題;
先ず、フレット位置がどのようにして決められているか考えてみます。細
かい説明は省きますが2(あるいは1/2)の12乗根で計算されています。ナット
の位置もこれで計算できます。これは、一見良さそうに見えます。そして一
部のメーカーでは、この計算値どうりにナットの位置を決めてしまうようで
す。
計算値どうりのナット位置というのは、弦の張力が一定であるという条件
のもとで成立するのです。もし指で弦を押さえること無しに、有り得ないこ
とですが、フレットが下から持ち上がって(図1)、弦の張力を変えること無
しに弦の振動する部分の長さを変えることが出来るとしたら、これは正しい
のです。
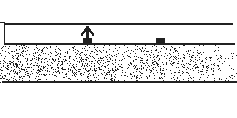 図1
図1
しかし、現実は違います。普通の設定で弦を押さえるということは、弦の
張力を増加させてしまっています(図2)。つまりシャープするのです。ブ
リッジが正しい位置にあると仮定すると、全てのフレットでシャープして当
然なのです。(ポジションによってシャープの度合いは違いますが、ここで
は省略して説明しています。)
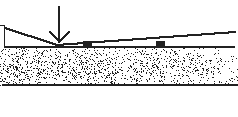 図2
図2
ところがオクターブ調整をするといって、ブリッジを動かして、12フレッ
トを強引に合せてしまいます。つまりブリッジは本来あるべき位置よりも遠
くにセットされることになります。結果として12フレット以降はどんどんフ
ラットします。
この状態のギターをチェックすると先ほど述べたようになっているわけで
す。
厳密に言うと、このように設計されたギターは二十数フレットある内のわ
ずか十分の一である二カ所だけがチューニングが合う状態で、それ以外は合
わないのです。(開放と12フレットで合せているのでそこだけは合う)
解決策としては、開放のときの弦の張力と押弦したときの弦の張力の違い
を、吸収してやればよいのです。具体的には第一フレットとナットの間をほ
んの少し(0.50mmから2.00mm)短くしてやればよいのです。どれだけ短
くするかは、ナット高の設定と密接に関係します。プレイスタイルによって
ナット高は変えた方が良いと思いますので、ナット高を設定すると共に決定
するのがベストでしょう。「ナット」の項も参考にしてください。
{ナットの位置を計算値よりも若干短くする} ただこれだけのことでブリッ
ジ位置も適正なところにセットできますし、全てのフレットでピッチが合う
ようになります。
-- 繰り返しますが、ナット高の不良でもこのシャープは起きます。店頭
でのチェックではどちらに原因があるか特定しておりません。ナット位置不
良かナット高不良か、いずれにしてもピッチが合わないギターが多すぎます。
88鍵のピアノで8カ所しかチューニングが合っていないとしたらどうします
か?おそらく演奏しないでしょう。ところがギターだとこれで通ってしまっ
ているわけです。 --
ネックやフレットの状態が良ければ、全ての弦で開放から最終フレットま
で全フレットでの狂いは0〜±5セント以内に入るでしょう。(実用的なフレッ
トポジションではもっと狂いがすくなく 0〜±2とか±3ぐらい)
僕や友人が所有しているギブソンやフェンダーはほとんどこの範囲内には
いります。
一部メーカーでは悲しい現実が有ります。クロマチックチューナーが有れば
現状を把握するのは容易だと思うのですが、何故なんでしょうか、ひどいギ
ターはいろいろなポジションで20セントもずれています。楽器を作るとい
う意識があまりにも欠除しているのではと僕は思ってしまいます。
↑back to top
前説ー2 直線フレットでは チューニングが合わない??
チューニングの問題を解決するものとして階段状になったフレットの図
(図3)を見たことがある人も多いと思います。本当に直線フレットではチュー
ニングが合わないのでしょうか?
ちょっと考えてみましょう。
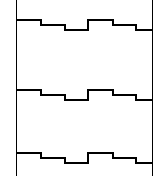 図3
図3
先ず、ブリッジが直線で,弦に対して直角であるギターを考えます。クラ
シックギターのようなものです。フレット配置は弦ごとに調整できるように
なっていると仮定してください。
第1弦用のフレットは第1弦を弾いたときに完璧である間隔に打ってあると
します。この状態で第2弦を弾いたときに完璧であるフレットを考えると、
確かに、第1弦のフレット位置とは違うところにフレットが来ます。更に第3
弦で考えると例の階段状のフレット形状が出てくるわけです。太い弦になる
とフレットがナット方向にシフトしているのが分かります。
しかしこれはブリッジが直線であるという前提での話です。
例えば第3弦に着目して、12フレット(オクターブ上)が丁度第1弦の12
フレットと同じ位置にするにはどうすればよいのでしょう。試しに第3弦の
弦長を長くして12フレットが第1弦に一致するようにしてみます。具体的には、
ブリッジを後ろにさげて弦長を長くします。すると、なんとほかのフレット
も第1弦のフレットの位置にほとんど一致してしまいます。同じように全て
の弦で考えていくと、ブリッジの位置を変えることによって、フレットは直
線のままでもチューニングが合ってしまいます。もちろん実用上の範囲内で
の話です。
この作業の、前提を変えたアプローチ、つまり固定されたフレットに対し
て、オクターブ関係を参考にして、ブリッジを適正位置に合せていく、これ
がオクターブ調整と呼ばれているものなのです。
ではなぜ、このような調整が必要とされるのでしょうか。これは弦が「太
さ」を持っているからです。弦の理想状態とは長さと重さと張力だけが有っ
て、太さが無い状態なのです。太さが有ることによって、弦としての性質と
共に、固体としての性質も合せ持ってしまうのです。当然固体としての性質
は弦が弦長に対して太くなるほど大きく現われます。弦が太くなるほど計算
値で割り出されたブリッジ位置からの偏差が大きくなるのは自明のことなの
です。
巻弦は同じ太さのプレーン弦に比較して、太さによる影響が少なくなって
います。したがって、適正に調整されたブリッジの並びは、図のようになり
ます。(図4)
1、2、3弦はプレーン弦、4、5、6弦は巻弦の場合です。
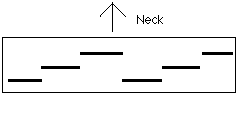 図4
図4
↑back to top
前説ー3 ピックアップとピッチ
一見関係なさそうなピックアップとピッチですが、実は大いに関係有りま
す。ためしに次のことをやってみてください。僕はストラトで試してみました。
1)ピックアップを全体にかなり下げる。特に第6弦側はピックガードと同
じ位の高さにする。
2)第6弦をチューニングする。12フレットで合っていることを確認する。
3)第6弦の12フレットを押さえて音を鳴らしたまま、フロントピックアッ
プの第6弦側をどんどん上げてピッチを見る。弦とマグネットがぶつか
らない程度に出来るだけ高くあげたら、次にミッドピックアップの第6
弦側も同じようにあげてみる。
この作業をチューニングメーターを見ながらやったら、どんどん「フラッ
ト」していく様子を見れると思います。
どうですか?驚きませんか?ピックアップのマグネットが弦を引っ張って
しまうために起こる現象です。普段の状態ではあまり気がつきませんが、ピッ
クアップを弦に近づけすぎていると、特にハイポジションでマグネットの影
響が出て「フラット」してしまいます。音はというと、基音はフラットして
尚且つ倍音関係がグチャグチャになっているみたいで、様々なピッチが聞こ
えます。単音を弾いているのに濁ります。チューニングメーターは基音を読
んでいるようでフラットの表示になります。ストロボチューナーを使うと、
この辺の様子が解りやすいです。
巻弦のハイポジションがメーター上「フラット」して、オクターブ調整後
のブリッジの並びが綺麗にならないとき、一度ピックアップを下げてみてく
ださい。そしてもう一度調整してみてください。
完全に調整してからピックアップを上げていき、ピッチと音質の折り合い
が付くところにピックアップをセットする、というのが基本のような気がし
ます。ピッチがガタガタになるほどにピックアップをあげなければ希望する
音がでないのであれば、そもそも、そのピックアップを選択したのが間違い
だったのかも知れません。
先進的なピックアップメーカーはこのマグネットの影響を軽減するために
工夫をこらしています。レースセンサーが良い例です。
↑back to top
前説ー4 押さえ方でのフラット
押さえ方でシャープするのは容易に理解できると思います。しかしフラッ
トさせることについてはあまり理解されていないようです。
押さえる指の向きと力の方向でフラットさせることが出来ます。プレーン
弦よりは巻弦のほうが比較的簡単です。特にハイポジションでは簡単にフラッ
トします。第4弦の12フレットで25セントぐらいは普通に出来るでしょう。
逆に言うとハイポジションのピッチをチェックするときは押さえる力の
向きに注意しなければなりません。
クラシカルな標準的な左手のフォームはピッチの変動が余りありません。
フラットを試しているうちに左手のフォームの変化に気付くかも知れません。
(シカゴブルースのギタリスト達のフォームの意味が分かるような気がしま
す。彼らのフィーリングを出すためには、あのフォームがきっと必要だった
のでは無いか、と思っています。指を斜めに当ててバタフライビブラートを
する・・というのはおそらくフラットした音から、ジャストピッチをはさん
だ、シャープ〜フラットのビブラートを可能にする為ではないかと僕は勝手
に想像しています。彼らは全く意識していないでしょうが。
普通の押さえ方ではジャストピッチからシャープへのビブラートが普通だ
と思います。クラシックな弦方向へのビブラートはジャストピッチをはさん
だシャープ〜フラットのビブラートですね。)
指によるフラットの方法はスタジオでレコーディングの合間にやってみせ
たりしますが最初は信じてもらえません。「理論的に」おかしいというので
す。ですが、こちらも「理論的に」説明すると解ってもらえます。某スタジ
オミュージシャンとこの話になったとき、彼も「簡単にフラットできるよ、
だって力の向きで弦がたわむから」と言っていました。
↑back to top
前説ー5 テンション????
良く言われる謎のひとつに「テンション」というものが有ります。
いわく「ブリッジとテールピースの角度を大きくすると弦のテンションが
強くなる」とか「ヘッド角度を大きくすると弦のテンションが上がる」とか
「いや角度が小さいほうが弦の張りが強い」とか・・・・・
「角度を大きくするとテンションが上がる」というのは、ある面で正しい
のです。が、世の中でいわれているプレイアビリティ上の「テンション」と
呼ばれるものとは無関係です。
ちょっと弾いてみてテンションが高いからとテールピースの高さを変える
etc・・、テンションが低くなったからチョーキングが楽になったetc・・・、
とかいうのは、ほとんど気のせいでしょう。
弦の角度を変えることでなぜプレイアビリティ上の弦の張りが変わると言
えるのでしょうか?そんなことは無いと思います。納得のいく説明は残念な
がらまだ見たことが有りません。
(もちろん、角度を変えたことによる影響はいろいろ有ります。特にブリッ
ジやナット近傍の弦の状態の変化は考慮すべきところです。)
ギター制作者が言うテンションとはナットにかかる弦の下向きの力とか、
ブリッジにかかる力とかをいうのだと思います(図5)。これは確かに角度
によって変わりますし、不要な弦の遊びを防ぐ為に工夫するところです。ナッ
ト部のテンションが弱いと、ヘッド部の長い弦がナットの溝から飛び出した
りしてしまいますし、ブリッジ部のテンションが弱いとコマ鳴りとか不要部
分の振動とかの問題が出てきてしまいます。それでテンション(駒圧)調整
ということで弦の角度が語られるわけです。
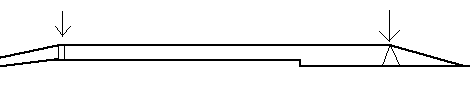 図5
図5
しかし、もう一度いいますが、チョーキングのしやすさ押弦のしやすさな
どで語られるプレイアビリティ上のテンションとは無関係だと思います。
「テンション=弦の張り=弾いたとき指に感じる弦の固さ」というのが検
証無しに独り歩きしているようです。テンションという言葉から単純に「弦
の張りである」と誤解をしてしまったというのが真実です。
弦の張力は使用する弦と、スケール長と、合せようとしているピッチによっ
て自動的に決まってしまいます。例えば.032の弦をフェンダースケールのギ
ターの第5弦に使うとすれば、それが何処のメーカーのギターであろうと、
色々なところの角度がどうであろうと、スケール長と合せようとするピッチ
が同じであれば、同じ張力で張られるのです。
弦の角度についてはまた後ほど触れると思いますが、ひとつだけ・・・・・
フロイトローズに付いているストリングガイド(僕はそれ以上のものでは
ないと思っています)についてです。ヘッドに付いているバー状の「テンショ
ンバー」とか呼ばれているものです。
これはチューニングのしやすさだけのために有ると思います。あのバーが
無い状態でロックナットをはずして、ナット部を良く見るとヘッド側の部分
で弦がナットから離れているのが解ります。この状態でペグで仮のチューニ
ングをしてからロックナットを締めてみるとシャープしてしまいます。先ほ
どの隙間部分を締め込んでしまうのでそのぶんシャープするのです(図6)。
このシャープが、ブリッジ部のアジャスターで調整できる範囲であればよい
のですが、往々にして合わせきれません。そうするとまたロックナットを緩
めてペグで少しチューニングをさげてからロックナットを締め直してアジャ
スターを回して、これで合えばよいですが、また合わなければ、ロックナッ
トを緩めてペグを回して・・・・・なんともめんどうくさいですね。
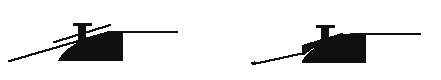 図6
図6
そこでストリングガイドが登場するのです。あらかじめ弦がナットに密着
するようにストリングガイドを設定しておけば(図7)、ロックナットを締
め込んでもチューニングの変化はわずかで、容易にアジャスターで微調する
ことが出来るようになります。
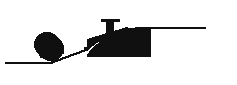 図7
図7
故にあれは単にストリングガイドであり、それ以上でも以下でもないと思
うのです。
あのバーについてとんでもないことをいう人がいて本当にびっくりしまし
た。なんでも、あれの高さを変えると、ロックナットで固定しているにも関
わらず、「テンション」が変わって、チョーキングのしやすさが変わったり、
弦のビビリかたとかが変わるそうです。彼は「プロ」のリペアマンです・・??
さて前置きはこれぐらいにして本題に入りましょう。具体的に各部につい
て考察し、調整の基準を述べてみます。
↑back to top(このページの最初に戻る)
←前の章へ
次の章へ→
←←目次に戻る
Copyright(C)1993-2004 Jin TERADA, All Rights Reserved.
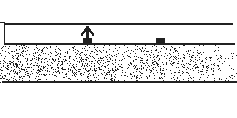 図1
図1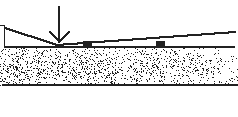 図2
図2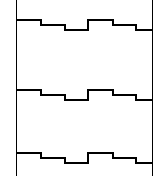 図3
図3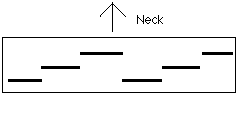 図4
図4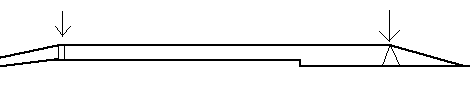 図5
図5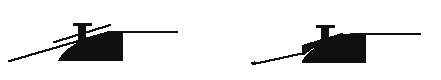 図6
図6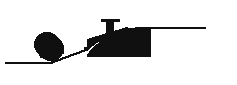 図7
図7