�@
�@
�d���A�_�v�^����2,�������ߓd���A�_�v�^
�d���A�_�v�^�Ɋւ��郊�|�[�g��ǂ�����u����͂ǂ����낤�H�v��
�A�_�v�^���������Ă��܂����BRoland BOSS PSA-100G�ł��B
�L���Ȑ��i�Ȃ̂ɁA�c�O�Ȃ���l�͎����Ă��Ȃ������̂ł��B
���������Ă݂�Ƃ������ɑ�ϗǂ����̂ł����B
�n���m�C�Y�̓f�W�e�b�N�Ɠ��l�ɑ�Ϗ��Ȃ��A�Â��ł��B
�d�����͂����Ă݂܂����B��i��9V�@200mA�ł��B
�����ׁ@�@�@�@�@9.16V
15mA���������@�@9.15V
30mA���������@�@9.14V
�D�G�ł��ˁB��������艻����Ă���悤�ł��B
�f�W�e�b�NPS200R�ƃ{�XPSA-100G�ł͓d�����Ⴂ�܂��B�i9.6V��9V�j
�G�t�F�N�^�[�ɂ���Ă͂��̉e��������̂��L�邩���m��܂���B
OPERATION3�ł͎���G�������܂��B
PSA-100G�̂ق�������ɓ������o�܂��B
PS200R�́A����ɔ�r���āA������������ۂ��L��܂��B
�Ⴂ�͔����ŁA�ǂ����I�Ԃ��͂܂��ɍD�݂ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�d���e�ʂ� PSA-100G��200mA, PS200R��300mA�Ȃ̂ŁA�K�v�Ƃ���d��
�Ƃ����̂��I���̍ۂ̗v�f�ɂȂ邩���m��܂���B
�����̃G�t�F�N�^�[��ڑ����鎞�ɂ͊e�G�t�F�N�^�[�̏���d���𑫂���
����ɂ�����x�̗]�T�����Ă����̂��ǂ��Ǝv���܂��B�K�i�M���M���Ŏg����
���Ȃ�M�������Ƃ�����܂��B
�������E�E�E����ɂ��Ă��E�E�E�Ƃɓ]�����Ă���6�̃_���A�_�v�^��
���������낤�Ǝv�����Ƃ�����ł��B
�Q�l�ɂ��Ă��������܂��ƍK���ł��B
(2005.04.14)
��back to top
�@
�d���A�_�v�^����
�G�t�F�N�^�[�p�̃R���p�N�g�ȓd���A�_�v�^�ɂ��Ă̑���ł��B
�O��̃��|�[�g��[A]�Ƃ������̂��X��2�w���������܂����B
�ʔ������ƂɁA����w���������̂͑O��̃��|�[�g�̂��̂Ɣ����ɈقȂ��Ă��܂��B
�P�[�X�̃��[���h��x���ɈႢ�������܂��B���ꂪ���b�g�ɂ����̂Ȃ̂�
���邢�͍H��̈Ⴂ�Ȃ̂��肩�ł͂���܂���B
�O��Ɠ��l��OPERATION3�Ńm�C�Y���`�F�b�N���܂����B
2�Ƃ����Ƀ��[�m�C�Y�ł��B����͗ǂ��ł��B
�d�������肵�Ă݂܂����B��i��9.6V�ł��B
���������ׂ̏ꍇ����
[I]-----9.80V
[II]-----9.67V
[III]-----9.70V
������20�`25mA�������ꍇ�����@
[I]-----9.79V
[II]-----9.66V
[III]-----9.68V
������40�`50mA�������ꍇ����
[I]-----9.78V
[II]-----9.65V
[III]-----9.66V
�����̒ʂ��ϗD�G�ł��B
����͂����߂ł���Ǝv���܂��̂ŁA���i���\�����Ă��������܂��B
[I] �̓f�W�e�b�N��CROSSROADS�ɕt�����Ă���PS200R-100�ł��B
[II] �� [III] �͒P�̔���̃f�W�e�b�NAP-2(PS200R-100�j�ł��B
��{�I�ɑS���������i�̂͂��ł��B
�o�͒�i9.6V��300mA�A�艿�́�2500�ł��B
���̐��\�ł��̉��i�́A�܂������̂����������Ǝv���܂��B
�O��e�X�g�����m�C�Y���傫��������d���ϓ����傫�������肷����̂ł��A
�قړ������i�тŔ̔�����Ă܂��B
���[�J�[�ɕ����Ă݂�Ɠ��Ƀ��M�����[�V�����̌����ڎw������H�ɂȂ��Ă���
�����ŁA�t���i�̕��̔��ɂ͏��������肰�Ȃ� [REGULATED] �Ə����Ă���܂��B
�P�̔���̔��ɂ͓��ɂ��̂悤�ȋL�ڂ͂���܂���B�����Ƒ傫���A�s�[�����Ă�
�ǂ��̂ɁE�E�Ǝv���Ă��܂��܂����B
�O��Ɠd���A�_�v�^�����Ă��܂������A�s��ɂ�����̂̂����̂ق�̈ꕔ
�ł��B�e�X�g���Ȃ��������̂̒��ɂ��f�W�e�b�NPS200R-100�̂悤�Ȑ��\��
���������̂����邩������܂���B
�F������������������܂��Ƒ�ς��肪�����ł��B
(2005.04.09)
��back to top
�@
�d���A�_�v�^�iAC-DC�j�ɂ�����
�R���p�N�g�G�t�F�N�^�[�̓d���Ƃ��āA�l�͓d�r�̎g�p�������߂��Ă��܂����B
�Ƃ��낪�ŋ߂̌X���Ƃ��ēd�r�ł͔��ɕs�o�ςɂȂ��Ă��܂��G�t�F�N�^�[��
�ӂ��Ă��܂����B�f�W�^�����ł�������A�`���[�u�̎g�p�ł�������A���R��
���낢�날��܂����A�d���A�_�v�^�̎g�p���������Ȃ��ɂȂ��Ă��܂����B
�ł͍����ʂ��Ă���R���p�N�g�ȓd���A�_�v�^�̒��x�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B
�莝���̃A�_�v�^6�@��Ǝ���̎����p�d�����r���Ă݂܂����̂ŁA���ʂ��
�������܂��B
�����Ɏg�����G�t�F�N�^�[��ALEATORIK��OPERATION3�ł��B
�d�r�Ŏg�p�����ꍇ�⎩��̎����p�d���̂����A�G�t�F�N�^�[���g�ł�
�n���m�C�Y�i�u�[�[���Ƃ����ቹ�̃m�C�Y�j�͔��ʂł��Ȃ����x���ɂ���܂��B
�ƂĂ��Â��ł��B����̎����p�d���͂������ʂ�3�[�q���M�����[�^�ŁA����
�����\�Ƃ����킯�ł͂���܂���B
ALEATORIK�͂���ʂ̓d���͓�����O�ɋ����������̂Ǝv���Đv���܂����B
�������A�s�̂̓d���A�_�v�^�ɂ͂��낢��Ȃ��̂������āAALEATORIK�͎g��
�A�_�v�^�ɂ��e�����傫�����Ƃ��킩��܂����B
���݂ɑ��̃G�t�F�N�^�[�Ŏ����Ă݂�ƁA�e���̎��͗l�X�ł���ALEATORIK
�قǂł͂Ȃ����̂�����܂��BALEATORIK�ł͒ቹ����\�������邭�炢�̂���
����̂ŁA����̉e�����Ȃ��E�E�Ƃ��v���Ă���܂����A�ڎw�����T�E���h����
�l���āA���̂Ƃ���ύX�̗\��͂���܂���B
�O�q�����悤��ALEATORIK������̎����p�d���Ŏg�p����ƑS���Â��ł��B
�s�̕i�̓d���A�_�v�^��6�@��̂����̂ЂƂ@A�@�͎����p�d���Ɠ����悤��
�Â��ł��B
3�@��@B�@�Ɓ@C�AD�@�̓n���m�C�Y������������̂̃V�r�A�ȏ����łȂ����
�g�p�ɂ�����Ǝv���܂����B�̂����2�@��@E�AF�@�͔��ɑ傫�ȃn���m�C�Y
���o�܂��B����͎g�p�ł��܂���B
�R���p�N�g�Ȏs�̕i�ɂ͕�����H���\���łȂ����̂�����̂�������܂���B
��Ƃ��ẮA�Ƃ肠�����A�S���Â��ȓd���A�_�v�^���s�̕i�ɂ���̂ŁA����
���������̂�T���Ē��������Ȃ��̂��ȂƎv���Ă���܂��B�y��̃{�����[����
�i���Ă��u�[���Ƃ����m�C�Y���C�ɂȂ�Ƃ��ɂ́A�d���A�_�v�^���`�F�b�N����
�ɓ���Ă݂Ă��������B
�\�Ȍ���d�r���g���Ƃ����̂��A��͂肨�����߂ł��B
�A�_�v�^��������Ɖ����ς��A�Ƃ����ӌ������������Ŏ��ɂ��܂��B
�d���A�_�v�^�Ɋւ��Ă̓n���m�C�Y�����ł͂Ȃ��A�o�͓d���̌덷��e�ʂȂǁA
���̖ʂł��`�F�b�N���ׂ���������������悤�Ɏv���܂��B
�莝���̎s�̕i�ɂ�9V�@DC�i1����9.6V�j�Ə����Ă���܂����A���ۂɑ�����
�݂�Ǝ��̂悤�Ȍ��ʂł����B
�i���ɂ͂Ȃ��Ȃ��d�������肵�Ȃ����̂�����̂ł����ƌX����������x�ł��B
�@����덷�ɂ��Ă͂��e�͂��������j
���������ׂ̏ꍇ����
����i��i9V�j---�@8.99V
A�i��i9.6V�j----�@9.80V
B--------------�@10.89V
C--------------�@15.21V
D--------------�@13.60V
E--------------�@13.38V
F-------------�@12.82V
������20�`25mA�������ꍇ����
����i��i9V�j---�@8.95V
A�i��i9.6V�j----�@9.79V
B--------------�@10.22V
C--------------�@13.55V
D--------------�@12.93V
E--------------�@13.06V
F-------------�@12.65V
������40�`50mA�������ꍇ����
����i��i9V�j---�@8.91V
A�i��i9.6V�j----�@9.78V
B--------------�@10.04V
C--------------�@12.80V
D--------------�@12.65V
E--------------�@12.84V
F-------------�@12.46v
�Ƃ������ʂł����B���ꂭ�炢��������Ɖ�������ē��R�Ƃ����C�����܂��B
B����F�͒�i9V�̂͂��̎s�̕i�ł��B��������d���͍����ł��B
�m�C�Y�����Ȃ������@A�i��i9.6�u�j�͓d���̌덷������x���ǍD�ł��B
B�@�͂܂��܂��ł��B
C�@�͕��ׂɂ���ēd�����ϓ����߂��ł��B
D�@�͂�����Ɠd�������߂ł����A�Ȃ�Ƃ��g����Ǝv���܂��B
E�@�͓d���ϓ��͏��Ȃ߂ł����A�n���m�C�Y�������ă_���ł��B
F�@��E�Ɠ��l�ŁA�n���m�C�Y���傫���Ďg���܂���B
���ׂ̕ϓ��ɂ���ēd���ω����傫�����̂́A1�̃A�_�v�^�ɕ����̃G�t�F�N�^�[
��ڑ�����ꍇ�A���ӂ��K�v�ł��B�G�t�F�N�^�[�̌��𑝂₵�Ă����Ɠd����
�ǂ�ǂ����Ă����ĉ����ς���Ă��܂��܂��B
���ʂɍl���Đ�Ɂ@A�@���ǂ��ł��ˁB
�m�C�Y�����Ȃ��A�d�����K�ł���A���ׂ̕ϓ��ɂ��e�������Ȃ��ł��B
A�@�ɂ��Ă͂܂�1�����e�X�g���Ă��Ȃ����߁A�����̌̂������Ă݂�
�������ʂ��ǂ���ΐ��i�������m�点���悤�Ǝv���܂��B
�����������Ԃ����������B
�Ȃɂ͂Ƃ�����d���A�_�v�^�ɂ͂����ӂ��I
��낵�����肢�������܂��B
(2005.4.6)
��back to top
�@
���f�����O�̐V���� Eric Clapton Crossroads
���f�����O�͂Ƃ��Ƃ��s���|�C���g�̑_�������ɂȂ��Ă��܂����B
�G���b�N�E�N���v�g���@Crossroads �́A�A�[�`�X�g�����������邾���ł͂Ȃ��A
�v���Z�b�g���u�Ȗ��v�ł������肵�āA���̐V�����������ے�������̂̂悤��
�v���܂��B
�f�W�e�b�N���甭�\���ꂽ���̃G�t�F�N�^�[�̓N���v�g���{�l�ƃM�^�[�e�N��
���[�E�W���N�\���ɂ���ĊďC����Ă��邻���ł��B
�K���Ȃ��Ƃɓ���o���܂����̂ŕ������܂��B
��������MODEL��CTRL��������
�R���g���[���m�u�͂S�ł��B
LEVEL�ACTRL1�ACTRL2�AMODEL�ł��B
CTRL1�ACTRL2 ��MODEL�ɂ���ĈقȂ����������^�����Ă��܂��B
�v���Z�b�g�iMODEL)�̓��e�������Ă����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@CTRL1 �@CTRL2
(1) Sunshine of Your Love (1967) Distortion Gain Tone
(2) Crossroads (1968) Distortion Gain Tone
(3) Badge (1969) Overdrive Gain Leslie Speed
(4) Layla (1970) Distortion Gain Tone
(5) LayDownSally (1977) Distortion Gain Tone
(6) Layla Unplugged (1992) Body Amount Reverb Level
(7) Reptile (2001) Overdrive Gain Reverb Level
�o�͂͂Q�n�������āAAmp��Mixer�p�ł��B��{�I�Ƀ��m�ł����i�R�j�Ɓi�U�j��
�����̃A�E�g���g���ăX�e���I�o�͂ɂȂ�܂��B
�������������o���Ă݂遖������
�M�^�[���q���ʼn����o���Ă݂܂��B�ǂꂭ�炢�����Ă��鉹�̍Č���������̂�
�����[���Ƃ���ł��傤���A�g�p�M�^�[��F�X�����Ă݂�ƁA����ɂƂ��Ȃ���
���R�ł��������ς��܂��B�Ƃ������Ƃ́A���̃v���Z�b�g�̍Č��ɂ́A�܂�
����Ȃ�̃M�^�[���g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�܂��A���v�̏��قȂ�킯�ł����A������Ă���Ȃ̃T�E���h�Č��͂��Ȃ�
���肳�ꂽ�����Ŏ��������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�l�͊�{�I�ɁA���������Ɏ��Ă���Ƃ����悤�Ȃ��ƂɁA���܂肱�����͗L
��܂���B
�����B�����ʂ��Ă���V�[���Ńx�X�g�ȉ����o��������OK���ƍl���Ă��܂��B
�]���āA���̃G�t�F�N�^�[�ɂ����Ă��A�g���鉹���o���₷���̂��A�O���Ƃ���
�����o����̂��A�Ƃ������Ƃ����������̒��S�ɂȂ�܂��B�e�v���Z�b�g�̖���
�͂��ꂼ��̃T�E���h�X���́u�ے��I�Ȉ��́v�Ƃ��ė������������ǂ��Ǝv����
�܂��B
�i�P�j�̓~�b�h�����W�������������̂ł��B���̂悤�ȉ��͂悭���E���I���ɂ�
�Ăǂ����ɌŒ肵�č�邱�Ƃ������ł��B���ꂪ�ȒP�ɓ�����̂͂�����Ɗ�
�����ł��B
���̃T�E���h�����������Ǝv���ƃg�[���̐ݒ肪�d�v���Ƃ������܂��B�y���
�g�[���R���g���[����CTRL2�̃g�[���ł͂��̓��������قȂ�܂��̂ŁA�y���
�g�[�������܂��g����Ηǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B�\�ł���s�b�N�A�b�v�̕���
���d�����ĉ��F������Ƃ����H�v���L�������m��܂���B�i�Ⴆ���X�|�[��
�ȂǂŃs�b�N�A�b�v�Z���N�^�[���Z���^�[�ɂ��܂��B�����āA�ǂ��炩��VOL��
�ǂ�ǂ�i���āA�����Ȃ��Ȃ鐡�O2�Ƃ�3�ɃZ�b�g���܂��B
�g�[���R���g���[�����i��̂Ƃ͈قȂ��������̉��������܂��B�o���ł̓���
�����i�荞��ł����Ƃ��Ȃ�ǂ������ɂȂ�܂��j
�i�Q�j�s�p�I�Șc�ݕ��ł��B���ʂɎg����㎿�ȃf�B�X�g�[�V�������ƌ����܂��B
�i�R�j�c�݂������I�ȃ��Y���[�T�E���h�B�O�q�̒ʂ�X�e���I�A�E�g�Ȃ̂ŁA
�@�@�@�A���v���Q��g����Ƃ����ʓI�ł��B
�i�S�j���Ƃ��ƃ`�����v�ō�������Ƃ͎v���Ȃ������������Ă��܂��B���̃��[
�@�@�@�̊����͑�D���ł��B�A���T���u���̒��Ńo�b�e�B���O���Ȃ��悤�Ɏg��
�@�@�@��Ηǂ��̂ł����B
�i�T�j���܂�c�܂Ȃ������B�N���[���E�N�����`�ł��傤���BCTRL1����������
�@�@�@��Ɖ��̌`�������悤�Ɏv���܂��B
�i�U�j�Ȃ�ƁA�A���v���O�h�̎��̃A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�̉��ɂȂ邻���ł��B
�@�@�@CTRL1�Ń{�f�B�̂Ȃ�����R���g���[���ł��܂��B000-42�̃f�[�^���Ƃ��B
�@�@�@����͂Ƃ������A�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�̃V�~�����[�V�����Ƃ��ďG��
�@�@�@�ł��B���܂ŕ��������̂̓��Ńx�X�g�̕��ނ����m��܂���B���o�[�u��
�@�@�@�[���ɂ��Ă��Ɠ��̋��������L��܂��B�{���̃A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[��
�@�@�@�̂��̂̉��Ƃ͌����܂��A����͂���Ƃ��Ďg���鉹���Ǝv���܂��B
�@�@�@�X�e���I�A�E�g�ł����A���m�ł��ǂ������ł��B
�i�V�j�K�x�ɘc�ޏa�߂ȉ��₩�ȉ��ł��B���o�[�u�����Ă���̂Ń��[�f�B�[
�@�@�@�Ȉ�ۂł��B
���������G���A�R��x�[�X�ł���������
�S�̓I�ȏo���Ƃ��đ�ϋC�ɓ����Ă���܂��B�d�r����R���Ԃ��������Ȃ��̂�
�c�O�ł����A�p���[�T�v���C���t�����Ă��܂��̂Ŏ��ۂ̎g�p��͖��L��܂���B
�i�p�b�P�[�W�ɂ̓p���[�T�v���C�̑��Ƀs�b�N���P���ƃG�t�F�N�^�[�p�|�[�`��
�����Ă��܂��B�|�[�`�͂Ȃ����������ăG�t�F�N�^�[�������܂�܂���B�Ȃɂ�
�̊ԈႢ�炵���A���[�U�[�o�^������Ό�����傤�Ǘǂ��T�C�Y�̂��̂𑗂���
����邻���ł��B
�s���Q�̃|�[�`����ɓ��邱�ƂɂȂ�A�������ă��b�L�[�����m��܂���j
�f�W�e�b�N�̑_���͖{���ɃN���v�g���T�E���h�̍Č��������̂ł��傤���B
�f�W�e�b�N�̎v�f�����̂����m��܂��A�l�ɂ́A�N���v�g���T�E���h��
����Ă������ʂɃG�t�F�N�^�[�Ƃ��āA�ƂĂ��g������̗ǂ����̂Ɏv����̂ł��B
�o���G�[�V�����̍����ɔ[���������Ă��܂��܂��B�s���|�C���g�ł���悤��
�����Ď��͂����������L���J�o�[���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�n���o�b�J�[��V���O���R�C���ł̃e�X�g����i�����܂����̂ő��̂��̂ł�
�����Ă݂܂����B
�G���A�R�i�Ƃ����Ă��X�g���g�̃s�G�]�E�u���b�W�T�h���j�������Ă݂�ƁA
�ЂƖ�������Ȃ��Ȃ��g���鉹�ł��B�s�v�ȑш悪���܂��}�X�N�����悤�ł��B
����ł̓x�[�X�͂ǂ��ł��傤���B�W���Y�x�[�X�^�C�v��ڑ����Ă݂܂����B
������ӊO�Ƃ������肵�����ŁA�ʔ����ł��B�M�^�[�Ŏg�p�����艹�ʂ���
�������C�����܂����Ȃ��ł��傤�B
LEVEL�܂݂������グ���݂ɂ��Ď����Ă��܂��B����ƃZ�b�e�B���O�ɂ����
�����ɋ�C�����t�������悤�Ɋ����܂��B���ʂ̃f�B�X�g�[�V�����Ƃ͊��G��
�قȂ�܂�����������\�D���ł��B
�H�v����ŗl�X�ȃV�[���Ŋ���o�������ł��B���̃M�^�[���R�[�f�B���O���y��
�݂ł��B
�����������̃��f���́H��������
�N���v�g�����f���̏o�����ǂ������̂ŁA����ɑ������f���ւ̊��҂��傫���ł��B
GuitarPlayer��(USA)1�����ɂ��A�G���N�g���b�N���f�Bst�ŁA�f�W�e�b�N��
�G���W�j�A�ƁA�ւ��̂������G���W�j�A�ƂŁA�W�~�E�w���h���b�N�X�̃T�E���h
�̉�͂�����������ł��B
2�y�[�W�̃��|�L���ŁA�̂̃e�[�v���烉�t�~�b�N�X�����l�q�Ȃǂ����|�[�g��
��Ă��܂��B
�����ɂ����A�����Ԃ��Ȃ����\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
NAMM�V���E�ɂ̓��E�y�_���̌`�ŏo�i����Ă����Ƃ̂��Ƃł����A�W�~�E�w���h
���b�N�X�̂ǂ̃T�E���h�����������̂��A�ڍׂ��҂��ǂ������ł��B
���������⑫�@�f�W�^���N���b�v��������
��ʓI�Ƀf�W�^���@��ł̓f�W�^�������ł̃N���b�v�������g���������߂��
�܂��B
�A�i���O�����Řc�ނ̂Ƃ͈قȂ��āA�f�W�^�������ł̘c�݂͉������Ƃ������ł��B
���̐��i�̎戵���������ł��G����Ă��܂����A�u�u�`�u�`�v�����m�C�Y��
�����������ɂ͓��̓��x�����������鋰�ꂪ�L��܂��B����CROSSROADS�̑O��
���̃G�t�F�N�^�[�Ȃǂ����Ă���ꍇ�͂���̏o�̓��x�������������Ă݂�
�������B�M�^�[���̏ꍇ�ł��s�b�N�A�b�v�̏o�͂��傫������ƃN���[���n��
�v���O�����Řc�ނ��Ƃ��L��悤�ł��B�y���VOL�����������̘c�݂�����
���邱�Ƃ��ł��܂��B
�f�W�^���@����g�����Ȃ��ɂ̓��x���W�Ɏ���Ӑ[���Ȃ邱�Ƃ��K�v�ł��B
(2005.03.25)
��back to top
�@
�f�W�]�E�N�Ɋւ���2.3�̎���
�Ђ���Ƃ�������{���̃M�^�[�ōł��L���Ȃ̂́uZO-3�v��������܂���B
���̃]�E����̐V�^����肵�܂����̂ŁA�������܂��B
Digi-ZO ULTIMA �ł��B
�傫���ς�����_�̓X�P�[�����m�[�}���ɂȂ������Ƃł��B�قڂ�����M�u�\��
�X�P�[���ɂȂ��Ă��܂��B�ȑO�̃V���[�g�X�P�[�����A���̓��b�P���̃V���[�g
�X�P�[���Ɏ��Ă��āA�����ɍD���������肷��̂ł����E�E�E�E
��ʓI�ɂ͍���̂��̂̕����D�܂��̂�������܂���B�^�L���̎�̃M�^���X
�g�߂�A�����u���x�̂̓��M�����[�����炷�����~�����v�ƌ����Ă��܂����B
�X�P�[���������Ȃ�������ł��傤���A����Ƃ��傫�Ȋ�Ղ���������邽�߂�
���傤���A�{�f�B����傫���Ȃ��Ă��܂��B�d���͐�p�X�g���b�v��d�r�S��
���݂Ŗ�3.6kg�ł��B
�ȑO�̃A�[���t���]�E����ɔ�̃X�g���b�v��������ԂŖ�2.8kg�ł�����A
��͂菭�������d���Ȃ��Ă��܂��B
�������������̂悤�Ȓ�����������
�X�g�b�N��Ԃł��ǂ���Ԃł������A�l�̍D�݂���A������������܂����B
�l�b�N�����A�t���b�g���肠�킹�A�t���b�g���`�ȂǁA�����̍�Ƃł��B
�i�b�g�͍���͕ύX�����ɁA�������u�f����PTFE���p�ŏ����������߂܂����B
�X�g�����O���e�[�i�[�͌���ł����͏��Ȃ��̂ł����A�O���t�e�b�N�ɕύX��
�܂����B���[�J�[�d�l�ł̓��e�[�i�[��1�A2�������ɂ��Ă��܂����A�ߋ��̌o
������R���ɂ����܂����B
�u���b�W�T�h���͖l�ɂ͌ł�����悤�Ɋ�����̂ł����A�Ƃ肠��������͂���
�܂܂ŁA�i�b�g�Ɠ������������u�f����PTFE��h��܂����B
�`���[�j���O�̌X���͑�ϗǂ��A�J������n�C�t���b�g�܂Ŗ����ł���͈͂ɓ���
�Ă��܂��B
���[�J�[�w��ł͌��̊���������1�A2�A3���͋t�����ł��B���̊p�x�̊W����A
���̕������萫�����������ł��B
�������l�͂��ꂪ�D���ł͂Ȃ��̂ł��ׂď������ɕύX���܂����B��ɏ����܂�
���悤�Ɋe���̊�����l���������߁A�������ł��`���[�j���O�̈��萫�͑�ϗ�
�D�ł��B
����ƁA����͒��ӂ��Ăق����̂ł����A���[�J�[���o���ɒ����Ă��錷��
���܂�悭�Ȃ������ł��B�P�ɂ���Ȃ̂�������܂��A����ł͂���
�M�^�[�̐^����������Ȃ��Ǝv���܂��B
�o��������ɑ��̐M���ł��錷�ɒ���ւ��Ă���A�T�E���h��e���̃`�F�b�N
�����Ăق����ł��B���̌��Ɋւ��Ă̓��[�J�[�ɘA�����ĉ��P�����肢���Ă��܂��B
�������Ă���G�t�F�N�^�[�͊ȒP�Ɍ����f�W�e�b�N�̃}���`�����̂܂ܓ�����
����悤�Ȃ��̂ŁA���i�����Ǝv���܂��B�v���Z�b�g�̃G�t�F�N�g�ݒ�͂������
���߂����ȂƂ������������܂����A�G�f�B�b�g�͑�ϗe�Ղł��̂ŁA������
�T�E���h�����₷���Ǝv���܂��B
���Y���{�b�N�X�ƃ`���[�j���O���[�^�[�͕K�v�ɂ��ď\���Ƃ��������ł��B
�s�b�N�A�b�v�̓m�[�}���̂܂܂ł��B�ȑO�̃]�E����̓_���J���ɕύX���Ă���
�D�]�ł����B�����������ƕύX�����������߂܂������A����Ńt�B�[�h�o�b�N
�����ɔ�����������̂ŁA����Ɏ䂩��Ď��t���Ȃ����Ƃɂ��܂����B
�s�b�N�A�b�v�����́A�ύX����ۂɒ��ӂ���悤�ɏ�����Ă��܂����A�l�͏���
�グ�Ă��܂��܂����B
�X�s�[�J�[��FOSTEX���g���Ă��܂��B
���ʂ͔��ɑ傫���o���܂����܂��ő剹�ʂ͎��������Ƃ�����܂���B
�������������������Ă݂遖����������
���ʂɎg�����ɂ͂���ő�ϊy�����g���܂��B
���g�����Ďg�����Ƃ��l����̂��y�����̂ŁA�����������Ă݂܂����B
��قǂ��t�B�[�h�o�b�N���������Ə����܂������A����������Ɛ��������Ƃ���
���݂ł��B
�����܂�AUX�W���b�N��z�����͂������ɂ��̂܂��O���܂��B�K���ȃr�j�[��
�@�@�ȂǂŐ≏���ă{�f�B�[���̃X�y�[�X�ɓ]�����Ă����܂��B�i�����K�v�ɂ�
�@�@��Έꉞ�����Ɏg����j
����AUX�W���b�N�����Ă����ꏊ�Ƀ��m�W���b�N�����t���܂��B
�����s�b�N�A�b�v����z�����|�b�g�ɐڑ�����A�|�b�g�̒��_�����Ղɔz����
�@�@��Ă܂��B���̒��_����p�����āA�W���b�N�̃z�b�g�[�q�ɔz�����܂��B
�@�@�R�[���h�[�q�i�A�[�X�j���̓|�b�g�̃P�[�X����Ƃ�Ηǂ��ł��傤�B
����Ńs�b�N�A�b�v�̉���Ɨ����Ď��o���܂��B���ʂ̓|�b�g�̓����̃c�}�~
�ŃR���g���[���ł��܂��B
�d�����I���ɂ��Ȃ��Ă������o����̂ŁA�Ȃɂ��ƕ֗��ł��B
�������������g�p��@1�i���j�@������������
�����̃|�b�g�͍ő�ɂ��Ă����܂��B�{���̃A�E�g�W���b�N�ɂ͉����ڑ�����
����B
�܂��]�E����{�̂̉����f�B�X�g�[�V�����ɂ��Ă����܂��B�����ă|�b�g�̊O��
�̃c�}�~���ő�ɏグ���Ƃ��ɂ��傤�NjC�����悭�t�B�[�h�o�b�N����悤�ɉ�
�ʂ�ݒ肵�Ă����܂��B
�ǂ������ł���ΊO���̃|�b�g���ŏ��ɂ��Ė{�̂��特���o�Ȃ��悤�ɂ��Ă���
�܂��B
���ɐ�قǍ�����s�b�N�A�b�v�̃_�C���N�g�A�E�g����O���̃A���v�Ȃǂɐڑ�
���܂��B
�Ċm�F���܂����A�����̃|�b�g�͍ő�A�O���͍ŏ��ł��B
�O���A���v�̉��F���C�ɓ��������̂ɒ������܂��B�]�E����{�̂̉��F�Ƃ͊W
�Ȃ��ݒ�ł��܂��̂ŁA�D�݂ɍ��킹�Đݒ肵�Ă��������B�����ł͌��ʂ��m�F
���邽�߂ɘc���F���������߂ł��B
���F�����܂����班���e���Ȃ��烍���O�g�[���̉ӏ��Ń|�b�g�̊O��������Ə�
���Ă݂܂��B
�]�E����{�̂Ńt�B�[�h�o�b�N����ƂƂ��ɊO���̃A���v������t�B�[�h�o�b�N
�T�E���h���o��͂��ł��B
����͌����I�ɃT�X�e�B�i�[�݂����Ȃ��̂ł��B�d���I�ɂ���Ă��邩�ǂ�����
�����Ⴂ�͂���܂����B
���܂��ݒ�ł���Ɩʔ����g����Ǝv���܂��B�C�����̂悢�����O�g�[����\��
���t�B�[�h�o�b�N�T�E���h�ȂǂȂǁB
�������������g�p��@2�@������������
������s�b�N�A�b�v�A�E�g�̃W���b�N�́A�t�ɍl����A���̃M�^�[�̃A�E�g��
�����ɐڑ����ăf�W�]�E�N�̃G�t�F�N�^�[�ƃA���v���g�p���邱�Ƃ��o���܂��B
�O���̃M�^�[�ƃf�W�]�E�N�̃s�b�N�A�b�v���p���ɂȂ�����Ԃł��̂Ŏ�̒�
�ӂ��K�v�ł����A����Ă݂�킩��Ǝv���܂��B�i������t��Ɏ������
�̃g���b�N�v���C���\�ł��j
�f�W�]�E�N�̓����̃|�b�g�����ڂ肫��Ɓi�p���ł��̂Łj�����o�Ȃ��Ȃ�܂��B
�����|�b�g���グ����ԂŊO���M�^�[���f�W�]�E�N�������Ƃ��e���Ή����o�܂��B
�������������g�p��@3�i���j�@������������
�g�p��@1�ł킩��悤�ɁA�Q�n���̏o�͂Ƃ��Ďg�p�ł��܂��B
�A���v����p�ӂ��āA�s�b�N�A�b�v�A�E�g�̃_�C���N�g�A�E�g�����ځA�{��
�̏o�͂���ڂɐڑ����܂��B
�|�b�g�̓������ő�A�O�����ŏ��ɂ��Ă����܂��B
����ň��ڂ̃A���v���炾�������o�܂��̂ŗႦ�N���[���g�[���ɐݒ肵��
���B
���ɊO���̃|�b�g���グ��Ɠ��ڂ̃A���v�������܂��̂ŁA�f�B�X�g�[�V����
��
��A���̃G�t�F�N�g�Ȃ�قȂ������F��t�������邱�Ƃ��o���܂��B
��̉��F�̍������͊O���̃|�b�g���Ē��߂��邾���ł��̂ŁA�����
�ȒP�ł��B
���̎�@�̉��p�͈͂͂����L����������܂���B
�i���j�g�p��1��3�ł͊O���̃|�b�g�����ʂ̒����ł���悤�ȃv���O������I��
�ł��������B
�O���̃|�b�g�����E��[�~�[�Ȃǂ̃R���g���[���ł���ꍇ������܂��B
���낢�뎎���Ă��܂����A�y�����ł��B�����̎Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B
(2005.03.12)
��back to top
�@
LES TREM�������Ă݂�


LesPaul���g���Ă��āA�A�[������������Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����܂��B
��ɂƂ����킯�ł͂Ȃ��A���R�[�f�B���O�̂���V�[���ŁA���������Ɏg������
�Ǝv�����Ƃ�����̂ł��B
�r�O�X�r�[��������Ηǂ��̂ł����A���H���K�v�ł����A�͂������Ƃ���
�r�X�����c�邱�ƂɂȂ�܂��B
�ŁA�����Ȃ����ƒT���Ă�����ALES TREM�Ƃ����̂�����܂����B
�\���̓r�O�X�r�[�̕ό`�ł����A�e�[���s�[�X�̑���Ɏ��t���ł��āA
�قƂ�ǖ����H�ł��B�K�v�ȂƂ��������t������Ȃ�֗������ł��B
���������Ă݂܂����B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�������Z�b�g���e������
�g���������j�b�g
�X�v�����O
�X�v�����O����@3���
���b�V���@2���
�}�E���e�B���O�|�X�g�@2���
6�p�����`�@2�{
���������t�����@������
�����͂����A�e�[���s�[�X�����O���B
�}�E���e�B���O�|�X�g���Ă͂����B
�t���̃|�X�g�̓��g���b�N��M8��5/16-24 ������̂ŁA���̃M�^�[��
���������̂�I��ł����B
�Ƃ肠�����A�����̃��b�V�����ꖇ����āA�I�|�X�g�����t����B
���j�b�g����둤�������āA�|�X�g���y�����߂���ŌŒ肵�Ă����B
�X�v�����O����ƃX�v�����O������̈ʒu�ɋ��ݍ��ށB����̉��ɕt����
�v���X�e�B�b�N���b�V���������ƁA�{�f�B�[�ɏ������Ȃ��B
�X�v�����O�����3��ނ̍���������̂ŁA�g���₷���ʒu�ɃA�[��������
���̂�I�ԁB
�Ƃ肠�����́A�^�̍����̂��̂����āA�l�q������B
�X�v�����O���ނ̂����܂����������������Ƃ��ɂ͖����������A�|�X�g���ɂ߂�
���j�b�g�������グ�āA�X�v�����O������ł���|�X�g�����ߍ���ł����Ɗy��
��Ƃł���B
�����ă`���[�j���O����B
�������Z�b�e�B���O������
�܂��A�A�[���̍���������B�g���₷���ʒu�ɖ����Ƃ��́A�ʂ̍����̃X�v�����O
����ɕς��Ă݂�B
���ɁA�Â��ɃA�[���A�b�v���Ă݂āA���j�b�g��[�ƃ{�f�B�Ƃ̃N���A�����X
�i���ԁj������B
�{�f�B�Ɗ��������Ȃ�A����l����B
���j�b�g���グ�����Ǝv���ꍇ�A�|�X�g�̃��b�V���ɓK�x�ȃX�y�[�T�[��t����
����Ηǂ��B
�l�̏ꍇ�A��5mm���̂��̂�t�������Ă���B�i��q�j
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
��������́H������
�A�[���̓����̓X���[�Y�ŁA�`���[�j���O�̈��萫���ǂ��ł��B
�������A�ڂ���LesPaul�ł͉������܂����ɂȂ�܂����B
�U���n�̏d�����ς�������߂��A�X�v�����O���t�����ꂽ���߂��킩��܂��A
���̐U�ꂩ�����C�ɓ���܂���B��T�Ɂu�����Ȃ����v�Ƃ͌����������̂ł����A
���Ȃ��Ƃ��l�����҂�����̂Ƃ͈قȂ��Ă��܂��܂����B
���t���̗e�Ղ���A����̑�̂̋�͂킩��܂����̂ŁA���j��]�����邱
�Ƃɂ��܂����B
����LES TREM�̓M�u�\���^�C�v�̃e�[���s�[�X���������M�^�[�Ȃ�ǂ�ɂł����
�t���o�������ł��B
�莝���̃M�^�[�ł�SG�ɍ��������ł��B
����SG��70�N�㔼�̃X�y�V�����ŁA�ȑO����U���n�̏d�ʃo�����X�Ɏ��
�^��������Ă��܂����BLesPaul�ł̕ω��̎d������l���āA�Ђ���Ƃ��āA�A�A
�Ǝv���Ď����Ă݂܂����B
����SG�ɂ��Ă����e�[���s�[�X��82g�ALES TREM�̃��j�b�g��256g�ł��B
���ʂ̓o�b�`���ł��B���̃o�����X�A���ɒቹ�悪�O���Ɨǂ��Ȃ�܂����B
�Ƃ����킯�ŁA����ɂ߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�܂��X�v�����O����͐^�̍�����I�т܂����B�v���X�e�B�b�N���b�V����
�͂����ăX�v�����O����݂̂ɂ��܂����B
����͓����ƃC���Ȃ̂ŁA�����������ʃe�[�v�Ōy���{�f�B�g�b�v�ɌŒ肷��
�悤�ɂ��܂����B
�i�h���ʂɉe�����o�邩������܂��j
�|�X�g�����̃��b�V���͂܂�������1���Ŏ����܂����B
���\�ȃA�[�~���O�����Ă����烆�j�b�g��[�Ńg�b�v�ɏ������Ă��܂��܂����B
�{�f�B�[�g�b�v�����ʂȂ̂ŁA�����Ă��܂��悤�ł��B
�莝���̖�3mm���̋������b�V�������Ă��̖��͉��������̂ł����A
���̊p�x���C�ɓ���܂���ł����B
���ǁA��5mm���̋����X�y�[�T�[������ċ��ނ��Ƃɂ��܂����B
����ŃA�[���������K�Ŏg���₷���Ȃ�܂����B
�������`���[�j���O�̈��萫������
���萫�͂����ނ˗ǍD�ł��B�������A����̗l�q���e�ׂɌ��Ă݂�ƁA�u���b�W��
����肠�肻���ł��B�A�[�~���O�ɏ]���āA�{���g�������ł���̂��킩��܂��B
���Ȃ݂Ƀi�b�g�̓O���t�e�b�N�g�����i�b�g�A�u���b�W�̓{���g���_�C���N�g��
�{�f�B�ɑł����܂�Ă�����̂ŁA�i�b�V���r���ɕύX���Ă���܂��B�T�h����
�O���t�e�b�N�ł��B
����͔��Q�ɂ悢�͂��Ȃ̂ł����A����ł������ł͂Ȃ��悤�ł��B���[���[�^�C�v
�������Ă݂����Ƃ���ł��B
�A�[���͉�]���āA�g�p���Ȃ��Ƃ��͌���ɉĂ����܂��B
�A�[����O�ɏo���Ďg�p��Ԃɂ����Ƃ��ƁA����ɉ��Ƃ��ƁA�����ɉ���
�Ⴂ�܂��B
����ɉ��Ƃ��̕������̗h�ꂪ���Ȃ��悤�ł��B
���������ӓ_�Ɠ䁖����
�A�[�������j�b�g�ɌŒ肵�Ă���2�{�̃r�X���Z���Ďア���߁A������Ɩ�����
����ƊO��Ă��܂��܂��B
�r�X���o�J�ɂȂ�₷���ł��B�i���s�����o���҂ł��j
�莝���̃r�X�̒����炿�傤�ǎg���鑾���̒��ڂ̂��̂�I�сA�O���C���_�[��
�����߂��Ă���������t���܂����B
��̕����ɂ��āB���j�b�g�̑O�ʂɏ����Ȍ���2�J�������Ă��āA����6�p�����`��
��r�X�������Ă��܂��B���ɂ͂������l�W�������Ă���܂��B�t�������`��
�ׂ������A���̃r�X�ɍ����܂��B
�������A�ǂ��l���Ă݂Ă��A���̃r�X�����̂��߂ɂ���̂������ł��܂���B
�����ŁA���{�̗A���㗝�X�ƁA�A�����J�̗L�͂ȃp�[�c������ɖ₢���킹��
�݂܂����B
�o���̓����͑S�������Łu���̃r�X�͂Ȃ�̖��ɂ������Ă��Ȃ��v�ł����B
���̂����Ȃ��Ă���̂��S���s���ł��B�����ߒ��ł��̌����K�v�������Ƃ��āA
�����i�ɂ͕s�K�v�Ȃ��̂������Ƃ��Ă��A�킴�킴�l�W�������ăr�X�����āA
����������p�̃����`��t�������Ă���̂ł��B
�����̌����߂ɂ��Ă͎肪���݂����Ă��܂��B�S����ł��B
�������֗�����������
�S�̓I�Ɍ��āA��ϗL�p�ȃp�[�c���Ǝv���܂��B�s�v�ɂȂ����犮�S�Ɍ��ʂ��
�o����̂��ǂ��ł��B
�A�[����K�v�Ƃ��Ă�����͎����Ă݂鉿�l������ƌ����܂��B
���{�ł̒艿�́�26000�ł��B
������������������������������������������������������������������������
(2005.02.20)
��back to top
�@
VOX��LINE6�̐V���i
VOX��LINE6����ӗ~�I�ȃR���p�N�g�G�t�F�N�^�[�����\����܂����B
�������肵�ăe�X�g���Ă݂܂����B
��VOX BigBen Overdrive
�`���[�u���d���Ŏg�����ӗ~��ł��B�P�O4�{�Ŗ�16���Ԏg����Ƃ̂��Ƃł��B
�c�ݕ��͑�σX���[�Y�ŁA���Ɍ֒������Ƃ��낪�Ȃ��A�u�[�X�^�[�I�Ȏg������
���C�������悢�ł��B�f�W�^���̃��f�����O���̂̑O�ɓ���Ďg���ƁA���Ȃ��
���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����W�͏����㑤�Ƀ��C�h�ɂȂ銴���ŁA���݂���Ȃ����邳���L��܂��B�ȑO
���\����Ă���VOX-VALVETONE�̓~�b�h�����W�������I�ł������A���t���b�g
�őf���ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B
BigBen�͘c�݂�������ɂ�A��d�S����ɏオ���Ă����X�����L��܂��B
���A�ςɌy�����Ȃ炸�A��ʓI�ɂ͂��ꂭ�炢�̂ق����g���₷���̂��������
����B
�啝�ɘc�܂��Ă����Ă��A��i�Ȉ�ۂ�ۂ��Ă��܂��B�֒����ꂽ�M���M������
���܂�L��܂���B���ɏЉ��Bulldog�Ƃ̃T�E���h�o���G�[�V�������l����ƁA
�Ȃ��Ȃ��Ó��ȍ������ȂƎv���܂��B�����A�n���o�b�J�[�Řc�܂�������Ə�
�����������o�Ă��Ă��܂��̂��c�O�ł��B
�S�̂Ƃ��āA�l�����삵�Ă���I�y���[�V����2�Ɣ�r����ƁA���̊�������
�炩�ɈႢ�܂��B�l�����̑���Ƃ��ċ����[���ł��B
�`���[�u��12AU7���g���Ă��܂��B12AX7�ɂ��Ȃ������Ƃ��낪�܂��Ȃɂ�����
�����ŁA���R��m�肽���Ƃ���ł��B���Ȃ݂�12AX7�ł�12AT7�ł��S���R���p�`
�œ��삷��Ǝv���܂��̂ŁA�`���[�u���������ăJ�X�^�}�C�Y����Ƃ�������
���l�����܂��B���オ�y���݂ł��B
��VOX Bulldog Distortion
�`�����l����2�n���p�ӂ��ꂽ�f�B�X�g�[�V�����ł��B
������ȑO��Vox DistortionBooster�Ƃ̔�r�ɂȂ�܂����A�l�������S���ς����
�Ǝv���܂��B
��{�I�Ƀp�L�b�Ƃ����V���������̘c�ݕ���ڎw���Ă���悤�Ɏv���܂��B�ȑO
�̂悤�ȃI�[�o�[�h���C�u����̐i���^�Ƃ��������̂Ƃ͈�����悵�Ă���Ǝv
���܂��B
�c�܂��Ă������Ƃ��Ƀ����W����ɃV�t�g����Ă����X����BigBen�Ɠ��l�ł��B
���ꂪ�c�ݕ��̏�i���ɂȂ����Ă���悤�Ɏv���܂��B�啝�ɘc�܂����Ƃ���
������т₩�ʼnؗ�Ȉ�ۂŁA�\�ꂽ�r�������͂��܂�o�Ă��܂���B
���݂ɖl�����p���Ă���LED���@�����^�C�v��RAT��Sovtek-BigMuff�ƒe����ׂ�
�݂�ƁA���̍l�������S���قȂ��Ă���悤�Ɋ����܂��B
���̕ӂ�́A����Ă��鉹�y��A���T���u���̒��łǂ������邩�Ƃ������ł���
�āA�ǂ��炪�D��Ă���Ƃ������Ƃł͗L��܂���B�v���C���[������]�ނ̂��A
�ł��B
Bulldog�̃R���g���[���͂킩��₷���g���₷���ł��B
�m�C�Y�����Ȃ���r�I�Â��ł���_���D�������Ă܂��B
�`�����l��1�͔�r�I�f���Șc�ݕ��ŁA�`�����l��2��Voice�R���g���[������
�Ă���Ԃ�A�����炩�F�t�����ꂽ�����I�ȃT�E���h����悤�ɂȂ��Ă�
�܂��BVoice�ł̉ϔ͈͍͂L�߂ł����A�������A�T�E���h�́u�F�v�̎��͂���
�܂Ń~�b�h�n�C�ȏ�ł���悤�Ɏv���܂��B
�`���[�u�Ɋւ��Ă�BigBen�ƑS�����l�ł��B�`���[�u�̈Ⴂ�ɂ��c�݂̍��Ȃ�
�����e�X�g�ł�����ʔ����Ǝv���܂��B
Bigben,Bulldog�Ƃ��d�r�g�p����6V�쓮�ŁA�A�_�v�^��9V�̂��̂��g���܂��B��
�����Ă����Ȃ��Ă���̂��͕s���ł��B�d�r�쓮���̎g�p�\���Ԃ���l���āA
�P�O4�{���g�p�����������̂�������܂���B6�{�ς��9V�ɂ���X�y�[�X�͖�����
���̂����B������ɂ��Ă����p���ōl����A�_�v�^�͕K�{���Ǝv���܂��B����
�d�͂��傫���̂ŁA�ǎ��Ȃ��̂�d���e�ʂ��悭�l���Ďg�p���������̂ł��B
�܂��o�C�p�X�X�C�b�`�͑o���Ƃ��g�D���[�o�C�p�X�ł��B
���i
BigBen Overdrive�@ �21,000
Bulldog Distortion � 23,000
�i��������ŕ�)
��LINE6�@Constrictor�@Compressor
�Ȃ��Ȃ��D�ꂽ�R���v���b�T�[�ł��B���܂Ŏg�����y��p�R���v�̒��ł����Ȃ�
��ʂɓ�����̂ł��B���삪���肵�Ă���̂��������_�ł�����܂��B���F�̓A
�^�b�N�ƃ����[�X�̎��萔�ݒ�̍��łR��ޗp�ӂ���Ă��܂��B�������A���ۂ�
�e���Ă݂�Ƃ��̍��͎��萔�����ł͂Ȃ��悤�Ȋ���������̂͋C�̂����ł���
�����BCompact�ASqueze�AMellow�͂��ꂼ��ɓK�ł���A�C�����悭�g��������
���Ƃ��o���܂��B�G�t�F�N�^�[�������甭������m�C�Y�����ɏ��Ȃ��̂̓f�W
�^��������ł��傤���B��ς悢�ł��B����ɓ��M�������̂�GATE�ł��B��{�I
�Ȑݒ肪���܂��̂��A���Ȃ�C�����悭�g�p�ł��܂��B�R���s���[�^���j�^�̐^
��O�Ŏd�����Ă��Ă��悢�����Ƀm�C�Y���������Ă���܂��B����͖{���̃R��
�v�Ƃ������Ƃ𗣂�Ă��g���r���L�邩������܂���B
�����߂�����1��ł��B
��LINE6 Crunchtone Overdrive
����ɂ�3��ނ̉��F���p�ӂ���Ă��܂��B���ꂼ��̉��F�̃��f�����O���ɂ�
���Ă̓}�j���A�������Ă��������B�f�W�^���̘c�݂��͎̂g���l�̍D�݂ɂ����
�傫���]����������܂��B�l�l�͌����ăI�[���}�C�e�B�[�Ƃ͎v���܂��A
�g�p�V�[���ɂ���Ă͑��݉��l������悤�Ɏv���Ă܂��B�����������Ӗ��ł���
�͂悭�o���Ă���Ǝv���܂��B�c�݂��グ�Ă������Ƃ��̖\����Ƃ����܂��Ȃ�
�v���܂����BGATE��OFF��1��2�Ńv���Z�b�g�̑I�������ł��B�R���v�ɍ̗p���ꂽ
�悤�ȘA���ςł��悩�����̂��ȂƎv���܂����A�����������Ȃ�������L���
�ł��傤�BGATE�̃v���Z�b�g�̐ݒ�͖l�̊��ł͓K�Ɏv���܂����B
��LINE6 UberMetal Distortion
��{�I�Ȍ`�̓I�[�o�[�h���C�u�Ɠ��l�ł����A����Ƀ~�b�h�����W�̃R���g���[��
��������Ă��܂��B
�g�����Ƃ��Ă͂����̂Ƃ��낪�̂ɂȂ邩������܂���B�c�ݕ��͑S���u���v��
���̂��Ǝv���܂��B�Ђǂ��c��ł��������蕷�����镔�����L��Ƃ����悤�ȁA
�܂��ɍD�݂ɍ��E����镔���ł��B�D�݂̔@�����킸�A�d���ł͌��\�g�����
�̉���������܂���B
��LINE6 TapTremolo
���[�h��3��ނ���g�������}�V���ł��B�I�v�`�J���ƃo�C�A�X�̍�����������
�`�ŏo�����Ɠ��h���Ă��܂��܂��B
�e�������ɔ�������peek�̃R���g���[���͓�ꂪ�K�v�ł������Ȃ�L���ł��B
�t�b�g�X�C�b�`�͌y�����Ƃ��Ƌ������Ƃ��ŁA���ꂼ��tap�ƃG�t�F�N�g
��on-off�ł��B�������ꂪ�K�v��������܂���B
��LINE6 Space Chorus
�����3���[�h�̃R�[���X�ł��BTri�R�[���X�ƃ��B�u���[�g�͂��Ȃ�D���ł��B
�t�b�g�X�C�b�`�̓g�������Ɠ��l�ł��B
��LINE6 EchoPark Delay
������➑̂ɐ������̋@�\�荞�f�B���C�ł��B��{�I�ɂ���܂ł�LINE6
�̃f�B���C���̂����^�ɂ����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���ɏ������Ƃ͂���܂���B
���܂ł̂��̂��g�������Ƃ��L��A���̈�a���������ł��傤�B
�t�b�g�X�C�b�`�͏�L�Ɠ��l�ł��B
�ȏ�LINE6��6�@��ł����A�������ɑ�ϗ��h�ȏo�����Ǝv���܂��B�_�C�L���X�g
�{�f�B�����ɏd���Ƃ���͕]�����������_��������܂���B�d�r�Ɋւ��ẮA
������Ɩ������Ǝv���܂��B�d���A�_�v�^�͕K�{�ł��B���������d�͂������̂ŁA
�����Ȃ��Ƃ��ɂ́A�d���e�ʂ��悭�l���������悢�Ǝv���܂��B
�A�_�v�^�W���b�N�����{�d�l�ɂȂ��Ă���̂Ŏg���₷���ł��B
�ȏ�ȒP�ł������|�[�g�����Ă��������܂����B
(2004.12.25)
��back to top
�@
����I�u���b�W�����ɂ��Ă̍l�@�i�����Łj
�@�u���b�W�ʒu�̒����ɂ��Ė{�Ғ��ɏ����܂������A�����܂œK�ɐv����
���y���O��ɂ��Ă��邽�߁A���炩�̕s�������y��łǂ����Ă悢���킩
��Ȃ��A�Ƃ������ւ������������������܂��B�����ŁA����́A������I��
�u���b�W�����ɂ��ď����Ă݂܂��B
�@�i�b�g�ʒu���̐v�������ꍇ�A�u�P���ɃI�N�^�[�u�����v����Ɣߌ��I�Ȃ�
�ƂɂȂ�A�Ɩ{�Ғ��ɏ����܂����B�u�I�N�^�[�u�����v�Ƃ������������̂��̂�
������������̂Ȃ̂Łu�u���b�W�����v�ƌ��������Ă����܂��B�J���ƃI�N�^�[�u
������킹��Ƃ����̂��ΓI�ȏ����ɂ���ƁA�͂Ȃ͂��s���������Ȃ邱�Ƃ�
���邩��ł��B�i�b�g�ʒu�����K�łȂ��M�^�[�ł�����������������ƊJ����
�I�N�^�[�u�ゾ���������Ă��āA���̂Q�O�ӏ����炢�͋����Ă���Ƃ�����Ԃ�
�Ȃ�܂��B�i�M�^�[�S�̂ł͂P�Q�ӏ����������Ă��Ă���ȊO�̂P�Q�O�ӏ�����
������������j
�@�����ł�����x�u���b�W�����̖{���̖������悭�l����Ƃ�����I�ȕ��@��
������܂��B����́A�i�b�g�̈ʒu���ǂ��ł����P�t���b�g����ŏI�t���b�g
�܂ł𗘗p���āA�K�ȃu���b�W�ʒu����肾�����Ƃ������̂ł��B���̖���
���Y�݂̕��͐��������������B
�����l�b�N���܂������Ɂ���
�@�܂��l�b�N���ł��邾���܂������ɂ��܂��B���̌��ɂ��Ă̍l�@�͖{�҂��Q
�Ƃ��Ă��������B���ꂮ������������Ȃ��悤�ɁB
�����J�|���g������
�@��P�t���b�g�ɃJ�|�����܂��B����ŊJ���̃s�b�`�����킹�Ă��������B�J�|
�����̂Ƃ���蔼����ł��킹�邱�ƂɂȂ�܂��B�J�|�̂����Ō�������ɂ���
���킹�Â炢��������܂��A��������Ԃ����ł��̂ʼn䖝���Ă��������B
�@�J��������������Ƀn�C�|�W�V�������`�F�b�N���܂��B�������e���Ǝv����
�����Ƃ������t���b�g�ʼn������āA���ꂪ�������s�b�`�ɂȂ�悤�Ƀu���b�W�ʒu
�����܂��B�I�N�^�[�u��ō��킹��A���̏ꍇ�͑�P�R�t���b�g�ɂȂ�܂����A
����ł��ܘ_���܂��܂���B�ǂ��ō��킹�Ă��A��Ƃ̂��₷���������ς����x
�ŁA�ŏI�I�Ȍ��ʂ͓����ɂȂ�͂��ł��B
�@�P�J�|�̂܂܊J���ƃn�C�|�W�V�����̃s�b�`���`�F�b�N����B����̌J��Ԃ��ł��B
�@�S���̌������킹����A�P�J�|�̂܂܂��ׂẴ|�W�V�����̃s�b�`���m�F����
�݂܂��傤�B�l�b�N�̏�Ԃɂ����܂����A�قƂ�ǂ̏ꍇ���Ȃ�ǂ���ԂɂȂ�
�Ă���͂��ł��B����Ŕ[���ł����ԂɂȂ��Ă�����ɐi�݂܂��B
�@�����t���b�g�ɂ���đ啝�Ȃ��������悤�Ȃ猴����Njy���Ă��������B
�����덷�������ł���Ȃ�u���b�W�ʒu���ق�̂킸���������đS�̓I�Ȃ��
���ŏ��ɂȂ�悤�ɂ��Ă��������B
�����J�|���͂����ă`���[�j���O���遖��
�@�J�|���͂����܂��B����Ń`���[�j���O����킯�ł��B������Ɩʓ|�ł����A
��P�t���b�g���T�t���b�g�ȂǔC�ӂ̃|�W�V�����Ō�������������Ԃōs�Ȃ�
�܂��B
�@�����̎d��������Ńs�b�`�̂�����ł邩������܂��A�P���ň��肷
��悤�ɂȂ�܂��B�����̊����͂����܂ŋȂ�e���Ƃ��̗͂ƕ�������{�ɂȂ�
�Ǝv���܂��B
�@�`���[�j���O���ł��܂�����A�܂��S�t���b�g���`�F�b�N���Ă݂Ă��������B
�������ł��傤���H�����K�v�Ȃ�A�u���b�W�ʒu�̔������s���Ă��������B
�@���̒��������܂������ƊJ���̂Ƃ��ȊO�̂��ׂẴt���b�g�Ŗ����ł���͈�
�ɓ���܂��B�܂肷�ׂẲ��̂����J���̂U�ӏ��ȊO�͑S�ėǂ���ԂɂȂ��
���ł��B�{���́u�u���b�W�����v�͂��̂��߂ɂ���̂ł��B
�@����ŁA�J�����������ǂ����̓i�b�g���K�ɐv����Ă��邩�ǂ����ɂ�������
���܂��B�l���{�҂ŏ����Ă���悤�Ȑv�����Ă���ΊJ�����ܘ_�����͂��ł��B
�@�ł́A���̂܂܊J���̃s�b�`���m�F���Ă݂Ă��������B���������ɋ���������
�Ƃ���A���ꂪ�i�b�g�ʒu�s�ǁA�i�b�g�`��s�ǁA�i�b�g���s�ǂɂ��s�b�`
���Ȃ̂ł��B���̍�������Ƃ������Ƃ́A������u�I�N�^�[�u�����v�̕��@��
�`�F�b�N����ƁA�u�I�N�^�[�u�����v�������Ă���Ƃ������ʂ��ł邱�Ƃɂ���
��܂��B
�@������������Ȃ��ł��������B���́u�i�b�g�v�ɂ���킯�ŁA�u�u���b�W�v��
�K�ɒ�������Ă��܂��B�u�u���b�W�����v�͂��łɈׂ��ꂽ�̂ł��B���ׂ�
��Ƃ̓i�b�g�����Ȃ̂ł��B
�@���̂����肪�@
�o�@�P���ȁu�I�N�^�[�u�����v�Ƃ����������͌�����܂ށ@�p
�@�Ɩl���v���䂦��ł�����܂��B
�@�u�I�N�^�[�u�����v�̓`���[�j���O���[�^�[�Ȃǂ���ʓI����Ȃ����A
�I�N�^�[�u�W���Q�l�Ɂu�u���b�W�����v���Ă������Ƃ̖��c���Ǝv���Ă��܂��B
�������ۂ̎g�p�́H����
�@�O���ł̊J���̃s�b�`�덷���L�����Ă��������B���ۂ̎g�p���ɂ͊J��������
�덷�ɍ��킹�ă`���[�j���O����킯�ł��B����ŊJ���ȊO�͑S�Ă������Ƃɂ�
��܂��B
�@���邢�͖ʓ|�łȂ���`���[�j���O���₷���|�W�V�����ʼn������ă`���[�j���O
���Ă��������B����ł��J���ȊO�͑S�Ă������ƂɂȂ�܂��B
�@�J��Ԃ��܂����A���̏�ԂŃi�b�g���K�ł���A�J���̃s�b�`����������
��͂��ł��B
�������ӓ_����
�@���p��S�����Ȃ��Ƃ͎v���Ă܂����A�����Ɍ����Ɩ�肪�Ȃ��킯�ł͂���
�܂���B����ɋC���������́A�l�̍l���̗v�_���\���ɗ������ꂽ���ł��傤
����A������ƍH�v���Ď����Ă݂Ă��������B
�`�`�`�قȂ����A�v���[�`�ł̒����`�`�`
�@��L�̕��@�́A�ŏI�I�ɁA�J���͖������āA���������ʒu�Ńu���b�W��������
�Ă����A�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�܂���B����������ƊȒP�ɍs�����Ƃ͏o���Ȃ�
�̂ł��傤���B
�@������ƌ�����ς��Ă݂�ƁA�u���b�W�����͑S�̂̃s�b�`�X���A���Ȃ킿���[
�|�W�V��������n�C�|�W�V�����ɂ����Ēe���Ă������Ƃ��A����t���b�g��
�Ă������V���[�v���Ă���������Ƃ��W���X�g�Ȃ̂��A�Ƃ����u�X���v����
����̂��Ƃ������Ƃł��B���ꂪ�W���X�g�̂Ƃ��A�u���b�W�ʒu�͓K���ł����
�������Ƃ��o���܂��B
�@�菇�͎��̒ʂ�ł��B
�i�P�j���[�|�W�V�����̂ǂ������������ăs�b�`�����܂��B
�i�Q�j�n�C�|�W�V�����̂ǂ������������ăs�b�`�����܂��B
�i�R�j���[�|�W�V�������n�C�|�W�V�����̂ق����t���b�g���Ă���Ƃ�
�@�@�@�u���b�W�T�h����O�i�l�b�N���j�ɏo���܂��B
�i�S�j���[�|�W�V�������n�C�|�W�V�����̂ق����V���[�v���Ă���Ƃ�
�@�@�@�u���b�W�T�h�������ɉ����܂��B
�i�T�j���[�|�W�V��������n�C�|�W�V�����܂Ńs�b�`���m�F���āu�X���v�����܂��B
�@�@�@����V���[�v������t���b�g�����肵�Ȃ����Ƃ��m�F���Ă��������B
�@�@�@���ꂪ�n�j�ł���u���b�W�����͊����ł��B
�i�U�j�`���[�j���O���ĊJ���Ɖ����̂Ƃ��Ƃ̃s�b�`�W�����܂��B�����Y����
�@�@�@����A���ꂪ�i�b�g�̖��ɂ����̂ł��B
(2004.5.16)
��back to top
�@
�ŋߎ���������
�`�`�`�`�k�h�m�m�̃P�[�u���`�`�`�`
�����I�[�f�B�I���i������Ă���X�R�b�g�����h�̂k�h�m�m�̃C���^�[�R�l�N�^�[
�P�[�u�����R��ށA�M�^�[�p�̃P�[�u���Ƃ��Ď����܂����B�A���o�����X�Q��A
�o�����X�p�P��ł��B
���@�u���b�N �i�A���o�����X�j
������ƍאg�ŏ_�炩���A�����y�ȃP�[�u���ł��B�V�[���h�̖Ԑ��̓V��
�v���ŁA���������I�[�\�h�b�N�X�ȍ\���ł��B�R���̂��̂Ƀm�C�g���b�N�̃v��
�O�����Ď����Ă݂܂����B
�֒����Ȃ��A��r�I�f���Ȉ�ۂł����A����Ƀs�[�N�����銴���ŁA�L���L����
�Ă��܂��B�������A�\��Ă���ƌ����قǂ̂��̂ł͂���܂���B�V���O���s�b
�N�A�b�v�Ŏg�p���Ă݂�ƁA�c�݊��̂�������V���O���R�C���̉���L���ɂ���
�悤�ŁA�Ȃ����M�^�[�̓������悭�����o�����������܂����B���i���������
�ɂ͎g�������ł��B�i�蔄��P�����P�T�O�O�j
�v�d�a�ŃI�[�f�B�I�t�@���̕]�������Ă݂�ƁA���Ȃ�D�ӓI�Ɍ���Ă��܂��B
�Ód�e�ʂ́A�P��������X�P�o���ł����B�i�v���O���ő��肵�āA�P��������
�̐��l�����߂����̂ł��B����덷�ɂ��Ă͂��e�͂��������j
���@�V���o�[�@�i�A���o�����X�j
������Ƒ��߂ł������������G�͏_�炩���ł��B��F�̔핢�ŁA�c�����P�{��
�Q�d�̖Ԑ��V�[���h�Ƃ����\���ł��B�R���̂��̂ɃX�C�b�`�N���t�g�̃v���O��
���Ď����܂����B
��ϑf���ŁA���������L��܂��B�u���b�N�ɗL�����s�[�N�͊����܂���ł����B
������ƒe���ł͂��ƂȂ��������Ă��܂���������܂���B���A���낢��ȃM�^�[
�Ŏ����Ă݂�ƁA���̓��������D�܂������̂Ɏv���Ă��܂����B�d�S�͏������
�Ɋ����܂����y�����邱�Ƃ͖����A�ȑO�����p�d�c�������u���Ƃȁv�ɂ���
���������܂��B���i�͐蔄��P�����T�O�O�O�ł��B
�Ód�e�ʂ́A�P��������W�X�o���ł��B
���@�V���o�[�@�i�o�����X�j
�O�`���@�͏�L�̃A���o�����X�ƂقƂ�Ǔ����ł��B���������G�͏���������
�ł��B��F�̔핢�Őc�����Q�{�ƁA���V�[���h�A�Ԑ��V�[���h�Ƃ����\���ŁA�A
���o�����X�P�[�u���Ƃ͂��Ȃ����Ă��܂��B�≏�̂��f�ނ��قȂ��Ă���悤
�ŁA�������͎��Ă��Ă��A���҂͑S���ʂ̍l�����ō��ꂽ�P�[�u�����ƌ�����
�Ǝv���܂��B�R���̂��̂Ƀm�C�g���b�N�̃v���O�����Ď����܂����B�V�[���h
�̓��[�v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɃP�[�u���̕Б������Ńv���O�ɐڑ����A�z�b�g�E�R�[
���h�E�V�[���h�Ƃ����`�ł��B
�k�h�m�m�̃P�[�u���ɂ͖���Ă��āA�����\����̕��������L��̂�����
��܂��A�ڍׂ͂킩��܂���B�ڑ��͈ꉞ���̕����d���A�V�[���h�̓A
���v���ŃA�[�X�ɗ����Ă��܂��B
���̓V���o�[�̃A���o�����X�P�[�u���Ɏ��Ă��ē������������I�ł��B����ɒ�
��̏[�������D�܂������̂ŁA�͊����D���ł��B�M�^�[�p�Ƃ��čl����ƁA�R��
�ނ̒��ŁA���ꂪ������D����������܂���B���i�͐蔄��P�����T�O�O�O
�ł��B
�Ód�e�ʂ́A����̍\���Ńv���O��������ԂŌv�����āA�P��������P�U�Q�o��
�ł����B
�k�h�m�m�̃P�[�u���́A�S�̓I�ɑ�ύD�܂������̂ł����B�s�v�c�Ȃ��ƂɃC�M
���X�̃P�[�u���̓��[�J�[������Ă��A�ǂ���������ۂ��L��悤�Ɏv���܂����B
�������ɉe���������Ď����悤�ȉ�����Njy���Ă��܂��̂ł��傤���B
�`�`�`�u�n�w�@�s�n�m�d�@�k�`�a�@�r�d�`�`�`
�u�n�w�̃A���v�ɍ̗p���ꂽ�`���[�u���g�����v���A���v�̐V�^�ł��B
�r���g�C���̃A���v���o�āA���Ƀf�X�N�g�b�v�^�C�v�A�����Ă��̃t���A�[�^�C
�v�Ƃ����킯�ł��B
�V�^���ł邽�тɉ��ǂ���������̂ł��傤���E�E�E
���̂Ƃ���A���̃t���A�[�^�C�v��������D���ł��B
��ς킩��₷���A�����I�ȑ��삪�ł��A�������قƂ�ǕK�v�Ƃ��܂���B
�y�_�����Q�{���Ă���͖̂{���ɕ֗��ł��ˁB
���͂��̐��i����啝�ɕω������悤�Ɏv���܂��B�ȑO��������̃V���[�Y�͂�
�Ă��D�������Ă��̂ł����A����ɗǂ��Ȃ����Ǝv���܂��B
�u�ǂ��Ȃ����v�Ƃ������Ƃ̓��e�ł����A�V�~�����[�V�������Ă���A���v�^�C
�v���ɂ悭���Ă���Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�����Ɗ�{�I�Ȏ����A�M�^���X
�g�̈ӎu�Əo���Ƃ̊֘A���ƂĂ��ǂ��Ȃ����悤�Ɏv����̂ł��B�i�e�����Ǝv
���^�b�`�Əo�Ă��鉹�̗��������Ȃ��Ƃ������Ƃł��j
�l�����h���M������^�M�^���X�g�Ƃ̈ӌ������ł��A���̓_�͊m�F�������Ă��܂��B
���i�I�ɂ��[���ł�����̂Ȃ̂ŁA���ꂩ��V�~�����[�V�������̂���肵�悤
�Ǝv���Ă�����ɂ͖��킸�����߂ł�����̂̂ЂƂł��B
(2004.05.05)
��back to top
�@
�ǎ҂̐�����5�@��������
����������uFCON�v�ɂ��Ẵ��|�[�g���܂����̂ŏЉ���Ē����܂��B
������������������������������������������������������������������������
�w Fcon �x�Ƃ́H
���p�@�r��
�˂��A�{���g�p���t�����͈��艻��
���u���́v�Ƃ������t�ɓ���݂̂Ȃ��������������m��܂��A
�@�u�g���X���b�h�������ς�́v�ƍl���č����x���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����@����
�������̂˂��ʁA���ʂ̊E�ʂł̖��C�`�Ԃ����͈��艻�����ɂ�萧�䂵�A
�@�g���N�W���̕ϓ���}�����邱�Ƃɂ��A�����̂ɐ����鎲�͂����艻�����܂��B
���g���N�W���̕ϓ��W�����}�V�����ɑ��ő�P�^�T�B
���ɂݓ����̓}�V�����Ɠ����ȏ�B
�����x�ω��ɂ��g���N�W���̕ϓ������Ȃ��B
�ڂ����͊������ �������쏊�̃T�C�g�ց@
http://www.tohnichi.co.jp/
���̂e�b�n�m���g���X���b�h�̃A�W���X�g�i�b�g�Ɏg���Ă݂܂����̂ŁA
���̊��z���F����ɂ��m�点�������Ǝv���܂��B����̓l�b�g������
�����ȉt�̂ł����A�@����肪���X���ł�����w�ɒ��ڂ���
�h��悤�Ȏg�����͂����߂ł��܂���B�i���[�J�[�ɂ������t����
�ꍇ�͑䏊�p�N�����U�[�Ő���Ăق����Ƃ̂��Ƃł����j
���l�W�R�̓N���[���ȏ�ԂɁ�
�܂��M�^�[�̃l�W�Ɍ������b���ł͂���܂��A�e�b�n�m���g���O��
�l�W�R���ڐG�ʂ͂ł��邾���N���[���ȏ�Ԃɂ���K�v������܂��B
�i�����M�^�[���y�C���g�̃J�X�Ȃǂ��c���Ă��鎖�͒���������܂���ˁj
�l�W�R�����߂Ȃ����x�ɁA�������i�ʼn�����������Ă����܂��B
�܂��A�W���X�g�i�b�g�̐ڐG�ʂɂ͐[���L�Y���t���Ă��鎖�������
�v���܂����A�\�߃��X���E�y�[�p�[�����g���ďC�������Ă����܂��B
���R�ł����S�����c���Ă��Ă͈Ӗ�������܂���A���̏ꍇ��
�s���Z�b�g�Ɋ������E�G�X�ɃA���R�[�������Đ���@���܂����B
�����b�h�ɂ��u�`���[�j���O�v�̊ϓ_����
�l�W�R�Ɉٕ������܂��Ă���ꍇ�A���C�������ŏW�����ău���[�L��
�|��������ԂƂȂ�A���ꂪ���͂̔�����s����ɂ��ăg���X���b�h��
�����������Ă��܂��܂��B�g���X���b�h�ɂ��u�`���[�j���O�v����Ƃ���
�ϓ_������A���̕����̓}�V���w�b�h�ɂ�����܂���������ƐT�d��
�P�A������Ă��悢�͂��ł��B
���u�����Ƃ肵���v���G��
�i�b�g�������|���炸�ɉ�鎖���m���߂Ă���A���悢��e�b�n�m��h��
�܂����A�l�W�R�����łȂ��������C�͂�����ʂɂ��K���h��܂��B
�y�����ߍ���ł݂�Ɓu�����Ƃ肵���v���ߖ�������܂��B����ł��ĕς�
�������y�߂��邱�Ƃ�����܂���B�l�b�N�̏�Ԃ����Ȃ���̖{���߂�
����ƁA�]���̃J�b�N���ƃu���[�L���|����悤�ȁu�������v���G����A
������ŃW�����Ǝ~�߂���u�����Ƃ肵���v�C�C���G�ɕς��܂����B
�����K�Ȓ�����Ɓ�
����Œ������l�߂̒i�K�ɂ���u���ߑ���Ȃ����ɂ߉߂��v�̃W�����}
����J������āA���ɉ��K�Ȓ�����Ƃ��ł��܂����B���̎����ɂ��Ȃ��
���A���̓x�[�X�̒������ɍ����Ȃo�a�̃I�t�Z�b�g�h���C�o�[�̐��
�܂��Ă��܂������Ƃ�����A���N�g���X���b�h�������|�ǂ̃g���E�}�ɉՂ܂�
�Ă��܂������A���̂e�b�n�m�Əo����Đ��ɍ������邱�Ƃ��o�����̂ł��B
�{�g���P�{�łX�O�O�~���x�ł�����A�F��������Ўg���Ă݂ĉ������B
�����߂͑S���̃A�X�g���v���_�N�c�ŁB
http://www.astro-p.co.jp/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
��������傳��̃v���t�B�[���i�����g�̏������݂ł��j
�P�X�U�T�N�@��ʌ�����s�ɐ��܂��
���{�M�^�[����w�@����̏A�E��̓J�M��
���݂͉�Ћ߂̐[�違�T�����y�A�}��
��N��Ƀv���f�r���[��ڎw���Ă���H�炵��
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
������������������������������������������������������������������������
���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������
�肦��ƍK���ł��B
(2004.02.05)
��back to top
�@
Aleatorik�戵������

Aleatorik�@Proto�̃v���[���g����͒��ߐ�܂����B�����̂����傠�肪�Ƃ�
�������܂��B
�ȉ��͎戵�������Ƃ��ď��������̂ł����A�����̎Q�l�ɂ��Ă���������Ǝv��
�f�ڂ����Ă��������܂��B
������������������������������������������������������������������������
Aleatorik�ɂ��Ă̓�O�̎����@�@By�@���c�m
Aleatorik�uOperation�P�v�uOperation�Q�v�uOperation�R�v�uOperation�S�v��
���肵�Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
�c�܂��Ă����Ɉ������܂Ȃ��A�|�[���ƑO�ɏo�Ă��鉹��ڎw���Đv���삵��
�����B
���ہA���̃��[�J�[�̘c�ݕ��Ɣ�r���āA�������x���Ȃ�A��苭�����݊���
�O�ɏo�Ă���悤�Ɋ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�A���v�ɐڑ����Ă̎g�p�͖ܘ_�A���Ƀv���c�[���Y���Ń��C���Ř^��Ƃ��ɂ��A
�傢�ɈЗ͂����Ă��܂��B���Ƀv���~���[�W�V�����̊F�l�����ς��D�]��
���������Ă���܂��B
�ȒP�ł����AAleatorik�ɂ��āA�������̎������L���Ă����܂��B�����̎Q�l
�ɂ��Ă���������K���ł��B
�i�P�j�R���g���[��
| ���u�@ | ���H�����[���@�@�@�@�@ | �G�t�F�N�^�[����̏o�͂̑傫�������܂��B |
| ���s�@ | �g�[���R���g���[�� | ���ɉƒቹ����������A�E�ɉƍ�����
��������܂��B |
| ���c�@ | �h���C�u | �c�ݕ������܂��B�y��̏o�͂̑召��
����Đݒ�ʒu�͕ς��܂��B��ʓI�Ɍ����āA
�h���C�u�͂��������Ȃ��ق�������ł��B
�������\�ꂽ������]�ޏꍇ�͂��̌���ł͂���܂���B |
�͂��߂Ďg���ꍇ�́A�Ƃ肠�����g�[���ƃh���C�u�̃m�u��^��ɂ��āA�u���R��
���炢�ɂ��Ă����ĉ��F�̊������Ă��������B���Ƃ͊�]�̉��ɂȂ�悤�ɁA
�e�m�u���Ă݂Ă��������B
| �uOperation�P�v | �u�[�X�^�[�v���X�ł��B�h���C�u��������ƃ\�t�g�Șc�݂��t������܂��B |
| �uOperation�Q�v | ��r�I�f���Șc�݂��������I�[�o�[�h���C�u�I�Ȃ��̂ł��B������Əa�߂Ȋ��G
�ł��B�R�[�h�e���ł����܂����Ȃ��̂ŁA�g���₷���Ǝv���܂��B |
| �uOperation�R�v | �h���C�u�̐ݒ�ł������̐��i�̘c�݂���悤�ɍl�������̂ł��B
�c�ݕ��͑f���Ȃ��̂���A���G�Ȃ��̂܂ŁA�A���I�ɕω����܂��B
���܂�c�܂Ȃ��ݒ�ɂ��ăv���A���v�I�ɂ��g���܂��B���̎g�����̓x�[�X�v��
�C���[�ɍD�]�ł��B
|
| �uOperation�S�v | ������t�@�Y�I�Ȃ��̂ł��B�\�ꂽ�c�ݕ��ƁA�����̂ނ悤�ȃt���[�Y�̋N��
�������I�ł��B
�M�^�[�̏o�͂̑傫���ɂ����܂����A�h���C�u�͍ŏ�����^�ギ�炢�܂ł̔�
�͂������߂ł��B����ȏ�̐ݒ�͓���p�r�ɑΉ��ł���悤�ɕ�������������
�̂ł��B |
(��)���U���ɂ����悤�ɍl���Ă��܂����A�c��u���グ������Ɣ��U����ꍇ��
�L�邩������܂���B����Ȍ��ʂ��˂炤�Ƃ��ȊO�͔��U���Ȃ��͈͂ł��g���������B
�i�Q�j�A�_�v�^�[�W���b�N
��ʓI�ȂX�u�̂`�b�[�c�b�A�_�v�^�[��ڑ��ł��܂��B�O�����v���X�A�������}
�C�i�X�ł��B
�������A�A�_�v�^�[�ɂ���ē����Ԃ��傫���قȂ�\��������܂��̂ŁA�o
����O�O�U�o���d�r���g�p���邱�Ƃ������߂������܂��B�d�͏���͔��ɏ�
�Ȃ��ł��B�����ŁA�悭����f�B�X�g�[�V������I�[�o�[�h���C�u�̂T���̈ꂮ
�炢�ł��B���ɑ����̃o���c�L���������Ƃ��Ă��A�d�r�͑�ϒ���������Ǝv��
�܂��B
�d�r�̏ꍇ�A�C���v�b�g�W���b�N���d���X�C�b�`�ɂȂ��Ă��܂��B���m�v���O��
�ڑ����邱�ƂŁA�d�����n�m�ɂȂ�܂��B�A�_�v�^�[��ڑ����Ă���Ƃ��͂���
�X�C�b�`���o�C�p�X����܂��̂ŁA��ɓd���n�m�ɂȂ�܂��B
�i�R�j�ڑ�
�h�m�ɃM�^�[��x�[�X�Ȃǂ̊y����Ȃ��܂��B�n�t�s�ɃA���v��A���C������
�c�h�Ȃǂ��Ȃ��܂��B�ڑ�����P�[�u���̃v���O�̉��������āA��ɗǍD��
�ڑ���Ԃ��ۂ����悤�ɂ��Ă��������B���ɉ��炩�̃m�C�Y����������ꍇ�A
�܂����Ƀv���O�̐��|�����Ă݂Ă��������B
�i�S�j�t�b�g�X�C�b�`
��{�I�ɂR�o�c�s���g���āA�g�D���[�o�C�p�X�ɂ��Ă܂��B�R�o�c�s�d�l�ł�
�G�t�F�N�g�n�e�e���ɃG�t�F�N�g���̓��͂��n�o�d�m�ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ�R��
�A�[�X�ɗ����Ă��܂��B�M�����C���̐ړ_���͂Q��H���ł��B
�ꍇ�ɂ���Ăc�o�c�s�Ńg�D���[�o�C�p�X�E�v���X�e�d�s�[�k�d�c��A�c�o�c�s
�œ��̓p���������̗p���Ă��܂��B
�e�d�s�[�k�d�c��H �́A�G�t�F�N�g�n�e�e�̂Ƃ��͂n�t�s�̉�H�ɐڑ�����ď���
���A�n�m�̂Ƃ��͉�H����͂Ȃ���ē_�����܂��B�����̏�ԂƂ����̎��g�p
����Ă���M�����C���Ƃ͓Ɨ����Ă��܂�����A�e�����قƂ�ǂ���܂���B
�g�D���[�o�C�p�X�ŐM�����C���̐ړ_���͂Q��H���ł��B
���̓p�������̂��̂̓G�t�F�N�g�̓��͂���ɐM�����C���ɂԂ牺�����Ă��܂��B
�������A�C���s�[�_���X�����߂ɐݒ肵�Ă��邽�߁A�G�t�F�N�g�n�e�e�����e��
�����Ȃ��Ǝv���܂��B�M�����C���̐ړ_���͂P��H���ł��B����Ӗ��A�L���ȕ�
���������āA�l�l�͎̂Ă������v���Ă܂��B
�i��̑O�̃G�t�F�N�^�[�ɂ͓��̓C���s�[�_���X�����ɒႢ���̂�芷����
�H�ɖ�肪������̂������A�g�D���[�o�C�p�X�ւ̉������K�{�Ǝv����
���̂�����܂��B�j
���ꂼ��g�p�X�C�b�`�̉�����ړ_���̉e���������āA�ǂꂪ�x�X�g�Ƃ͌����
�ł��B�g�����̍D�݂ɂ����܂����A���ۂɎ����Ă�����đI��ł��������ق�
�����悤�Ɏv���Ă��܂��B
�i�T�j�p�[�c�Ɖ�H
�l�������̂���ɓ����p�[�c���H�Ƃ͌���܂���B���̎�����ł������̂�A
����v�f�ŕύX���Ă���ꍇ������܂��B��{�I�ȍl�����Ƃ��āu��_���v��
����Ă���悤�Ȃ��ł��B�ł�����A���ۂɖڂ̑O�ɂ�����̂Ŕ��f����
����������������܂���B������ǂ�ǂW�E���ǂ���Ă����\��������܂��B
Aleatorik�i�u���R����e�F����v�Ƃ����悤�ȈӖ��ł����j�̖��O�ɖƂ��āA
����������������A�Ǝv���܂��B
���܂̂Ƃ���JACK,FOOTSW,��CRYO�������������̂����C���Ŏg�p���Ă��܂��B
�i�ꕔ�̓��ʂȕ��ɂ͂���ȊO�̕����g�p���Ă��܂����B�j
�i�U�j�z��
�z���ނ́A�g�[�����Ⴄ���̂��������g�ݍ��킹�Ďg���Ă��܂��BCRYO������
�{�����m�[�U���G���N�g���b�N1976�̕������C���Ŏg�p���āA����ɓK�ނƎv��
��铺�����W��g�ݍ��킹�Ă��܂��B��ϖʓ|�ł����A�ꕔ�̔z���͐��ނ�
�p�������Ŏg�p���Ă��܂��B�e�z���ނ͍�����肵�ē���ł��邩�ǂ����s����
�����Ƃ肠�����͌���̑g�ݍ��킹�ł�������ł��B
�e�z���E�p�[�c�̑��Ȃǂ͏o�������[�q�ɃK�b�`�������āA�n���_�͂����
�ێ�����Ƃ����ړI�����Ɏg�p���Ă��銴���ł��B
���Ԃ�������A�����������܂�������Ȃ��A���Ƃ���̃p�[�c�̌�������ύ���
�ł����A�������邱�Ƃŗǂ����ʂ���悤�ȋC�����Ă��܂��B
�e�n���_�t�����͐�ĕی�̈Ӗ��Ńy�C���g���Ă��܂��B
�i�V�j�A����
Aleatorik�ł͕ۏ؊��Ԃ͓��ɐ݂��Ă��܂���B�l�l�ʼn�����ۏ���Ƃ���
�̂͑�ϓ���ł��B������[�����ē��肵�Ă��������A�Ƃ����̂���{�ł��B
����������������K���ł��B
�̏�C�����Ɋւ��Ă͂������グ�̊y��X�A�܂���
HUMAN GEAR
Voice 81-3-5450-6178
FAX 81-3-5450-8939
http://www2.gol.com/users/yagi/
�ɃA�N�Z�X���Ă��������B
���Օi�̕s�ǂɂ��Ă͗L���ƂȂ�܂��B
�Ȃ��A�^�G�t�F�N�^�[���[�J�[�ł̌̏�C���̂W�O���ȏ�́A���Ղ����d�r�̎�
��ւ��������ł��B�̏Ⴉ�ȂƋ^������A�d�r�̃`�F�b�N�����Ă݂�̂��ǂ���
���ł��B
���ɑ����̏��FOOTSW�̕s�ǂł��B����͓��݂��Ďg�p���镔���Ȃ̂Œv����
�Ȃ���������܂���B
�����Ƌ@�B�I�ɋ������i���o�ꂵ�Ă���悢�̂ł����E�E�E
���ӌ��₲��]�A���̑������z���̂��A�������������ꍇ��
jterada@air.linkclub.or.jp
�ɂ��肢�������܂��B
�܂��A�M�^�[������s�b�N�A�P�[�u���A�n���_�ȂǂɊւ������
http://www.geocities.co.jp/MusicStar/7571/
�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B����A�N�Z�X���Ă��������B
����Ƃ���낵�����肢�\���グ�܂��B
������������������������������������������������������������������������
(2004.02.01)
��back to top
�@
Aleatorik�ɂ��āi�v���[���g�̕�W�͏I�����Ă��܂��j
�x����Ȃ���A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B���N����낵�����肢�������܂��B
�C�����P�O�O�O�O�O�A�N�Z�X���z���Ă��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�����ŁA�P�O�O�O�O�O�A�N�Z�X���L�O���ăv���[���g���l���܂����B
���
�q���[�}���M���̔�����A�u�G�t�F�N�^�[������Ă݂Ȃ����v�Ƃ����߂��L��܂����B
���͖l�̓o���h������������G�t�F�N�^�[�����삵�Ă��܂����B���ꂱ��R�T�N�O�̂��Ƃł��B
���ꂩ��y�탁�[�J�[�ɓ����ăG�t�F�N�^�[��A���v��M�^�[�̊��J�������Ă��܂����B
�l�h�w�d�q�ɂȂ��Ă�����������g�̌����̂��߂ɂ��낢��Ȃ��̂����삵�Ă��܂����B
������͂��̂�����̂��Ƃ�m���Ă��āA��ʂɎg���Ă��炦����̂�����Ă݂Ȃ���
�Ƃ������Ƃł����B
���삵�Ă݂�ƍK���ɂ��D�]�ŁA���Ƀv���~���[�W�V�����Ɏg���Ă��������Ă���܂��B
���i�͂��Ԃ�������
�q���[�}���M�����甭������܂��B���i���̑��A�ڂ�����
�q���[�}���M���̂g�o��A�G���L���������������������Ǝv���܂��B
���삷��͖̂l��l�ł��̂ŁA����ł��鐔�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B���P�T��O��ł��傤���B
�{�ƂƂ̌��ˍ����ŗ\���͂��܂���B
�u�����h����Aleatorik�Ƃ��܂����B���㉹�y�̗p��Łu���R����e�F����v�Ƃ����悤��
�Ӗ������ł��B�i�ꌹ�̓��e����Łu�T�C�R����U��v�Ƃ������Ƃ炵���ł��j
���삵���͎̂��̂S�@��ł��B
�uOperation�P�v�@�u�[�X�^�[�v���X�ł��B�h���C�u��������ƃ\�t�g�Șc�݂��t������܂��B
�uOperation�Q�v�@��r�I�f���Șc�݂��������I�[�o�[�h���C�u�I�Ȃ��̂ł��B������Əa�߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@���G�ł��B�R�[�h�e���ł����܂����Ȃ��̂ŁA�g���₷���Ǝv���܂��B
�uOperation�R�v�@�h���C�u�̐ݒ�ł������̐��i�̘c�݂���悤�ɍl�������̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�c�ݕ��͑f���Ȃ��̂���A���G�Ȃ��̂܂ŁA�A���I�ɕω����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���܂�c�܂Ȃ��ݒ�ɂ��ăv���A���v�I�ɂ��g���܂��B���̎g�����̓x�[�X�v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�C���[�ɍD�]�ł��B
�uOperation�S�v�@������t�@�Y�I�Ȃ��̂ł��B�\�ꂽ�c�ݕ��ƁA�����̂ނ悤�ȃt���[�Y��
�@�@�@�@�@�@�@�@�N���������I�ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�M�^�[�̏o�͂̑傫���ɂ����܂����A�h���C�u�͍ŏ�����^�ギ�炢�܂ł̔�
�@�@�@�@�@�@�@�@�͂������߂ł��B����ȏ�̐ݒ�͓���p�r�ɑΉ��ł���悤�ɕ�������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�̂ł��B
�ŁA�P�O�O�O�O�O�A�N�Z�X�L�O�Ƃ��āA����i���P��v���[���g�������Ǝv���܂��B
�uOperation�Q�v���܂��� �uOperation�R�v�̃v���g�^�C�v�̂ǂ��炩������]�ŁB
�s�̗\��i�Ƃ͈قȂ��Ă��܂����A���i�̕������͗������Ă�����������̂��Ǝv���܂��B
�������
jterada@air.linkclub.or.jp�Ɂu�v���[���g����v�Ƃ����^�C�g���Ń��[�������������B
���I�łP���l�Ƀv���[���g�������܂��B���I���ꂽ���ɂ̓��[���ł��A�������グ�܂��B
���ߐ�͂Q�O�O�S�N�P���R�P���ł��B
�ł́@��낵�����肢�������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�S�@�������@�@���c�m
(2004.01.16)
��back to top
�@
�ǎ҂̐�����4�@"S.T"����
�������@�n���_�̐����ɂ�鉹���ω��ɂ��ā@������
������������_�ŁA�Ƃ������ƂŃn���_�ɂ��Ă��m�点���܂��B
�ȑO�A�h�q���W�̐����̎d��������Ă�����������������܂����BF�Ќo�R��
���Ȃ�ł����i���Ǘ��ɂ͋�������A�A���Ƃ����������܂����B������
���݂�ƕi�����Ȃ��Ȃ��X�S�C���̂�����܂��B�d�q���n�[�l�X�̐�������
�Ȏd���ł��B
�����Ńn���_�d�����o�����̂ł������̕i�����݂�Ɣ��[���Ⴀ��܂���B�܂�
�قƂ�ǂ̍�Ƃ̓p�[�g�]�ƈ������̂ł������̎蒼���͌��ǎЈ�����邽��
�{�ȏ�̎�ԂƋZ�p���K�v�ɂȂ�܂��B�����������o��������܂����̂ł�����
�߂ĂP�O�N�o���܂�����d�̏C���͓�����Ȃ��Ă��܂��B
�͂̎�ނɂ���ĉ����̕ω�������A�A�Ƃ������Ȃ�ł����ǂ��ł��傤�B
�����̈Ⴂ��܂܂��t���b�N�X�̈Ⴂ������ׂ��ꂪ���������E����Ƃ�����
�͈ꌩ�������̂�������܂���B����ł���ɐ���ނ̃n���_���g���킯�Ă���
�����BF�Ђ̎w��n���_������܂��Ă����͎x���i�Ȃ�ł����h�q������̎w��
���ǂ����͂킩��܂���B�n���_�̎w��͐����]�X�Ƃ������d�オ�����Ƃ���
�M�������Ǝv���܂��B�ɒ[�Ȍ�����������ΐM���ɑ����d�オ�肪�o�����
�̂Ȃ牽�ł��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ł����̐M�����Ƃ����̂��N�Z���m
�ŁA���̎�������̂��̂ł͂���܂���B�P�O�N�Q�O�N�ƒ����ɓn���Ĕ�����
����i���ɂ͐퓬�n�сj�Ŏg���邱�Ƃ������Ă��i���ɖ�肪�N����Ȃ�����
���厖�ł��B�Ƃ����킯�ŁA�ꌩ���̏�ŗǂ������Ă����[���i���Ǘ����K�v
�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�n���_�̎�ނɂ���Ďd�オ��͈���Ă��܂��B����͐����Ⴂ�A�t���b�N�X��
���A�a�̈Ⴂ������܂��B�g���R�e�̌`���b�g���ɂ����܂��B�ł����ꂽ
�l�Ԃł��Ƃ��ꂼ��̎d�オ������z���Ē����������܂��B�������A�������S�A
����ӏ����n���_�Â���Ƃ���邱�Ƃ��Ȃ��l�ɂ͏�Ɉ��̕i���ɂ����Ă���
���Ƃ͓���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���̂��Ƃ��A�n���_�Â���Ƃ�����ł͂�
���l�ɂƂ��Ă��Ղ�����̃n���_�����ݏo���Ă��܂��A�K�R�I�Ɏd�オ��
�̕i�����ǂ��Ȃ�A���̌��ʂƂ��ĉ����̗�Ƃ�Ă���ƍl�����Ȃ��ł���
�����H�g�n���_�����̍��h�����������E����̂ł͂Ȃ��A�����ɂ���ĕ\���d
�オ�����g�n���_�i���̍��h�����������E����A�ƍl����������ɂ͍����I����
�v���̂ł����������ł��傤�H�܂��A�܂܂��t���b�N�X���e���ł��ƕ��H�̌�
���ɂȂ�܂��B���ꂪ��X�̕i���Ɍq����܂��B�����ɕ\��Ȃ��Ƃ��낪�N
�Z���m�ł��B�����n���_��Ƃ�����Ƃ��͊܂܂�Ă���t���b�N�X�������[����
���Ă��܂��܂��B�܂��\�ʂɏo�������������܂��B
����ł̓t���������������Đ���܂����A�A���R�[���ő�p����̂����p��
���傤�B�V���i�[���P�F�P�ō�����Ǝ��Ղ��ł��B���̏ꍇ�ł���ŃA���R�[
���Ŏd�グ�܂��B�n���_���b�L�i�\���n���_�܁j�������ꍇ�����l�ł��B
�����Ń��y�A����Ă���l�̃n���_��Ƃ����Ă���Ƃ��̂��̂͑f�l���x���̐l
�����邭�炢�ł��B������Ɗ�p�ȗF�l����������̂ȂǑS���b���ɂȂ炸����
���Ă鎖���̕s�v�c�Ȃ��̂�����܂��B���́g�������Ă��܂��h�Ƃ����̂�
���ł��B����ŗǂ��Ǝv���Ă܂�����B
�V�[���h�v���O�̏ꍇ�A�V�[���h�Ԃ̏������v���ł��ˁB�܂��A�[�X�̐茇
���Ŕ핢�������t���ČŒ肵�܂����A��������߉߂��Ă���ꍇ�������ł��B��
������Ă���̂ɐM�����R��邱�Ƃ�����܂��B��������n���_�����Ă���ΐ�
��邱�Ƃ͂���܂��炱���͌y���핢���w�R�ޒ��x�ŗǂ��Ǝv���܂��B
���ӋC�Ȃ��ƌ����Ă܂������i�R�OW�̃t�F���_�[�A���v��Vol�Q���x�ʼn����o��
�Ă܂����V�[���h�̈Ⴂ�ɂ�鉹���̈Ⴂ�������ɂ͂킩��܂���B
���i�C��t���Ă��邱�Ƃ͐M�����ł��B��Α��v�I���Ă����m�M�ł��B�t�ɂ�
�����ꂪ��������o���Ă���Β����l�������Ή������ۂ���Ă���̂ł͂Ȃ�
���ƍl���Ă܂��B
�������ł��傤�B�g�T�ւ��h���炢�͂��������܂������H
�܂���������_�ł��悢���̂����邫�������ɂ��Ă���������Ȃ�K���ł��B
������������������������������������������������������������������������
���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������
�肦��ƍK���ł��B
(2003.09.27)
���s���ɂ����s�ʒu�ύX���܂����i�T�C�g�Ǘ��lsaeco�j
��back to top
�@
�������u�f���Ƃo�s�e�d�i�e�t�����j
�i�b�g��u���b�W�T�h���������b�N�^�C�v�ł͂Ȃ��ꍇ�A�ȒP�ȃM�^�[�����̒�
�ł������Ă܂����A�悭���点�邱�Ƃ��K�v�ł��B���������܂�I�C����̂�
�̂��g����Ό��ʓI�Ȃ̂ł����A���ꂽ�蚺���z�����肷��̂ŁA�Ȃ��Ȃ�
�ނ��������ł��B
�����ŁA���������܂芣������ԂŊ�����悭��������T�����ƂɂȂ�܂��B
�������u�f����o�s�e�d�i�f���|���Ђ̏��W�ł̓e�t�����j��V���R�����l
�����܂��B
�ŋ߂ڂ��͓������u�f���Ƃo�s�e�d�̎������J��Ԃ��Ă���̂ŁA������
�������Ǝv���܂��B
�������u�f���̓G���W���I�C�����ɂ��Y������Ă���ꍇ������̂ł���
�m���Ă��邩������܂���B�����u�f���͂ƂĂ��s�v�c�ȋ����ŁA��������
�����Ă��܂��B�疌�̐F�͍����ۂ������F�i�H�j�ł��B
�ȑO�������Ƃ��͂҂�Ɨ��Ȃ������̂ł����A���߂Ďg���Ă݂�ƂȂ��Ȃ��ǂ�
���ʂ��o�Ă܂��B�ȑO�̎����ł͑��̗v�����L�����̂����m��܂���B
�ڂ��������Ă���͈̂�ʂɂ͎�ɓ���ɂ������[�J�[�̎����i�Ȃ̂ł����A��
�y�Ɏ������Ƃ��\�ł��B
�����ԗp�i�X�ɍs���ƃ��C�p�[�̃R�[�i�[�Ɂu�������C�p�[�v�Ƃ������i������
�܂��B����͖{���̓��C�p�[�̂т����h�~���邽�߂Ƀ��C�p�[�S���ɓh����
�����ǂ����镨�ł��B�������A���i�̉�����悭�ǂނƁu�������u�f����
�����疌�����v�ƂȂ��Ă܂��̂ŁA�ړI�ɂ҂�����ł��B�h�邱�Ƃ��\�Ȃ�
�̓S���A�����A�v���X�e�B�b�N�Ȃǂł��B�u�������C�p�[�v�̌`��̓y���^�C�v
�ł����ւ�g���₷���ł��B���������i�������A�ڂ��́��U�W�O�Ŕ����܂����B
����o�s�e�d�́u�e�t�������H�v�̖��O�Ŋ��点�����Ƃ���ɑ����g���Ă���
���̂ŁA���Ȃ��݂��Ǝv���܂��B�ڂ��������Ă���͕̂M�œh���t�̏�̂���
�ŁA�n�܃^�C�v�Ɛ����^�C�v�̕��̂Q��ނł��B��������ʂɂ͑��ʂłȂ����
��ɓ���ɂ��������m��܂���B
��������y�Ɏ����ɂ͂b�q�b�́u�h���C�t�@�X�g���u�v������܂��B�X�v���[�^
�C�v�ő������ł��B���i�́��W�O�O���炢�ŁA�ʔ̓X�ł͂����ƈ����ł��B�M�h
��ƈ���Ĕ�U�ɒ��ӂ��K�v�ł����A��y���ɂ͂������܂���B�疌�̐F�͑�
�������ۂ��������ł��B
�������H�݂����ȕ������]�ԗp�ł���悤�ł����A�܂�����ł��Ă܂���B����
�ł�����܂��������Ǝv���Ă܂��B
���̓�̏����܂ł͌��ʂɎ�̈Ⴂ������悤�Ɏv���܂��B�������u�f
���͂ǂ��炩�Ƃ����ƈ��͂������Ƃ���Ō��ʓI�ŁA�o�s�e�d�͂��܂舳�͂���
���Ȃ��Ƃ���Ō��ʓI�Ȃ悤�ł��B����͂����܂łڂ��̈�ۂł��̂ŁA�F����
�ɍČ������肢�������Ƃ���ł��B
���������܂��ł��Ă���Ƃ��A���̐U���̎d�����ς��悤�Ɋ����܂��B�`���[
�j���O���[�^�[�Ō��Ă݂�ƁA����e���Ă���s�b�`�����肷��܂ł̎��Ԃ��Z
���Ȃ�܂��B�ƂĂ������[�����Ƃ��Ǝv���܂��B�R�[�h��e�����Ƃ��̂܂Ƃ܂�
���C�����悢�ł��B������F����Ɍ����Ă����������������ł��B
�d�����Ďg���̂͂ǂ��ł��傤���H
�ڂ��̎����ł̓O���t�e�b�N�ɓ������u�f����h���āA����ɂo�s�e�d��h
��E�E�Ƃ����̂���ԗǂ��ł��B
������������������������������������������������������������������������
�����܂�h��ۂ̎菇�������Ă����܂��B
�i1�j�i�b�g�̍a��u���b�W�T�h���̌`����₷���Ȃ��Ă��邩�ǂ����`�F�b�N
���܂��B�M�^�[�����̖{�����Q�l�ɂ��Ă��������B���ꂪ�ǂ��Ȃ��Ɖ��������
�����߂݂����ł��B�X�g�����O�K�C�h�₻��ɗނ�����̂̌��������镔����
�`�F�b�N�����������B
�i2�j�h��ꏊ�i�i�b�g�a�A�u���b�W�T�h���A�X�g�����O�K�C�h�Ȃǁj�𐴑|����
���B�^���[�J�[�̎菇�ɂ́u��������Őv�Ə����Ă���܂����A�ڂ��̓A��
�R�[���Ő��|���Ă��܂��B����Ă���ꍇ�A�蒅���ɖ�肪�o��悤�ł��B
�i�R�j�����܂�h��A�悭�������܂��B�X�v���[�̏ꍇ�A�]�v�ȂƂ���ɂ���
���悤�ɃJ�o�[������A�z�����܂Ȃ��悤�Ƀ}�X�N��������ڂɂ͂���Ȃ��悤
�ɖh�상�K�l���|�����肵�āA�\���ɒ��ӂ��Ă��������B
�i�S�j�����ċ���݂Ă��������B�`���[�j���O���X���[�Y�ɂł��A������
�����ɂ����Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B�����O�q���܂����悤�Ƀs�b�`�̗h�炬����
�Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
������������������������������������������������������������������������
�ȏ�ł����A�������u�f���͕ʂ̗p�r�ɂ��g���Ă��܂��B�K�^�̂���l�W��
�ȂǂɈ��̃y�C���g���b�N�̂悤�Ɏg���ėǍD�ł��B�����Ɓu�����v�Ȃ̂ŋC
���I�ɗǂ��ł��B
�܂��������u�f���E�o�s�e�d�i�e�t�����j�Ƃ��A�ق��̓��������̏����ɂ�
�g���Ă݂Ă��܂��B�y�O�V���t�g��A�[�����Ȃǂł��B�C�̂��������m��܂���
�������ł��B�g�������͈��͂��傫�������邩�ǂ����A���ꂼ��́u�F�v������
��邩�ǂ����ɂ���Ă��߂Ă��܂��B
�H�v���Ă݂Ă��������B
������������������������������������������������������������������������
(2003.09.25)
��back to top
�@
�����M�^�[�p�V�[���h�P�[�u���������Ă݂�
�u�����v�Ȉ�{�����~����P�[�u�����A����ނ������Ă݂�@��^�����܂���
�̂ŁA���̈�ۂ����������܂��B�������ɂ���āA�Ȃ��q�ϓI�Ȃ��̂�
�͂Ȃ��A�l�̓ƒf�ƕΌ��ɂ����̂ł��B���̓_�����܂݂������������B
�e�X�g�̓t�F���_�[�A�M�u�\���A�N���C�}�[�A�G�s�t�H���Ȃǂ̃M�^�[�ƃ}�[
�V�����A���v�ōs���܂����B�g�`�A���g�����z�Ȃǂ��ώ@���������̂̓��C����
�v���c�[���Y�d�s�b���g���܂����B�P�[�u���̒����͂��������R�������S�ŁA��
��ȊO�̂��̂�����܂��B�e�X�g�ɂ������Ă͂ł��邾������ς������Ȃ�����
�ɂ��̑f���i�f�ނ�\���≿�i�Ȃǁj��m��Ȃ��悤�ɐS�����܂����B�K���ɔ�
�������ċC���������Ƃ��ɒe���Ă݂Č�ň�ۂ�����Ƃ����`�����܂�
���B
��r�����P�[�u���͍����P�[�u�����݂̑��ɃW���[�W�k�f���A�����X�^�[���b�N�A
�I�[�f�B�I�e�N�j�J�o�b�n�b�b�A�t�F���_�[�A�J�i���f�r�U�A���ȂǁA�茳��
���������̊e��ł��B
���������̂�
�ERequisite Audio
�ESynergistic Research
�EMadrigal
�E�v�d
�ETwoRock
�EVan Den Hul
�EAnalysis Plus
�E�p�d�c
�ECardas
�ł��B
�K���������ׂĂ��ŏ�����M�^�[�p�Ƃ����킯�ł͂���܂���B
������C���^�[�R�l�N�^�[�P�[�u���ɃM�^�[�p�̃v���O�����������̂���
�܂�Ă��܂��B
�i�P�j Requisite Audio�@�h�s�g�d�@�m�d�v�@�b�`�a�k�d�h
�����������P�[�u���ł��B�������ɂ͎�舵���ɂ���Ȃɋ�J���܂���ł����B
���̊����́u�N�����[�v�Ƃ������t�����������܂��B�������͍D��������
�܂����A����́u���v�݂����Ȃ��̂͂��܂芴���܂���ł����B����₩������
�߂�ɂ͗ǂ���������܂���B�A�����J�ł̉��i�͂P�Q�����Ł@���R�T�O�ƂȂ�
�Ă��܂�����A���S�Q�A�O�O�O���炢�ł��傤���B
�i�Q�j Synergistic Research
���̃��[�J�[����͉���ނ��P�[�u�����łĂ��܂����A�e�X�g�����̂��ǂ̃^�C
�v�̂��̂Ȃ̂������Ă��܂���B
�����W�����ɍL�������܂��B�n�C�t�@�C�ł���Ȃ��炵�����肵������͍D��
�ۂł��B���ڂ���P�[�u���̂ЂƂł��B
�e�X�g�����̂����ꂾ�����T���ƒ��������̂ŁA���̃P�[�u���ɑ��Ă������
�n���f�B������܂����B�o����R���ł�����x�e�X�g���Ă݂����ł��B
�G���Œ��ׂ܂��ƁA�قƂ�ǂ̃P�[�u�������\���l�ł��B�ō����i�ɂ͐��\���~
������̂�����܂��B�����Ђ��܂��ˁB
�i�R�jMadrigal
�L���ȃ}�[�N���r���\���̃O���[�v�̐��i�ŁA�^�Ԃ͕s���ł��B
�e���Ă݂�ƑS���ʎ����̉��ŁA�Ȃ�ƕ\�����ėǂ����킩��܂���B�����`�`
���ǂ��ł��B���A���܂�ɑ��̃P�[�u���ƈႢ�����āA�Ȃ�Ƃ����f��������
�Ă��܂��B�P�[�u�������Z�������i�P�A�R�����炢�j�������L�邩������܂���B
�킩��ɂ����������ł����A�֊s�̏o�����u�����I�[�f�B�I�v���ۂ��ł��B�Y��
�ŗ͂�����܂��B�D��ۂȂ�ł����A���i�������~���炢����悤�Ȃ̂ł��܂�
�C�y�ɔ����Ȃ���������܂���B�C��ꂪ���Đ��m�ȉ��i�ׂ�C���N���܂�
��ł����B�\����Ȃ��ł��B
�i�S�j�v�d
�v�d�̃I�[���h�P�[�u���ō�������̂ł��B�ڍׂ͕s���ł��B
����̕\��̏o�����ƂĂ��悢�ł��B�����W�͋��߂Ȃ̂�������܂���B
���i������Ă��邩�ǂ����m��܂���̂ŁA�܂��Q�l�o�i�Ƃ��������ł��B
���i���s���ł��B
�i�T�jTwoRock�@�h�b�q�x�r�s�`�k�@�b�k�d�`�q�h
�N�����[���蕨�ɂ��Ă���P�[�u���ł����A�g���Ă݂āA��������ނ���
����̏o���������I�ł���悤�Ɋ����܂����B
�������������I�ł�������Ƃ悩������ł����ǁA�D�����I�Ȋ����ł��B�o��
���X�͗ǂ��悤�Ɏv���̂ł����A���蕨�̃n�C�̊������l�ɂ͂҂����Ɨ��Ȃ���
��������܂���B �g�����߂D���ɂȂ�̂�������܂��E�E�E
���i�͂P�Q�����Ł��P�U�X�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���Q�O�A�O�O�O���炢���Ǝv��
�܂��B
�i�U�jVan Den Hul �h�h�m�s�d�f�q�`�s�h�n�m�@�g�x�a�q�h�c�h
�I�����_�̃��[�J�[�ł��B����͌��\�D���ł��B�o�����X���ǂ��A�j���A���X��
�o�������Q�ŁA���ʊ����オ���ĕ������܂��B�����̎����^���ĈȑO����̃��t�@
�����X�P�[�u���⑼�̃P�[�u���Ƃ̔�r�����x���s���܂������A���̂��тɂ��Ȃ�
�Ă��܂��܂����B�Ȃ�ƌ������A�����w�ɂ��Ă��銴�������܂��B���炭
Van Den Hul �Œe���Ă���ق��̃P�[�u���ɂ���Ƃ�����ƌ˘f���܂��B
���i�͂R���Ł��R�U�A�O�O�O���炢�B
�i�V�jAnalysis Plus �h�o�q�n�@�n�u�`�k�h
����₩�ŋC�������ǂ��ł��B�Ȃ��Ȃ��ǂ��Ƃ͎v����ł����A������Ȃ�����
���L��܂��B���ʊ��͗L�邵�j���A���X���o��ق��Ȃ̂ʼn���������Ȃ��̌���
�Ȃ̂��悭�킩��܂���B���悩�璆��悪���܂�S��Ȃ��Ă��Ƃ������肵
�Ă���̂���������������̂�������܂���B���̉��ɂȂ�Ă��܂��悢�̂�
�Ȃ��B
���i�͂P�O�����Ł��Q�X�X�ƂȂ��Ă��܂��̂Ł��R�U�A�O�O�O���炢�ł��ˁB
�i�W�j�p�d�c�@�h�p�m�d�d�w�@�Q�h
�C�M���X�̂p�d�c�͂��Ȃ�D���ȃ��[�J�[�ł��B��������ۛ��������Ă��邩��
����܂���B���邭�ĂȂ����\������čD���Ȃ�ł��B�p�d�c�̃X�s�[�J�[
�P�[�u���ł��������ł����A�Ɠ��̍���̐ꂪ�����āA�D��ۂł��B�����
���̔S��݂����Ȃ��̂������Ƃ���ō��Ȃ�ł����ǂ˂��B��ɂ���������
���͏������܂����A�ł�����ς�D���Ȃ�ł��B��̂������ȁH
���i�͂R���Ł��Q�O�A�O�O�O���炢�B
�i�X�jCardas
����͎d���ŖK�ꂽ�O�����h�}���}�X�^�����O������肵�����̂ŁA�o�[�j�[�O
�����h�}������̖��O�������Ă���ƂĂ��ׂ��P�[�u���ł��B�����i�͈�ʂł�
����ł���Ǝv���܂��B���i�͂������P�������聏�S�A�T�O�O���炢�i�H�j����
���悤�ɋL�����Ă܂��B
�M�^�[�p�ł͂Ȃ����̂Ȃ̂ŁA�n���h�����O�m�C�Y����������܂��B
���͍D���ł��B�p�d�c�Ɠ����悤�ɂ�����Ɩ���߂Ȃ�ł����A�D�݂ɍ����܂��B
���ɒ��悩��n�C�G���h�ɂ����Ă̑f�������C�ɓ����Ă܂��B
�l�͂b�`�q�c�`�r�t�@���Ȃ̂ŁA�ۛ������Ԃ�ɓ����Ă܂����B
����ȊO�ɂb�`�q�c�`�r����̓M�^�[�p�̃P�[�u�����łĂ���悤�Ȃ̂ŁA����
�����Ă݂����Ǝv���Ă܂��B������͎G���ɂ��ƂR���Ł��P�Q�O���炢�ł��B
�����Ƃ���Ȋ����ł��B�����̃P�[�u���ɂ͕����������������̂�����܂��B
�f�ނ̕�������A�\���̕������ł��B�P�[�u���ɉ��炩�̈���܂��̂ŁA��
�������m�F���Ďg�p����K�v������܂��B�������A�K���������[�J�[�w��̕���
�������ɂ����Ă���Ƃ͌���܂���B���Ό����������Ă݂đ��͂���܂���B
�������ɈႢ���������������Ă��������B���܂�e���͖����A�Ǝv��ꂽ��
�͋C�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ���������܂��B
�u�����P�[�u���v�́A���̂ɂ���ẮA�����ɂ��n�C�E�t�B�f���e�B������悤
�Ɋ����邱�Ƃ�����܂��B���̕ӂ́A�{���ɍD�݂̖��ŁA�ǂꂪ�ǂ��ƌ�����
�Ƃ��o���܂���B�����܂Łu�l�͂��ꂪ�D�����v�Ƃ������E�ł��B���i��������
�ʼn���ނ������Ď������Ƃ͂��Ȃ荢��ł��傤���A�����̋@��ɐ����Ă�
���������B
�P�[�u���̉����͎��ۂɁu�����Œe���āv���f����̂��x�X�g�ł��B���̃e
�X�g�͂����܂Łu�����Œe���āv�s��Ȃ���Ȃ炸�A���̐l���e���Ă鉹��
���Ă��A���܂蔻�f��ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv���Ă܂��B
����������ƋC�ɂȂ�ŋ߂̃P�[�u���iPlanet Waves�j����
�o�k�`�m�d�s�@�v�`�u�d�r�Ƃ������[�J�[������܂��B�M�^���X�g�ɂ͂��Ȃ���
�̃_�_���I�̃O���[�v�ł��B
�����̃P�[�u�����C�O�ŕ]�����ǂ��炵���̂ł��B�\�ł̓N���v�g����j�[�E
�N�����B�b�c���g�p���Ă���Ƃ������Ƃł��B
�������肵�Ď����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�y��X�̓X���ɂ��܂肨���ĂȂ��ĐV
��������X�̐{�c����ɂ��肢���Ă���ƍw�����邱�Ƃ��o���܂����B
�f�V���[�Y
�c�����Q�{�ŃR�[���h�ƃV�[���h���Ă��āA�����P�[�u���ɂ悭������\
���ł��B�V�[���h�͕Б��̃v���O�̂Ƃ���Őڑ�����Ă���A���������ăP�[�u
���ɂ͕�����������܂��B���[�J�[�w��ł́A�v���O�ɏ������uSHIELDED END�v
�Ə����Ă���ق����A�A���v���ɂȂ����ƂɂȂ��Ă܂��B
���͗��������Ă��ăn�b�^���������A�Ȃ��Ȃ����������ł��B�R�[�h�̍������
���Y��ŁA�o�����X�d���̉���肩�ȁH�Ǝv���܂����B�ς��ƒe���ăO�b�Ɨ���
���Ă������Ԓe���Ă��邤���ɂ���D���ɂȂ��Ă���^�C�v�̉����������
����B
�v���O���Ȃǂɗl�X�ȍH�v�������Ă���ł��̉��i�͋����ł��B
�f�[�P�O�@�R���@���R�A�P�O�O�B
�b�f�V���[�Y
�c������{�ŁA�]������̃M�^�[�V�[���h�̍\���ł��B�ƂĂ��_�炩���Ď���
�����y�ł����A�_�炩���P�[�u���͓��ȉ�������ꍇ�������̂ł�����ƐS�z
�ł����B
�����Ă݂�Ƃf�V���[�Y�Ƃ͈���Ă�����Ɩ\��C���̒����悪�����I�ł��B��
��̃X���C�h��v�����O�I�t�E�n���}�����O�I�����ڗ��������ł��B�\��C����
�����͌����ł͂���܂��A�g�p�M�^�[�ɂ���Ắu�L�����L�����v�����Ȃ�
�L�肷���邩������܂���B�D���������傫���킩�ꂻ���ł��B���ʊ��͂����
�ǖ�����ł����A�^�b�`�ɂ���ăN���[���g�[�����N�����`�C���ɂȂ�₷����
���B�ꍇ�ɂ���Ă͈Ӑ}���Ȃ��c�݂��ۂ��������邩������܂���B�b�f�V���[
�Y��e������őO�q�̂f�V���[�Y��e���ƂƂĂ����ƂȂ��������܂��B
�b�f�[�P�O�@�R���@���Q�A�O�O�O�B
�`�f�V���[�Y
�c������{�̃^�C�v�ŁA�v���O�Ƀ~���[�g�X�C�b�`�����Ă��܂��B����������
���Ƃ����V�v�̃P�[�u���f�ނɊ��҂������܂����B�n���_���X�̃v���O����
�p�������߂ɁA����ɂ��킹�ăP�[�u�����̂��V�v���ꂽ�悤�ł��B�����̔�
�\�͂���܂��A�Ód�e�ʂ����ɏ��Ȃ��炵���A�����ÁX�ł��B�n���_���X
�Ő��č�������Ńl�W����߂�n�j�i�W���[�W�k�f���Ɠ��������H�j�Ƃ���
�̂������[���ł��B
�ł����A�����_�œ��{�ł͂܂���������Ă��܂���B���������ē���ł��Ă���
����B�c�O�ł����A����o�����悱�̕ɒlj����邱�Ƃɂ��܂��B
���i�͂`�f�[�P�O�@�R���Ł��R�A�R�O�O�炵���ł��B
�i�P�[�u���̃L���p�V�^���X�j
�Q�l�����Ƃ��Ċe�P�[�u���̐Ód�e�ʂ��f�ڂ��Ă����܂��B�P�[�u���������Ȃ�
���Ƃ����̐Ód�e�ʂ������Ă��܂��B�e�ʂ������ƁA�v����Ƀg�[�������ڂ���
�̂Ɠ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B�o����Ώ��Ȃ��ɂ��������Ƃ͂���܂���B��
�����A�P�[�u���̉��͂��ꂾ���Ō��܂�킯�ł͂���܂���̂ŁA�{���ɎQ�l��
�x�Ƃ��������ł��傤���B
�Ód�e�ʂ̓v���O��������Ԃł��ꂼ��̗e�ʂ𑪒肵�āA�v�Z�łP��������
�̗e�ʂ�����o�������̂ł��B����덷�ɂ��Ă͂��e�͂��������B
Requisite Audio�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@94pF/m
Synergistic Research�@�@�@�@�@�@�@ 71pF/m
Madrigal�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@140pF/m
�v�d�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@244pF/m
TwoRock�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 212pF/m
Van Den Hul�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@151pF/m
Analysis Plus�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@200pF/m
�p�d�c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@130pF/m
Cardas�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@130pF/m
Planet Waves G �@�@�@�@�@�@�@�@�@ 105pF/m
Planet Waves CG�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@88pF/m
Planet Waves AG�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@???
�ȑO�e�X�g��������
�W���[�W�k�f���@�@�@���@�@�@ �@�@�@73pF/m
�W���[�W�k�f���@�@�@�ׁ@���@�@�@�@ 76pF/m
�W���[�W�k�f���@�m�[�}���ԁ@�@�@�@ 77pF/m
�W���[�W�k�f���Ԃ� ���h�������́@78pF/m
���[�J�[�s���@����i�@�@�@�@�@�@�@ 88pF/m
�I�[�f�B�I�e�N�j�J�o�b�n�b�b�@�@�@119pF/m
�t�F���_�[����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@119pF/m
�r�o�d�b�s�q�`�e�k�d�w�@�@�@�@�@�@125pF/m
�����X�^�[�q�n�b�j�@�@�@�@�@�@�@�@129pF/m
�J�i���f�r�U �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@150pF/m
�t�F���_�[ Whirlwind�@�@�@�@�@�@�@171pF/m
���Y�^�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@222pF/m
(2003.09.20)
��back to top
�@
�Ɏ��I�n���K���[����
�������N�A�ĂɂȂ�ƃn���K���[��K�₵�Ă��܂��B
��ړI�̓n���K���[�̗F�l�B����Â���t�F�X�e�B�o�������邱�Ƃł����A�n��
�K���[�ւ̒��s�ւ��������߁A���łɌo�R�n���ӂ����낤�낷�邱�ƂɂȂ�܂��B
�x���M�[�o�R��������A�I�����_�o�R��������A�����h���o�R�������肻�̎���
����ėl�X�ł����A���N�̓p���o�R�œ���܂����B
�o�R�n�t�߂Ńt�F�X�e�B�o����R���T�[�g���ɍs���̂��ʗ�ł������A���N
�̓t�����X�ł͂��܂莞�Ԃ��Ƃ炸�A����Ƀ��[�}�j�A�܂ő���L�����Ƃ�
���܂����B
���s����R�T�Ԃ̗��ł����B
�����J���[�J�E�t�F�X�e�B�o������
�F�l�̃o���h�́u�J���[�J�v�Ƃ������O�ł��B�n���K���[�̃g�b�v�o���h�̂Ђ�
�ŁA�l���P�O�O�O���l���炢�̍��łP�O�O�����q�b�g�����Ă���Ƃ����A
���l�C�t�H�[�N�E�|�b�v�o���h�ł��B
���̔ނ炪��Â���t�F�X�e�B�o���͍��N�łQ�S��ڂŁA�n���K���[��R�̓s�s
�~�V���R���c�̌Ï�Ղ����Ƃ��čs���܂����B����͖��N���������R�`�S��
�ŁA�o���o���h�̓��[���b�p�e�n����R�O���炢���Q�����܂��B�o��������
�u���[�c�Ƃ��Ė����H�������Ă��邱�Ɓv�Ƃ������Ƃ炵���ł����A�ނ�̍l��
�閯���E�����͂ƂĂ����L���A���炩�ȏ��Ɖ��y�ȊO�͂Ȃ�ł�����̏�Ԃł��B
�����ǂ̕���ざ��
���̃x�������̕Ǖ����A�n���K���[�̉��y�������ς��܂����B�]���͉��y��
���̂ɂ́u�Ƌ��v���K�v�ŁA�̐��ɂƂ��ĔF�ߓ���y�ɂ́u�Ƌ��v���^����
��Ȃ������̂ł��B���ɃA�o���M�����h�n�͔F�߂��悤�������A�n��������]
�V�Ȃ�����Ă��܂����B�������ꂽ��A���y�����̂��߂ɖS��������Ƃ�������
���L��܂����B
���ꂪ���̕ǂ̕����A��C�ɒn��ɏo�Ă����̂ł��B�܂��ɂȂ�ł�����̏�
�ԂŁA���ׂẲ��y�������ɕ���ň�ĂɃX�^�[�g��������̂��Ƃ��Ɍ���
�܂����B�ܘ_�e���y�X�^�C���̗Z����e�N�m���W�[�̗Z�����M����`�ŁA����
�������������R�ɍs���Ă����܂����B
�u�嗤�̉��y�͖ʔ����I�v�h�C�c�����_�Ɋ������Ă��钆��C�T�g��������̂�
��ł�����̉��y��M������Ă��ꂽ���Ƃ��L��܂��B�ǂ��Ӗ��ō��ׂ̖�
�������ő���ɗL�����Ǝv���܂��B
�������ݏؖ�����
�僈�[���b�p���`������Ă����Ȃ��ŁA����̃A�C�f���e�B�e�B�[�Ƃ��Ė�����
�������Ă����̂͂ނ��듖�R�̂��Ƃ�������܂���B�e�n�ł̖������y�̗�����
���̂悤�Ȕw�i�������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����ւ̈ӎ����r���ł͂Ȃ��A��
�݂��ɂ��݂��̑��݂�F�߂����Ƃ��������ւ̑��ݏؖ��ł���悤�ȋC�����܂��B
�����͂����ł����ė~�����Ǝv���܂��B���̂�����͂���n�̌��ł�����A�댯
�Ȕr�O�I������`�̑䓪�̒����͂����ă[���Ƃ͂����܂���B���Ӑ[���������
�����K�v���L��Ǝv���Ă��܂��B
�����n���K���[�̐�������
�n���K���[�̐����͋����قǖL���ł��B�s���X�[�p�[�ɂ͖��ʕ��A���ނ�
�ǂ̐H���i�A�ߗށA�I�[�f�B�I�@��A�J�����Ȃǂ����ӂ�����̏�Ԃł��B
��^�X�[�p�[�͓��{�ł����������炢�̋K�͂ŁA�S�����|����܂��B���i������
���Y�i�Ɋւ��Ă͂ƂĂ������ł��B�r�[���̓��X�g�����ň���ł��P�O�O�~����
���i�ό��q����̓X�ł͂Q�O�O�~�ȏ�ł����j�ŁA�������݂����Ă��܂���
���B
�R���T�[�g��C�x���g�������J�Â���A���ꗿ�͊i���ł��B
�E�C�[������u�^�y�X�g�܂Ŗ�Q�O�O�����A�����I�Ȗʂł͂��Ȃ�e�����傫��
�悤�ł��B���̐̂̓n���K���[�E�I�[�X�g���A�鍑�Ƃ��ĂЂƂ̍��ł����B
���s�҂ɂ͂��̂悤�ɂ������₷���Ƃ���ł����A��ʂ̃T�����[�}���̎�����
��������S�`�T���~�炵���̂ŁA���n�̐l�͂���قNJy�ł͂Ȃ��̂�������܂�
��B
���������Ƃ������Ɓ���
���łɃ��[�}�j�A�̃g�����V���o�j�A�܂ő���L���܂����B
�g�����V���o�j�A�͈ȑO�̓n���K���[�̈ꕔ�ł����B���������āA�����ɏZ��
�l�X�̓}�W���[���i�n���K���[�j�l�������A�����ʂł͂قƂ�ǃn���K���[��
�����Ă��ǂ��������L��܂��B���y�͐̂̃n���K���[���y�������|�{���ꂽ�悤
�Ȍ`�Ŏc���Ă��邵�A�n���K���[������Ȃ蕁�ʂɒʂ���悤�ł��B�����悤��
���Ƃ̓����h�o�n���i�����h�o���a���ł͂Ȃ����[�}�j�A�̈ꕔ�j�ɂ��Ă���
����悤�ł��B
�g�����V���o�j�A�̒n��������ƁA�����ꏊ�ɂR�̖��O�������Ă��܂��B
�n���K���[��A���[�}�j�A��A�����ăh�C�c��ł��B�������}���V�����@�[
�V�����w�C�i�n���K���[��j�̓g�D���O�E�����V���i���[�}�j�A��j�ł���A�m
�C�}���N�g�i�h�C�c��j�ł��B
�}�W���[���l�Ƌ������Ă����U�N�Z���l�Ƃ̊W������킯�ł��ˁB
�����悤�Ȃ��Ƃ͂��낢��ȏꏊ�Ō��邱�Ƃ��o���܂��B
�����̒n������Ă����Ɣނ�̋A���ӎ��͂����č��ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A
�����ƈႤ�Ƃ���ɗ��r�_���L��̂ł͂Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��܂��B�t����
�X�E�X�y�C���̃o�X�N�n���̐l�X���o�X�N���b���A���̊��ł͂Ȃ��o�X�N�̊�
�����X�ƌf���A�܂��t�����X�E�u���^�[�j���n���̐l�X���u���g�����b���A
�u���^�[�j���̊����f����̂����Ă������v���܂��B
���͂��������l�X���R���I�o�ϓI�ȗ��R�Ŝ��ӓI�Ɉ��������������Ĉ�̂Ȃ��
�̂��낤�Ǝv�����Ƃ����ł��B
���ӂ̃X���u�̍��X�̂��ƂׂĂ����Ǝ���͂܂��������G�ŁA�ȒP�ɂ��̂�
�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���[�}�j�A�̕����́A�n���K���[���X�Ɉ����A�����܂��B��ʂ̎����̓n���K
���[���X�ɏ��Ȃ��A�R���~�O��炵���ł��B
�������t�̂��Ɓ���
�e���l�����藐��Ă���t�F�X�e�B�o�����ŃR�~�j���P�[�V���������܂��Ƃ�
���Ǝv���Ɩl�̕Ќ��p��ł͂ǂ����悤���L��܂���B�܂������n���Ă݂āA
���܂��R�~�j���[�P�[�V�����o���Ă���l�͎�����ȊO�ɂR�J���ꂮ�炢�͗���
����悤�ł��B�I�����_��E�h�C�c��E�p��E�t�����X��E�E�E�Ȃǂ���O��
�炢�ł��B���݂��ɂǂ�ǂ�������Ă����āA�ł��悭�ʂ�����̂ɗ�����
���Ƃ������������ł��B
�n���K���[�̗F�l�B�����Ă����J�����b���܂����A�����̉�������t�����X��E
�n���K���[��E�p��E������i���{��j��b���܂��̂ŃR�~�j���P�[�V��������
�܂������悤�ł��B
���N�̗��̏I���̓c�[���E�h�E�t�����X�̍ŏI�����p���Ō���Ƃ������̂ł�
�����A���]�ԃ`�[���̈ꗬ�I�����͂�S�`�T�J����𗝉�����ƕ��������Ƃ�
�L��܂��B���ꂮ�炢�킩��Ȃ��ƍ��ۓI�Ȏ����ł͊e���`�[���̓����𗝉���
���Ȃ��Ƃ������Ƃ炵���ł��B�A�����J�l�����X���C���^�r���[�ł̓t�����X��
�œ����Ă��܂����ˁB
�����g���C�b�c�A����
�t�F�X�e�B�o���ɎQ�����Ă����Ȃ��Ƀx�����[�V�i�����V�A�j�̃g���C�b�c�A��
�����R�l�Ґ��̃o���h�����܂��B�ߋ��ɂ��Q�����Ă����̂ł����A���N�����C��
�p�������Ă��܂����B�t�F�X�e�B�o���̂��ƁA�u�^�y�X�g�ł̒P�ƃR���T�[�g��
�s���A�Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��B�o�`�m���R�[�h�����i���łĂ��܂��B�@�
�L��Ε����Ă݂Ă��������B�W���P�b�g�ʐ^�ł̓n�[�h�Ȉ�ۂ��܂����A��
�ۂ̉��y�͑@�ׂȖʂ��[���Ɏ������킹�Ă��āA��ې[���ł��B
�g���C�b�c�A�̒��S�����o�[�̓x�����[�V�ɏZ��ł���킯�ł����A�}�l�[
�W���[��c�A�[�X�^�b�t�̓I�����_�̐l�ł��B�d���̂��тɂ��������Ċ�������
�̂Œ�������ςȂ悤�ł��B�i�}�l�[�W���[���̓C���v���r�[�[�V�����ƕ\����
�Ă��܂����j
�}�l�[�W���[���͐��N�O�ɉ�������ɂ͕��������������[�S�ɏZ��łm�f�n�̊�
�������Ă��܂����B���a�̂��߂ɁA�����̑��ݗ����̂��߂ɁA��������������
�Ƙb���Ă��ꂽ�L�����L��܂��B
�ȒP�ł������N�̗��̕ł����B�v���Ⴂ���L�邩������܂��A�ǂ���
���e�͂��������B
(2003.08.06)
��back to top
�@
�I�[���B���@���X�|�[�����`���[�j���O����
�肪���Ă���^�~���[�W�V�����̃I�[���B�����X�|�[�����`���[�j���O���܂����B
�{�l�̊�]�͂����������߂̉��ɂȂ�悢�Ƃ������̂ł����B
�����ƃ`�F�b�N���܂��ƌ������s�K�ŁA�����z���ɉ��ǂ̗]�n�����銴��
�ł����B
���l�b�N�͎�̏��]��
�����Ƃ̏�Ԃ͏��]���ł����B
�g���X���b�h�ł܂������ɂ��Ă݂܂������A�l�b�N��t���b�g���������������
���܂�D���ł͂���܂���B�����ŁA�l�̒����Ƃ��Ă͒�������ł����A���
���]���E�����[�t�Œ������܂����B
����ɔ����u���b�W�̒������s���܂����B�����͕W�������߂ɂ��܂����B
�s�b�`���������A���ׂẴt���b�g�łRcent�ȓ��ɓ����Ă���Ǝv���܂��B
�e�[���s�[�X�͖���Ȃ��璲�����A���ʓI�ɂ��Ȃ�グ�܂����B
�u���b�W�T�h�����̌��̊p�x�͔����ł����A������X�C�[�g�X�|�b�g�������
���ł��B
���������u�f��
�i�b�g�͊��肪�����A�y�O���ƃL�b�L�b�Ɖ��𗧂Ă܂��B���i�Ȃ炷����
�O���t�e�b�N�Ɋ�����Ƃ���ł����A����̓I���W�i���̏�Ԃ��ł��邾���c��
���������̂ŁA�ʂ̕��@���Ƃ�܂����B
�i�b�g�a�̃l�b�N���̌`������炩�ɂ��A����ɓ������u�f����h��܂����B
�������u�f���͈ȑO�ɂ���ʂɎ�ɓ���₷�����̂����������Ƃ���������
�ł����A���̎��͂��܂�s���Ɨ��܂���ł����B����̓��[�J�[���猴�t�i�H�j
�̎����i�����ł��A���O�̃e�X�g�ł��Ȃ�ǍD�ł����̂ŁA�����h��܂����B
���ʂ͑�ς悢�ł��B�y�O���Ă̒��������Ȃ�X���[�X�ł��B
�u���b�W�T�h��������ɂ������Ɏv�����̂ŁA��͂�������u�f���ŏ�����
�܂����B
�i�������u�f���Ɋւ��Ă͂܂��ʂ̃M�^�[�ł��e�X�g���ł��j
����h���Ɠ����z��
�p�[�c��S���͂����āA�e�L���r�e�B�ɋ�h����h��܂����B
�z���̓m�[�U���G���N�g���b�N�̂V�U�N�̂��̂ƃE�G�X�^���G���N�g���b�N��
�V�O�N��̕��������Ɏg���܂����B�ꕔ��b�L�����g�p���Ă���܂��B�ǂ���
�����g�����͎��s���날��݂̂ł��B���낢�뎎���Ă݂ăs�b�N�A�b�v����̔z
���̓m�[�U���G���N�g���b�N�ɂ��܂����B
��b�L���̓A�[�X�W�݂̂ł��B�A�[�X�͊�{�I�Ƀ��[�v���o���Ȃ��悤�ɍl
���t�����g�u�n�k�̂Ƃ���ł̈�_�A�[�X�ɂ��܂����B
�L���p�V�^�͐���ނ����������ʃI�����W�h���b�v�S�P�W�ɗ��������܂����B
�n���_�̓q���[�}���M���N���V�b�N���g�p���܂����B
���s�b�N�A�b�v
�s�b�N�A�b�v�͋����J�o�[���͂����܂����B���[�h���͑O�q�̒ʂ�m�[�U���G��
�N�g���b�N�ł��B
����Ń|�[���s�[�X�̏o���ƃs�b�N�A�b�v���̂̍��������Ċ�]���銴����
�߂Â��܂����B
�X���Ƃ��ă|�[���s�[�X�̃l�W�����Ȃ���ߍ���Ńs�b�N�A�b�v���̂��������
���������ł��B������g���C�A���h�G���[�ł��B
����
�A�[�j�[�{�[���́@�O�P�O�Z�b�g�Œ������܂����B
�����I�Ɍ��āA���Ȃ�悭�Ȃ����Ǝv���܂��B�Ђ���Ƃ����玟�̃��R�[�f�B��
�O�ɓo�ꂷ�邩������܂���B�܂����̎��͂����܂��B
(2003.05.18)
��back to top
�@
�ǎ҂̐����̂R ���M����
���ӂɂ����Ē����Ă���M�^�[�����Takashi-Inoue Guitars [TIG]�̈��M����
����A�R�[�e�B���O���Ɋւ��郊�|�[�g���͂��܂����̂ŁA�f�ڂ��܂��B
�@����������������������������������������������������������������������
���āA�R�[�e�B���O���ł����E�E�E
�_�_���IEXP16�t�H�X�t�@�[�u�����Y
EXP11�u�����Y�^�C�v
����������Ă��܂�
EXP11�̕��́A�����ŋߎ�ɓ���� �u�E�E�Ƃ�����16���ɐ�Ȃ̂Łv�@
�d���Ȃ��g�p���Ă��܂��B
EXP16�́A�ق�1�N�O����g�p���Ă��܂�
�Ƃɂ����A�������悭�A�ቹ�̐F����2�����͕��C�ŃL�[�v�ł��܂��B�����āA
��Ȃ�!!
����́A�т�����ł�
�������SIT�̃t�H�X�t�@�[�u�����Y���g�p���Ă��܂����B
�������������̂ł����A���ۂ́A1�X�e�[�W��e���Ƃ����ƁA�ቹ�͂�����A��
�炫�炵�Ă����v���[�������A�߂����ȉJ�̓��̃T�E���h�ƕς���Ă��܂��Ă�
�܂����B
�����炱���A�f�l�Ȃ���X�e�[�W�̑O�́A���n�[�T�����I���ƁA������
���āA�V�������ƒ���ւ��o�����̂ł����E�E�E
����1�N�́A�X�e�[�W�̑O�ɖ����Ă���ł�
�T�E���h���A����Ȃɗ��Ȃ�����ł�
�R�X�g���������Ƃ�����A�u��[�[�����̂܂܂�����!!�v�Ƃ������Ƃ������܂�
���B
�����āA2-3�����߂��āA�ł��グ�ł����Ⴊ����e���Ă���Ƃ��A�����3����
����܂����B
����͂т�����ł�
�D�݂Ƃ��ẮA�ቹ�̂��炫�犴�����炵��EXP16�����p���Ă��܂�
EXP11�́A��͂�ቹ�̃R���v���b�V���������������悤�Ȋ���������Ȃ�����
���āA�R�[�h�X�g���[�N�ł����Ⴊ������̂��ǂ��悤�ł��ˁB
�l�b�g�ł́A12�� EXP38 ���̔����Ă��܂�
���X�����e���Ȃ�12�������A���̌��̂悢�Ƃ��낪�o��Ǝv���܂��B
[TIG]�̘A����
Takashi-Inoue Guitars [TIG]���M
��979-1754
�������o�t�S�Q�]���������v��37
�s�d�k/FAX 0240-36-2079
g_valley@d2.dion.ne.jp
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/guitar_valley
�l�b�g�ʔ̂̃y�[�W�ł�
�@����������������������������������������������������������������������
���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������
�肦��ƍK���ł��B
(2003.04.08)
��back to top
�@
�e�f�y�S�O�O���`���[���i�b�v����
�����̃��|�[�g�Ŏ��グ���M�^�[�̉����A���c�N���̃o���h�u�~���N�������O�v
�@�̂b�c�Œ����܂��B
�~���N�������O�̃t�@�[�X�g�~�j�A���o���u�~���N�������O�v03/5/28����
�EM-1�u�������|���v
�@�Е��̃`�����l���Ŗ��Ă���̂��uFGZ400�v�B�����Б����^�L�����[�J�[��
�@�r���e�[�W�M�^�[�ł��B
�EM-2�u���ȏЉ�v
�@�\���ȊO�̃o�b�L���O�S��
���c�N����̃I�t�B�V�����E�F�u�T�C�g�͂�����@
http://www.machidakou.com/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
��h���̃e�X�g�ŁA�t�F���i���f�X�̂e�f�y�S�O�O���{�p�ӂ��Ă��炦�܂����B
�������̂���{�茳�ɂ��邱�Ƃ͂���Ȃɖ����̂ŁA������@��ɂ��낢��e�X
�g���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
��{�͂��̂܂܂ɁA������{�ɂ͎�������āA���̍������悤�Ƃ����킯�ł��B
�J�[�{�����h��ꂽ���͂��̂܂܂ɂ��āA���h�������̂��`���[���i�b�v����
�������Ƃɂ��܂����B
�`���[���i�b�v�Ƃ����Ă��A��v�ȃp�[�c�����������̂ł͂e�f�y�S�O�O�ƕʕ�
�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�o���邾�����`���Ƃǂ߂��܂܂Ƃ����e�[�}�ł���Ă݂�
���B
���l�b�N������
�܂��l�b�N�����ł��B�茳�ɓ͂������_�ł����Ȃ�悢��Ԃ������̂ł����A��
��ǂ���Ԃ�ڎw���܂��B�o���邾���l�b�N���܂������ɂ��Ă���A�t���b�g��
���肠�킹�����܂����B�t���b�g���`�E�l�b�N�G�b�W�̐��`�������čs���܂����B
���u���b�W����
�g���������j�b�g�̍��������l�W����ߍ��݁A�u���b�W�v���[�g���s�b�^���ƃ{
�f�B�[�ɂ��悤�ɂ��܂����B�e�u���b�W�E�T�h�������A�W����葽�����
�̌����ɃZ�b�g���܂����B
���Ɋe�|�W�V�����ʼn������āA�s�b�`���m�F���܂��B���X�̏�ԂƂ͕ς��Ă�
�܂��̂ő����̌덷�������܂��B�T�h���̒����l�W�ō��킹�Ă����܂��B
�ǂ���ԂɂȂ�����A������x�����̃`�F�b�N�ł��B�������`���[�j���O���Ď�
���e�������Ċm�F���܂��B�T�h����傫�����������Ƃ��ɂ́A�����������ɕω�
���Ă��邩������܂���B�C�ɓ���Ȃ��������x�T�h���̍��������āA
�܂��s�b�`�̊m�F�����܂��B�C�ɓ���܂ł���̌J��Ԃ��ł��B
���i�b�g�̌`���ύX����
�i�b�g�͂����ނ˗ǂ��̂ł����A�w�b�h���̃G�b�W�̏o�����D���ł͂���܂���B
�w�b�h���̂��ǂ��₷��ŏ��������Ă����܂��B�����猩��ƃw�b�h���Ɍy��
�J�[�u��`���Ă���悤�Ȋ����ł��B�����Ƃ͂��Ȃ�p���Ă���̂ł����A
��������Ƃ́A�M�u�\���̃i�b�g�Ɍ�����悤�Ȋ��炩�Ȍ`��ł��B
�i�b�g�̍a�ɂ̓e�t�����I�C����h���Ă悭����悤�ɂ��Ă����܂����B
����h����h��
�R���g���[���L���r�e�B�[�ƃs�b�N�A�b�v�L���r�e�B�[�ɋ�h����h��܂��B�z
�����ʂ�g���l���ɂ��h����h��܂��B�R���g���[���L���r�e�B�[�͏����͂ݏo
���ēh���āA�W�̗��ʂƓ��ʂ��͂����悤�ɂ��Ă����܂��B
�L���r�e�B�[�̊W�̗����ɂ���h����h��܂����B
���z����ύX����
�܂��X�C�b�`�ȍ~��ς��Ă݂܂��B�v�d�̒P�����g���܂����B
�ŏI�A�E�g�͋�b�L���ƃp���ł��B
�A�[�X���̔z���͂u�n�k�|�b�g�ɏW������悤�ɂ��A��{�I�ɂ����ł̈�_�A�[
�X�̍l�����ł��B
�L���p�V�^�̓X�v���O�S�P�W�̂O.�O�Q�Q���g���܂����B
�ȏ�̏�ԂŖ^���R�[�f�B���O�̌���Ɏ��Q�������܂����B�e�퍂���M�^�[�̂�
���ŁA�艿�S���~�̃M�^�[���ǂ������]������̂��m�肽����������ł��B
����ɂ̓I�[���h�̂U�O���~�A�P�T�O���~�̃M�^�[��A�^�Ђ̃J�X�^�������M�^�[
�Ȃǂ�����ł��܂����B�����Ŏ����e�������Ă��炤�ƁA��ύD�]�ŁA�Ȃ�Ɖ�
�Ȃ��̖{�Ԃł��̂e�f�y�S�O�O���̗p���ꂽ�̂ł��B�����܂����B
�e��M�^�[�ƌ�����ׂ����Ȑ����ł��B
�`���[�������e�f�y�S�O�O�́A������{�̂e�f�y�S�O�O�Ƃ͈Ⴂ�����āA���͂�
��{���r���Ă��Ӗ����Ȃ����炢�Ɏv���܂��B�����̌v��͂��낭�����ꋎ��
�܂����B����ŁA������{�̂ق��������悤�ȃ`���[�������邱�ƂɌv��ύX��
�܂����B
�`���[���̕����ɊԈႢ���Ȃ����Ƃ��m�M���āA����ɓO�ꉻ��}��܂����B
�s�b�N�A�b�v����̔z�����ꕔ�v�d�ɂ��܂����B
�ꉞ���̑��̔z�������{�Ƃ������ɂ��Ă݂܂������A�ǂ����������藈�Ȃ���
���낪����܂��B
����ŁA���̓�{�̖{�������Ă��鉹���i����͔S��̂���d�߂̊����A������
���̓����n���̌����������G�l������ɉ��߂������̂ł����j�����������Ƃ��l
���܂����B
���x���̎��s����̌��ʁA��{�͂v�d�𒆐S�ɔz�����A�L���p�V�^�̓R�[�l���_
�u���[���g�p���܂����B������{�̓m�[�U���G���N�g���b�N�i�v�d�̊W��ЁA
�J�i�_�j�̂P�X�V�U�N�̃��C���[�𒆐S�Ɏg�p���A�L���p�V�^�̓X�v���O�S�P�W
�ɂ��܂����B
�܂��A���A�̃n���o�b�J�[�����ƕ��s�ɂȂ�悤�ɁA�G�X�J�b�V����������ďC��
���܂����B
���̏�Ԃł�����Ɨl�q�����邱�Ƃɂ��܂����B��{�̉��͔��������قȂ�܂�
���A���ꂼ�ꂩ�Ȃ薞���ł�����̂ɂȂ��Ă���܂��B
����������Ƃ̂܂Ƃ�
�l�b�N��t���b�g�������B
��h����h�����B
�z����ǂ���Ǝv�����̂ɕύX�����B
�L���p�V�^�����������B
�G�X�J�b�V�����C���B
���ʂƂ��āA��v�ȃp�[�c�͂��Ƃ̂܂܂ł����Ȃ�悢��ԂɎ����Ă��������ł��B
�ߓ����Ƀt�F���i���f�X�Ɏ�������ŁA����ɍו��ɂ��Č����������Ǝv����
�܂��B
(2003.03.23)
��back to top
�@
��̓��d�h���@�� from �t�F���i���f�X
��̓��d�h���ɂ��ăt�F���i���f�X����̕ł��B
�A�`�\���r�o�W�O�O����肵���Ƃ��ɁA�������̃M�^�[���[�J�[�E�H�[��
�u��̓��d�h������ɓ��������ǁA�e�X�g���Ă݂܂��H�v
�ƌ����āA��r���n���܂����B
�t�F���i���f�X�ł́A�����悭�����M�^�[���Q�{�p�ӂ��āA����̓J�[�{���A
��������͋��h���ăe�X�g����ƌ����Ă���܂����B
�����āA���̌����ƕ��l�̂Ƃ���ɓ͂��܂����B
�t�F���i���f�X�̊֍�����A���ۂɍ�Ƃ��Ă��ꂽ�t�F���i���f�X�Z�p���̋g�c
����Ɋ��ӂ��܂��B
������������������������������������������������������������������������
�M�^�[�̓t�F���i���f�X�I���W�i���̂e�f�y�S�O�O�ł��B
�s�b�N�A�b�v���C�A�E�g�͂r�r�g�ŁA�P�u�n�k�A�P�s�n�m�d�ł��B
�J�[�{���Ƌ�̂��̂�e���Ă݂�Ɩ��炩�ɉ����Ⴂ�܂��B
�Z�p���̋g�c����̃C���v���b�V�����͎��̒ʂ�ł��B
���n�C�����͂悭�Ȃ��Ă���
���m�C�Y�V�[���h���ʂ͓���
���h���̐������ʐ��Y�ɂ͌����Ă��Ȃ��i�������̂��ߍ��ѓh��ɓ��A�G�A�[
�@�K�����g���ƂȂ�ƃT���o�[�X�g/�V�[�X���[�n�ł̓}�X�L���O���K�{�ƂȂ�j
���̃n�C�̔������ǂ��Ȃ��Ă���Ƃ����Ƃ��낪�A�����͂����肷��Ƃ��A����
������Ƃ��A�L�т₩�ɕ�������Ƃ������A�l�̃��|�[�g�̊��G�����߂Ă���
�̂�������܂���B
�m�C�Y�E�V�[���h�Ɋւ��Ă͕��ʂ̏�Ԃł͂��܂荷�������Ȃ���������܂���B
����������ƍ������g���̓d�g�i�Ⴆ�Όg�сj����̏�Q��h���Ƃ����悤�Ȃ�
����ł͍����o�邩������܂���B��̓��d�h���̖{���̎g�p�ړI�͂��̕ӂ��
����܂��B�X�^�W�I�ł͂Ƃ��ǂ��g�тɂ���Q�Ǝv����m�C�Y���������Ă�
�܂��B�����������ׂ���Ă���킯�ł͂���܂��A�ǂ��l���Ă��g�шȊO��
�������Ȃ��Ǝv����Ȃ̂ł��B
�ł�����A�G���W�j�A�ɂ���ẮA�X�^�W�I�ւ̌g�т̎������݂��֎~���Ă���
�����ł��B�l�͂����܂ł͂��܂���̂ŁA�t�Ɋy�푤�ŏo���邾���h�䂵������
�l���Ă��܂��B
��Ɛ��̖ʂŁA��ʐ��Y�Ɍ����Ă��Ȃ��_�́A�l�B�A�}�`���A�ɂƂ��Ă݂��
��̗��_�ɂ��Ȃ�܂��B���[�J�[�������ł��Ȃ����Ƃ�����قǂ̋�J���Ȃ���
�s�ł���̂ł�����A�v�킸�ɂ�܂肷��Ƃ���ł��B
��̓��d�h���́A����ς�ǂ���������Ȃ��A�Ƃ����v���������������܂����B
������̃��|�[�g���͂���������Ă��������܂��B
(2003.03.06)
��back to top
�@
�ǎ҂̐����̂Q�@j-i����
���ǂݒ����L���������܂��B
�ǎ҂̕����炢�낢��ȃR�����g�����������Ă���܂��B
�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�Ǝv���̂ŏЉ���Ă��������܂��B
���̂Q�� j-i ����̃��|�[�g�ł��B
������������������������������������������������������������������������
�u�s�b�N�v�̘b���ʔ����A�����v�����Ƃ��낢��Ƃ���܂��āA���|�[�g������
���������܂����B
***�N���C�g���̃s�b�N***
�uꈍb���v�Ƃ����̂͒m��Ȃ��̂ł����A�uHUMAN GEAR CO.,INC�v�Ƃ����̂�
�g���Ă܂��B
�uCLAYTON�v�Ə����Ă��邩��A�N���C�g�����D�D�D�ł���ˁH
������ƌ��߂̃v���X�`�b�N�Ƃ��������B�����F�ł��B
���Ƃ��Ɗ������������܂��B
�u�l�Ԃ̒܂Œe�������Ɏ��Ă���v�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�̂悤�ł��B
�ƂĂ��C�ɓ����Ă���܂��B
***����~�߂ɂ���***
�u�s�n�q�s�d�w�v�ł����A���ɂ͂�����Ƃ��ׂ��Ďg���Â炢��������܂��B
���܂�����������ł����A�ŋ߁uScotch�@�N���A�[�e�[�v�i18mm*35m�j�v�Ƃ�
���̂�\���Ă݂��Ƃ���A�i�i�ɒe���₷���Ȃ�܂����B
�iScotch�̉҂ł͂���܂���j
�O�q�̃N���C�g�����s�b�N��������Ɗ���₷���̂œ\���Ă܂��B
�t�B�b�g���A�ō��ł��B
�i������������ǂ��Ȃ邩�A�́A������Ƃ킩��܂��j
***�X�v���[���E�s�b�N***
���̃s�b�N�ŁA������Ɣ��������ۂ��s�b�N�ł��B
�f�������Ɏ��Ă܂����A�Ⴄ�f�ނ������ł��B
�V�f�ނ̃s�b�N�̗�ɘR�ꂸ�A�ϖ��Ր��ɗD��Ă���悤�ł��B
FERNANDES��Terry Gould�Ȃǂ���o�Ă���悤�ł��B
�����ꂪ�u�v�����v�Ƃ������G������A�Ȃ��Ȃ��C�ɓ����Ă܂��B
�ŋ߁AFERNANDES�̃��m�͌`�ς��A���ʂ̎O�p�I�j�M���^����
�u�s�n�q�s�d�w�v�Ɏ����Ƃ������`�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�Ȃ�ł��ȁH�@�ȑO�̕����g���₷�������悤�ȁD�D�D�B
�~�������Ό��s�̃��m�ƈȑO�̃��m�Ƃ̒��ԕӂ�̋Ȑ����~�����D�D�D�B
�s�b�N�̃t�H�����ƒe���₷���Ɖ��̊W���āA����ς艽������Ǝv�����
�����D�D�D�B���������������āA����̂ł��傤���H
���[�J�[�́A�ǂ��������R�Ńf�U�C�����Ă����ł��傤�ˁH�i�j
***�������s�b�N***
���������Ă݂܂����B�\�z�Ƃ͑S���Ⴄ���I�@�����ł��ˁB
���̉����ǂ��g�����l����̂��y�����ł��B
����A�r�܂ɂ��郊�y�A�V���b�v�ɃM�^�[��������肢���܂����B���̎d�オ
���A�����ł����B
�������������Ⴂ�I�@�e���₷���I�I
���낢��ƃM�^�[�ɂ��Ẳ��[���b�������ėǂ������B
�������������o��ł͂���܂������i����ł��\�z�����������j�A�[������
�b�オ����܂����B
�M�^�[�̒������ǂ��ƁA�z���g�Ɋy�ɒe���܂��ˁB
������������������������������������������������������������������������
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
��j-i����̃v���t�B�[���i�����g�̏������݂ł��j
�𓊂���Γ���悤�Ȓʂ肷����̑�^�M�^���X�g
Works
���A�}�`���A�ł�
j-i����̊y����G
�����Ȃ��ł�������
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������
�肦��ƍK���ł��B
(2003.02.15)
��back to top
�@
�ǎ҂̐����̂P�@����O����
���ǂݒ����L���������܂��B
�ǎ҂̕����炢�낢��ȃR�����g�����������Ă���܂��B
�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�Ǝv���̂ŏЉ���Ă��������܂��B
�ŏ��̓v���M�^���X�g�̐��삳��ł��B
����������������������������������������������������������������������
���Ԃ������Ă܂��I����ł��I
�����ȃ��|�[�g�A�����ւ��[���ǂ܂��Ă��炢�܂����B
���̃��C���M�^�[�ł���A64�X�g���g�ɂ́A�����炭���ʂ̃h�[�^�C�g���h����
����̂ł����A���������̓��d�h����h���Ă��������ɂȂ肻���ł��ˁB
�n���_�ɂ��Ă������ւ�Q�l�ɂȂ�܂����B�s�b�N�ɂ��ẮA���̓��[�h�A
�J�b�e�B���O�A�A�R�M���Ŏg���킯�����Ă܂��B�Ƃ��ɃJ�b�e�B���O�̂Ƃ��͌�
���炷���Ɨ���Ă����s�b�N�������ł��B
���ǂ͐m����̌����Ƃ���A�g���C�A���h�G���[�̂���Ԃ��ł��ˁB�����̎���
����������Ă������A���܂ɂǂڂɂ͂܂�����B���ꂩ����M�^�[��e��
�Ă��������͂����Ȃ�ł��傤�ˁB
�m����Ǝ��Ԃ������A���Ђ��낢��Ǝ����������Ă��炦��Ȃǂƍl���Ă܂��B
����Ƃ��̂������̃s�b�N�̘b���ł����A�l�̏ꍇ�A�G���L�̎��̓A�[�j�[�{�[
���̃e�B�A�h���b�v�̃w�r�[���g���Ă܂��B�����ԑO�ɉ����D���Ŏg���Ă���
�s�b�N���A�����ł����قƂ�ǎ�ɂ͂���Ȃ��̂ŁA��ɂ͂���₷���D�݂�
�����������A�[�j�[�{�[���������킯�ł��B�ŁA�A�R�M�̃U�b�N�������J�b�e�B
���O�̎��͂��ɂ�����g���Ă܂��B���Ȃ݂ɂ��ɂ���ł͂܂��C�ɂ��������̂�
�������Ă܂���B����Ɩl�̏ꍇ�A���[�h�̎����A�R�M�̃A���y�W�I�̎�����
�w�Ƃ��́A�{�f�B�ɂ������肵�Ă܂���B
����Ǝ��_�Ȃ�ł����A���{�l�͘r�Ƃ���̎��ʂ��A�����Ƃ��I�ɔ��l�⍕�l��
����ׂď��Ȃ��Ǝv����ł��B���ʂ�����A�Ƃ�������X�s�[�h�́A����
�Ȃ�Ǝv����ł��B�ŁA�l�̓J�b�e�B���O�D���Ȃ̂ŁA����������Ȃ����߂ɂ�
�邽���傫���r�Ǝ����ӂ�悤�ɂ��Ă܂��B�ȂA���{�l�ăN���b�N�ɂ͂�
�킹���Ă��X�s�[�h�����Ȃ��悤�ȋC�����܂��H�����قǏ��������w�Ƃ�
���{�f�B�ɂ����Ȃ��̂��������炫�Ă��āA���[�h�̎����A�R�M�̃A���y�W�I��
����������x�傫�����������ق����A�X�s�[�h�����ł�悤�Ȋ��������܂��B
�܂��A�����e���ɂ���������A�~�X�^�b�`��������Ƃ�������͂��܂����B
�ł͂ł́A���ꂢ���܂��B
����������������������������������������������������������������������
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
������@�O����̃v���t�B�[��
1959�N3��14�����܂�
�R�`���R�`�s�o�g
���Z������M�^�[����ɂ���B19�˂̎��㋞�B�A���E�~���[�W�b�N�E�X�N�[��
�ň�㎁�Ɏt���B�����Ƀ��C�u�n�E�X���Ŋ������n�߂�B�ŋ߂ł͌��c�m���A��
�����ߓނ̃��R�[�f�B���O��C�u���n�߁A��،c�ꎁ��CM�AThe Choice�ł̃�
�C�u�����ƕ��L���������B������95�N����Dr.K Project�ɎQ���B���R�[�f�B���O
��C�u�͓I�ɍs���Ă���B
Works
���Q���A���o����
�@�Έ䗳��w�G�b�`�x
�@�I���W�i���E�T�E���h�E�g���b�N�w�S�[�X�g�X�[�v�x
�@���[���h�b�O�X�w���[���h�b�O�X�x
�@V.A�w�X�i�b�v�E�A�b�g�E�A�E�`�����X�x
�@���E�W���}���g�wHEM�x
�@�X�ፁ�D�wLOVE OR DIE�x
�@V.A�w�g�b�h�͐^���̃X�[�p�[�X�^�[�x
�@�����O���A�o�J�{����� ���w�X�[�p�[�E�M�^�[�E�g���r���[�g��1.2�x
�@V.A�w�݂ǂ�̃}�L�o�I�[ �܂��ʼn̍���x
�@�{���D�q�w�s�ӑł��x
�@V.A�w���A���T�E���h�`���̃��O���b�g�i�Z�K�T�^�[���j�x
�@�R�؍N���w���x
�@�������X���w���{���N2000�n��2�x
�@���c�@�n�w�O�����痈�����{�ꎍ...�B�x
�@Dr. K Project�w�G���L�o���h�����������x��
�@���c�m���wa day off my life�x
�@���c�m���w��Ǝ��x
�@���R��t�wegoist�x
�@�牮���ߓށw�e�ۂƉԁx
�@V.A�wQueen's Fellows�`yuming 30th anniversary cover album�x
�������r�f�I
�@�{���̃u���[�X�o�b�L���O�@���b�g�[�~���[�W�b�N���@
��CM��
�@�����e�����b�Z�[�W�A�g�������N�A�A�c�M�A�����O���[�v�A
�@���Y��CM�A�E�ғ��}�}�C�g�K�C���A�Z�F�����ANTT DoCoMo�@etc
���c�A�[/�T�|�[�g��
�@���[���h�b�O�X
�@��䂳���
�@�X�[�p�[�E�M�^�[�E�g���r���[�g
�@�U�E�Y�N��
�@���c�m��
�@���E�W���}���g
�@�ēc����
�@����c��
�@���R�Y�O
���G���W�j�A
�@Dr.K Project�w�G���A�E�R�[�h615�g���r���[�g�E���C�u�x
���삳��̊y����G
Fender Stratocaster64'
Fender Jazzmaster59'
Fender Japan Telecaster
Tokai Lespaul
Hofner �t���A�R�@Unknown
Aria Ventures Model2002
Kel Kroydon Acoustic (Made By Gibson) 1931'~1933'
Aria AC80 �G���K�b�g
Fender Princeton Reverb 64'
Soundcity LB50 Plus
Ross Comp
Handmade Fuzz
Honda Sound Works Lenny
VOX WOW 70'etc
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
���肪�Ƃ��������܂����B�F�l����M�^�[�ɂ܂�邢�낢��Ȃ��b����������
�肦��ƍK���ł��B
(2003.02.15)
��back to top
�@
�n���_�̂��̌�ƃq���[�Y
�ȑO�ɕ����n���_�̉��F�̑��҂ł��B
��ʓI�ɂ��̂悤�ȁu����Ȃ��Ƃ���͂��Ȃ�����Ȃ����v�ƌ�����悤�Ȏ�
���ɂ��āA���\����̂ɂ͖���������܂����B�Ƃ������_�������Ƃ��������
���M��I�J���g�ɂȂ��肪��������ł��B�l�Ƃ��ẮA�n���_�ɉ��F��������
�Ƃ������Ƃ�m���Ă��������ŁA���_�͊F����ɏo���Ă������������A�ƍl��
�Ă����킯�Ȃ�ł����A�u���ʂ������v�Ƃ�����������悤�Ȃ̂ŁA������
���\���悤�Ǝv���܂��B
�������A�����ƌ�����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��A�v���A�}��킸�A�@��L�閈�Ɏ���
���Ă���������z�E��ۂ�l�Ȃ�ɉ��߁E�����������̂Ȃ̂ŁA���l�I�ȗ��Â�
�͑S������܂���B�����܂Ŗl�������Ȃ�Ȃ����Ǝv���Ă���Ƃ������Ƃ�
�߂��܂��A���炩�̎Q�l�ɂ��Ă���������K���ł��B
�ȑO�̃��|�[�g�Ŏ��グ�Ă���W��ނ��������Ă��܂���̂ŁA�����ӂ�����
���B�ŋߐl�C�̂��郁�[�J�[�̂��̂Ȃǂ̓e�X�g�Ɋ܂܂�Ă��܂���B�܂�����
����W�߂Ă���Ă݂������̂ł��B
������������������������������������������������������������������������
�S�ʓI�ȈӖ��ŕ]�����ǂ������̂�
�i�P�j�q���[�}���M���E�N���V�b�N
�i�P�f�j�����_�[�\���_�[
�i�Q�j�J���_�X
�ł��B
���̏[���x�ŕ��ׂ��
�i�P�j�q���[�}���M���E�N���V�b�N
�i�Q�j�����_�[�\���_�[
�i�R�j�J���_�X
�̏��ł��B
���Q�G�ӂƂ���~�L�T�[�̂g���̓q���[�}���M���E�N���V�b�N�����܂��A��
�g���W����X�^�W�I�̔z������蒼���Ƃ����āA�q���[�}���M���E�N���V�b�N
���������ł��B
���ӂ��ׂ��_�̓q���[�}���M���E�N���V�b�N�ɂ͂Q��ނ���Ƃ������Ƃł��B��
�O�̃A�����J���ƁA�ŋߗ��ʂ��Ă���h�C�c���H�̂ӂ��ł��B�l�B�̃e�X�g��
�g�p�����͈̂ȑO�̃A�����J���̂��̂ł��B�i�e�X�g���h�C�c���̂��̂͂܂���
�������Ǝv���܂��j
����ɒ��ڂ����
�i�P�j�v�a�s
�i�Q�j�J���_�X
�i�R�j�����_�[�\���_�[
�ƂȂ�܂��B
����\���l����Ƃv�a�s�̓ƒd�ꂩ������܂���B�I�[�f�B�I�t�@���̊Ԃŕ]��
���ǂ��̂͂悭�킩��܂��B�������A���̕��A���y�I�ȁu��v�i�Ƃ��������͋C
�Ƃ������j�����銴�������āA���ɃN���A�[�Ȉ�ۂ������Ă��܂��܂��B�꒷��
�Z�Ƃ��������ł��B���̂�����͐��쌻�ꑤ�ƃ��X�i�[���ł͈ӌ����Ⴄ�̂���
����܂���B
�J���_�X�̍���͌����ł��B
���݊��Ƃ����܂����A���y�̃��A���e�B�[�ōl�����
�i�P�j�J���_�X
�i�P�f�j�����_�[�\���_�[
���o�����Ǝv���܂��B
�J���_�X�ƃ����_�[�\���_�[�͊�{�ƂȂ鍇���ɓ������̂��g�p���Ă���悤��
���B
���ꂼ�ꐻ�����@��t���b�N�X�ɍH�v�����Ă���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA����ňႢ��
�łĂ���̂�������܂���B�ʔ������̂ł��ˁB
�v�a�s�A�J���_�X�A�����_�[�\���_�[�E�E�E��ܗL�ł��B���Ђɂ���ܗL�͂���
�܂����A���̂����܂�]������������܂���ł����B
�@�O�q���܂����悤�ɑ����]���ł́A�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɂ����Ȃ������K�`�b
�Əo���Ă����q���[�}���M���E�N���V�b�N���D�]�ł����B����̃R���g���[��
�̓n���_�ȊO�̗v�f�ʼn\�ł���Ƃ������f���������悤�ł��B����̐��Ƃ���
�̓q���[�}���M���E�N���V�b�N�Ƌ���̑g�ݍ��킹�����������Ƃ������̂�����
������܂����B
�����_�[�\���_�[�͕��ʂɕ]�����ǂ��ł��B�v���E�A�}�̑o�����瓯���悤�Ɏx
������Ă܂��B
�l�̓J���_�X�̔��G�肪������D���ł��B�����������ɏd�S��������ƍ��߂�
�Ȃ銴���E�E�D�݂Ȃ�ł��B �i�J���_�X�t�@���ł��I�j
�l�̌���ł����ƃM�^�[�̔z���ɂ̓J���_�X�������_�[�\���_�[���g�����Ƃ���
���Ȃ�܂����B�g�������͂��̃M�^�[�ŃC���[�W���鉹�ɂ���āE�E�E�ł��B��
�̃n���_�́A���낢�����Ă݂Ăǂ����Ă��^�₪����Ƃ����Ƃ��Ɏ����Ă݂�
���܂��B
�b���ς���āA�q���[�Y�ł��B
�O��̃n���_�̃��|�[�g�̎��ɂ����b�ɂȂ����c������u���̗ǂ��q���[�Y
�������v�Ƃ����ēn����܂����B
�{�����ȁH�Ǝv���ă}�[�V�����Ŏ����Ă݂܂����B�ǂ���ł���A���ꂪ�B
�h�C�c�̃E�B�b�N�}���ł��B
�q���[�Y�Ɋւ��Ă��e�Ђ̐��i���g���Đ��삳�ꂽ�����p�e�X�g�b�c������܂��B
�q���[�Y�����̉����܂܂�Ă��āA���ꂪ������ǂ������ł͂����ł����A
�����I�ł͂���܂���B�q���[�Y�L��̂��̂̒��ł̓E�B�b�N�}������Ԃł����B
�E�B�b�N�}���̓h�C�c�H�����H���āA�����H��ɃV�t�g���Ă��Ă��܂��B��
��������܂������A�h�C�c�H�ꐻ�̕��������ǂ��ł��B�h�C�c�H��̂��͎̂c�O
�Ȃ��獡�͗��ʍɂ����ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�v���@�̃p�[�c�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�����Ă݂܂�����A�u�������X�`���[�_�[��
�q���[�Y�z���_�[���E�B�b�N�}�����Ȃ̂Ńq���[�Y�������̓E�B�b�N�}�������
�����ȁH�v�Ƃ̂��Ƃł��B���m�F�Ő\����܂��A���ɁA���Ƃ��͂��
�Ă�݂����ł��B�c�����킭�u�E�B�b�N�}���̃q���[�Y�z���_�[�������ǂ�
��v�E�E�E�E�E�X�ł��B
�ʍ��Ń��|�[�g���Ă����̓��d�h���ɂ��Ă��A�����r�b�N�͐̂���g�p���Ă�
��悤�ł��B
�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��A�l�͂R�O�N�߂������Ă����l�̌��ǂ������Ă���Ƃ���
�����ł��B���܂Œ��ڂ��ĂȂ��āA�Ȃ�������ɂ��Ă��������Ȃ̂��ȂƂ��v��
�Ĕ��Ȃ��Ă܂��B�����Ƃ����Ȃ�������Ǝv���������̂���ł��B
�ł͂ł́@�܂�
(2003.02.09)
��back to top
�@
��̓��d�h���@���p�ҁ@���̂P
��̓��d�h���̎g���݂����l���Ă݂܂����B�i�A�`�\���̋�̓��d�h���͐�����
�́u���d���h���v�Ȃ̂�������܂��A���̈Ⴂ���悭�c�����Ă܂���j
�P�[�u���̉��������P����A�N�Z�T���[�Ƃ��āA�P�[�u���Ɋ������铱�d����
�{����A���d���̓h���H�������Ă��܂��B�Ȃ�ł��P�[�u���̊O���ɔ�����
��s�v�ȑѓd������d�����������āA�����悭���邱�Ƃ��o���邻���ł��B
�����������͂ƂĂ������ŁA�h����̂��̂͂T�����Ł��Q�O�O�O�`���R�O�O�O
���炢���܂��B����͍���p�ӂ�����̓��d�h�����͂邩�ɍ����ł��B
�����ŁA�����̉�����悭�ǂ݂܂��ƁA�v����ɃJ�[�{�����ܗL�������d�h��
�̂悤�Ȃ̂ł��B�ł���Ȃ�A��̓��d�h���ŖړI��B���ł���̂ł͂Ȃ����E�E
�ƍl�����킯�ł��B
�ǂꂮ�炢�e����������̂Ȃ̂������Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�p�ӂ����̂̓W���[�W�k�f���̂R���̐ԃP�[�u���Q�{�ł��B����͑S����������
�������̂����o���č�������̂ŁA�v���O�͐�p�̃u���X�̂��̂����Ă�
�܂��B�����e�X�g�ł͓��R�Ȃ��猩���������Ȃ����̂ł��B����̂����̂P�{
�ɋ��h���Ăǂ��ς��̂���r�e�X�g���悤�ƍl���܂����B
���h���ĂP���Ԃ��炢�o���Ďg�p�ɑς��邮�炢�Ɋ������̂ʼn��������Ă݂�
�����B
���Ȃ�{�e�{�e�̉��ŁA�A���������Ƃ��������ł��B�O��ɉ����h�邱�Ƃ́A��
�ꂽ�ꍇ���܂߂āA���Ȃ�e�����肻���ȋC�z�ł��B�e�X�g�ɂ̓X�g���g�ƃ}�[
�V�����̃A���v���g�p���܂����B
���̌㐔���Ԃ����ɉ��F�������܂����B�����ɂ�ēh���疌�̒�R����������
�����悤�Ȃ̂ŁA�����Ɋ����Ȃ���Ώ���̐��\���łȂ��̂�������܂���B��
�����тɉ��F���ω����Ă��܂��B
�R���قnjo�����Ƃ���ʼn������肵�Ă��܂����B�V�[���h�̏ꍇ�ł����ꂮ�炢
�������Ȃ��Ɩ{���̐��\���o�Ȃ��̂ł͂Ǝv���܂����B���������������Ƃ��̓h
���C���[�̔M���𐁂�����Ȃǂ̍H�v�������ق����ǂ���������܂���B
���h�����P�[�u���̉��̈�ۂ́u�D�����v�Ƃ����\�����������Ă���悤�Ɏv
���܂��B�L�����L���������Ƃ��낪���������ĉ������������ĕ������܂��B����
�͓��ɑ�U�������߂ɒe�����Ƃ��Ɋ����܂��B���g���������ς�����Ƃ������
�͂���قǎ����܂��A���̉��ɕt���܂Ƃ��Ă����������ς�����悤�Ɏv��
�܂��B�ʂȌ�����������u���ƂȂ����v�Ȃ����Ƃ������܂��B
���̋�h���͗��[�Ƃ��v���O�̂Ƃ���ŃA�[�X�ɗ�����悤�ɓh���Ă���܂����B
�Ƃ������Ƃ͐M���d�������̓h���𗬂�Ă���킯�ŁA�{���̖ԃV�[���h�Ƃ̊�
�Ń��[�v���`�����Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ�ƍl���āA�Е��̃v���O�t�߂œh�����͂�
���āA�Б������ŃA�[�X�ɗ����Ă��邩�����ɕύX���Ă݂܂����B����Ŏ�����
�݂�ƁA�Ȃ�Ɖ����ω����Ă��܂����B
������̃L���L����������������h��Ȉ�ۂɂ��܂��B���ʊ������[�A�[�X����
����オ���������ł��B����͌��\�D���ł��B
���ɗ��[�Ƃ��A�[�X���������Ď����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�P�[�u���̊O
���ɓ��d�̂��h�����ꂽ��ԂŁA����̓A�[�X�ɂ͐ڑ�����Ă��Ȃ��Ƃ���
���ƂɂȂ�܂��B�O�q�̃I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[�̐����ł͂��̏�Ԃł����炩
�̌��ʂ����肻���ł��B���������Ă݂�ƂƂĂ��u�������v�����ł��B�s�b�L��
�O�̉����u�J���J���v���������ɕ������܂��B�������̓m�[�}���̐ԃP�[�u����
�߂��悤�Ɏv���܂��B
�ǂ̏�Ԃ��ǂ����Ƃ������Ƃ͈�T�ɂ����܂���B�D�������Ƃ������e�̂��̂�
������܂���B�������P�[�u���ɂ��̂悤�ȏ��u�����邱�Ƃʼn��F�ɕω���^��
�邱�Ƃ��o����̂͒m���Ă����ėǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B�P�[�u���̉��������
�炭�e����^����ł��傤�B�v���ӂł��ˁB
��h����h�������̂��Ԏg�p���悤�Ǝv���A�������h�����߂ɉ��炩��
�ی�K�v���Ǝv���܂��B����͂ق�̂�����Ƃ��������Ȃ̂œh���ʂ�
�ނ��o���̂܂܂ł��B
�O�̂��߃P�[�u���̐Ód�e�ʂ𑪂��Ă݂܂����B
���h�������́@�@78pF/m�@�@�@�i�����l����P����������v�Z�j
�m�[�}���ԁ@�@�@�@77pF/m�@�@�@�i�����l����P����������v�Z�j
�ł��B
�Q�l�܂łɂ��傤�ǎ茳�ɂ������P�[�u���̎����l�������Ă����܂��B
������������l����P��������̐Ód�e�ʂ��v�Z���ĂS�̂T���������̂ł��B
����덷�ɂ��Ă͂��e�͂��������B
�W���[�W�k�f���@�@�@���@�@�@ �@�@�@73pF/m
�W���[�W�k�f���@�@�@�ׁ@���@�@�@�@ 76pF/m
�W���[�W�k�f���@�m�[�}���ԁ@�@�@�@ 77pF/m
�W���[�W�k�f���Ԃ� ���h�������́@78pF/m
���[�J�[�s���@����i�@�@�@�@�@�@�@ 88pF/m
�I�[�f�B�I�e�N�j�J�o�b�n�b�b�@�@�@119pF/m
�t�F���_�[����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@119pF/m
�r�o�d�b�s�q�`�e�k�d�w�@�@�@�@�@�@125pF/m
�����X�^�[�q�n�b�j�@�@�@�@�@�@�@�@129pF/m
�J�i���f�r�U �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@150pF/m
�t�F���_�[ Whirlwind�@�@�@�@�@�@�@171pF/m
���Y�^�Ё@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@222pF/m
����e��P�[�u���ŋ�̓��d�h���������Ă݂悤�Ǝv���Ă܂��B
(2003.02.01)
��back to top
�@
�S�A�Ђ̌��@���̌�
�ȑO���|�[�g�����S�A�Ђ̃R�[�e�B���O���̂��̌�ł��B
���܂艹�������Ȃ����߂ɂقƂ�nj��̂��Ƃ��C�ɂ��Ă��܂���ł����B
�y�[�W�̓ǎ҂̕��Ƃ̘b�̒��ł��̌��̂��Ƃ��łĂ��܂����B����ł�`�`���l
���Ă݂�ƁA�����Ă�������܂�R�N���o���Ă��܂�����ł��ˁB�т����肵��
�����B
�����Ă���M�^�[�̓t�F���_�[�́u�G�X�v���v�ʏ̃��x���t�H�[�h���f���ł��B
�ŋߏo�Ă��郍�x���t�H�[�h���f���̑O�g�Ƃ�������y�킾�Ǝv���܂��B
���炽�߂Č����`�F�b�N���܂��ƁA�������Ƀt���b�g�������镔���ɏ����ڗ���
�Ă܂��B���������ς�炸���͂Ȃ��Ȃ��̊����ł��B�v���[�����͉��x��������
�Ă���悤�Ɏv���܂����A���܂�悭�����Ă��܂���B
���ꂮ�炢�����Ȃ��Ɓu������ƒe���M�^�[�v�ɂ͍œK�Ȋ��������܂��B
�ŏ��͂�����ƍ��߂ł����A�����ڂŌ���R�X�g�p�t�H�[�}���X�͍ō����Ǝv
���܂��B
�ŋ߂ׂ̃��[�J�[������R�[�e�B���O�������\����Ă܂����A�v�`�F�b�N��
���ˁB
�S�A�Ђ̌����i�����Ă���悤�ŁA���̂܂ɂ��o���G�[�V�����������Ă��܂��B
�l�����e�X�g���Ă��錷���p���������̂ƁA��蔖���R�[�e�B���O�̂��̂Ƃ��o��
����悤�ł��B���x�͔����ق��������Ă݂����ł��B
(2003.02.01)
��back to top
�@
��̓��d�h��
�A�N�Z�X���Ă��������ėL���������܂��B���ׂT���l���z���܂��Ċ�����
�v���Ă���܂��B
�@�ŋ߁A��̕s�v�c�����������Ă���܂��B�⃀�N���A��b�L���A�����n��
�_�E�E�E�����ċ�̓��d�h���Ȃ�ł��B
����������������������������������������������������������������������������
�@�ȑO����l�̓A�`�\���Ђ̃J�[�{���i�O���t�@�C�g�j�̓��d�h���d�P�P�Q���g��
�Ă��܂����B�����ň����₷���̂��ǂ����A�J�[�{���ł��V�[���h�Ƃ����ړI��
�\���ɂ͂����Ă���Ǝv��������ł��B���ہA�m�C�Y�����Ȃ�h�����Ƃ��o���āA
�������Ă��܂����B�i�d�P�P�Q�ɂ͗n�܃^�C�v������܂��j
�@�Ƃ��낪�Ђ��Ȃ��Ƃ���A��荂���\�ȓ��d�h���͂Ȃ����̂��ƒT���Ă݂�
�C�ɂȂ�܂����B�C���^�[�l�b�g�ŒT���Ă݂�Ɗe�Ђ���J�[�{���̂��̂͂���
���A�j�b�P���̂��́A���̂��̂ȂNJe��łĂ��邱�Ƃ��킩��܂����B
�@�����������̃��[�J�[�ɘA�����Ƃ��Ă݂܂��ƁA����j�b�P���̓V�[���h��
���͂�����Ă�����̂́A�M�^�[�̃L���r�e�B�[�Ɏg���ɂ͕s�K�ł͂Ȃ����A
�Ƃ��������ł����B�َ�����ƐG�ꍇ���\�����L��Ƃ���ł̎g�p�́A���H��
�̖�肩�炠�܂肨���߂ł��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B��͂�J�[�{���̂��̂�����
����肵�Ďg���邵�A����Ȃ�̐��\����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂���
�ʂ����ӌ��̂悤�ł��B
�@�C�O�̃��[�J�[�ŃV�[���h�ނL���Ă�����̂����Ă��J�[�{���������ł�
���A�����ł��n�܃^�C�v���܂߂ăJ�[�{�����嗬�̂悤�ł��B
�@����ł���荂���\�ȕ��͖����̂��Ƒ��k������A�A�`�\���Ђ���u��͂ǂ�
�ł��傤�B�V�[���h�����͔��Q�ɗǂ��̂Ŋy��ł��ǂ����ʂ�������̂ł͂�
���ł��傤���v�Ƃ��������߂��L��܂����B���萫���������ł��B
�@���[�J�[���\�̃X�y�b�N�ɂ��ƁA�J�[�{���Ɣ�r���Ē�R���i�i�ɏ��Ȃ��A
�V�[���h����������I�ɗǂ��悤�ł��B
�@�Ƃ����킯�ŋ�̓��d�h�����e�X�g�����Ă݂邱�ƂɂȂ�܂����B
�i�A�`�\���Ђ̍�������ɂ͑�ς����b�ɂȂ�܂����B���̂����ӂɊ��ӂ�����
�܂��B�j
����������������������������������������������������������������������������
�@�ȉ��ɏq�ׂ鎖���͂Ȃ��̋q�ϓI�Ȏړx���������킹�Ă��Ȃ����Ƃ��A�܂�
�ŏ��ɂ��f�肵�Ă����܂��B�l�̊��ł̓e�X�g�p�̊y��𑽐����낦�邱��
���o�����A�܂��h���Ƃ������̂̔�r���A���̃p�[�c�̏ꍇ�ƈ���Č�߂肵��
�����Ƃ���������L��܂��B���������āA����ɖl�̎v�����݂��]�ł���ꍇ
�����肤��Ǝv���܂��B���̓_�����܂݂������������B
����������������������������������������������������������������������������
�@�莝���̃G���N�g���b�N�M�^�[���{�̃R���g���[���L���r�e�B�[�ɓh���Ă݂�
�����B�A�`�\���Ђr�o�W�O�O��̓��d�h���ł��B�n�܃^�C�v�i��
�h����n������
�\��������̂ł͂ݏo���Ȃ��悤�v�����ł��j�ŁA�����͑����Z���ԁi��T���j
�Ŏ�ɂ��Ȃ��Ȃ�A��r�I�y����Ƃ͑����čs���܂��B���S�Ɋ����ɂ͂�����
���Ԃ��K�v�ł����A���[�J�[�����ɂ��܂��ƂQ�S���ԂƂȂ��Ă��܂��B�����
���\�邽�߂ɂ́A���S�������K�v�Ȃ悤�ł��B�e��e�X�g�͓h���Ă���Q�S
���Ԉȏソ���Ă���s�Ȃ��̂������ł��B
�@�O���m�C�Y�͂��Ȃ艟��������悤�ł��B�J�[�{���Ɣ�r���āA�����ʓI
�ȋC�����܂��B�f�B�X�g�[�V�������Ȃ��Ŏ����Ă݂Ă��S�̓I�Ȉ�ۂƂ���
�u�Â��v�ł��B�L���r�e�B�[�̃V�[���h�Ƃ��Ă͑�ϗǂ��Ǝv���܂����B
�@���͂ǂ��ł��傤���B�J�[�{���ɂ��V�[���h�̏ꍇ�A�l�ɂ���Ă͂���т�
���������Ȃ���Ƃ������z������邱�Ƃ��L��܂��B�����Ă݂�ƍ���̋�
�̓��d�h���ł����F�̕ω����L��悤�ł��B�������A���ꂪ�s�v�c�Ȃ�ł����A
�ڂ��ɂ͗ǂ������ɕς���ĕ�������̂ł��B
�@�܂��A�J�[�{�������ɓh���Ă������e���L���X�^�[�̏ꍇ�A�J�[�{���̎���
������ƕ�����Ȃ���ۂ��L��܂����B������܂�܂Ƃ܂��Ă���Ƃł�������
���傤���E�E�E�B���̃J�[�{���̏ォ���������h���Ă݂��킯�ł��B����
�Ă���e���Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƃ����܂����E�E���Ȃ₩�ɋ��������̉��ɕς����
�̂ł��E�E�E�\���ł��܂��E�E�E������Ȃ��͉����̕����ł��B
�@���ɃV�[���h������S�����Ă��Ȃ������N���C�}�[�̃A���~�l�b�N�i�V���O��
�R�C���j�̏ꍇ�B���X�Ɠ��̖\�ꂽ�����������Ďg���V�[�������肳�ꂻ���ȉ�
��������ł����A���h���Ă݂�Ƃ�͂�c���o�ĉ����ۂ��Ȃ��āA�C�����̗�
���܂Ƃ܂肪�L���āE�E�E�E
�@�J�[�{�������ɓh���Ă������X�g���g�̏ꍇ�B�ʔ����Ɍ�����Ƃ������A�܂�
�܂肷���Ă����ۂ��L��܂����B�s�b�N�A�b�v���̂������Ă���̂ł���̂�
�����ȂƎv���Ă��܂����B�ŁA���h���Ă݂�ƁE�E�Ȃɂ��L�т₩�ȋ������L��
�čD���Ȋ����ɂȂ��Ă���̂ł��B
�@���Y�^���[�J�[�̃G���N�g���b�N�P�Q���̏ꍇ�B�V�[���h�͂��Ă��Ȃ��āA
������Ƒ����������̉��B�����͂��قǗǂ��Ȃ��A�ʊ��̂Ȃ��̓{�f�B�̂�����
�Ǝv���Ă܂����B
�@��̓h����h���Ă݂�ƁA���_�����Ȃ�������ꂽ�悤�ɕ�������̂ł��B
���[�̓K�b�`���Ƃ��A����̔{�����Y��ɐL�тĂ�������Ɖ₩�Ȋ����ɂȂ�
�܂����B���肪���ĕ������ǂ��Ȃ����悤�ɂ��������܂��B
�@�ȏ�͖{���ɂ���Ɉ�ۂɉ߂��܂��v�����݂ŊԈ���Ă���̂��������
����B�C�̂�����������܂���B�傢�ɕs���ł��B
�@�����ŁA���i���痊��ɂ��Ă���F�l�ɓh���𑗂��Ď����Ă��炤���Ƃɂ���
�����B���̌��ʂ́H
�͂������[������̈��p�ł��B
�@�u�l�̂w�w�w�w�͓��d�h���ς݂ŃI�[�o�[���b�J�[���Ă���܂���
�@�@�͂������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���܂��B�ł�����A���̏�ɂ�����������
�@�@��h���Ă݂܂����B
�@�@���ʂƂ��ĉ������ǂ��Ȃ�܂����B�l�̊����Ƃ��܂��Ă�
�@�@���C�ŗ͋����Ȃ����C�����܂��B
�@�@�Ȃ�Ńn�b�L���Ƃ����悤�ɕ�������̂��s�v�c�Ȋ����ł��B�v
�@�l�Ɠ����悤�Ȉ�ۂȂ̂ł��B�S�������܂����B
�@�Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�l�Ƃ��Ă͊F����ɐ���Ƃ��ǎ������Ă������������̂�
���B
�V�[���h�ނƂ��Ẵm�C�Y�����͖��S�ł��B�J�[�{���ȏゾ�Ǝv���܂��B
�@���͋�̓��d�h����h�����Ƃ��A���F�̈�ۂ͂ǂ��ς��̂��A�����͕ς�
��Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃł��B
�@���̂Ƃ����̓��d�h���͏��ʂł͈�ʓI�ɓ��肪�����������܂���B
�L���r�e�B�[�ɓh��ʂ��l����ƃM�^�[��{������̋�̓h����͂���قǂ̋�
�z�ł͂���܂��A���i���̂��̂̓J�[�{���������Ȃ荂���ł��B�i
���P�j
�@�F����̃e�X�g���ʂ����҂����Ă��܂��B�X�������肢�������܂��B
�@�������F�ɕω����Ȃ������Ƃ��Ă��A�V�[���h�̓����̖ړI�ł���m�C�Y�h�~
�͒B�������Ǝv���܂��̂ŁA�����Ă݂Č����āu���v�͂��Ȃ��Ǝv���Ă܂��B
�@�l�������ăe�X�g���Ă������Ǝv���Ă܂��B�܂����ł���Ǝv���܂��B�i
���Q�j
�i���P�j�Ȃ�Ƃ��ȒP�Ɏ�ɓ������悤�ɂƍl���Ċe���ʂɂ��肢���܂����B
���̌��ʁA�q���[�}���E�M���Ŏ����I�Ɉ����Ă��炦�邱�ƂɂȂ�܂����B
���i�͌����ł̓J�[�{���̖�Q�O�{�̒l�i�Ȃ�ł����A���ʂȃP�[�X�Ƃ��āA
��r�I�����œ���\�ɂȂ�悤�Ɏ��v����Ă��炦�܂����B
�قڎ���i�����{���o��j�ł��B��h���Q�T���Ƃ��̗n�܂��Z�b�g�Ő���~���x
�ɂȂ�Ǝv���܂��B��h���Q�T���́A�L���r�e�B�[�̑傫���ɂ����܂����A��
�{�̃M�^�[�ɓh���ʂł��B���i�͂��̎��̋�̑���ŕϓ����܂��B�i����Ă�
���������̂�������ł��ˁj
�@�Ƃ肠�������ʌ���ł����A���v�ɉ����č�����l�������Ǝv���Ă܂��B
�@�ڂ����̓q���[�}���E�M���ɂ��₢���킹���������B
�@�@�q���[�}���E�M���@
http://www2.gol.com/users/yagi/
�@�@���[���A�h���X�@�@
yagi@gol.com
�@�@�s�d�k�@�@�@�@�@�@�O�R�[�T�S�T�O�[�U�P�V�W
�@�@�e�`�w�@�@�@�@�@�@�O�R�[�T�S�T�O�[�W�X�R�X
�i���Q�j���܂��̂��b�ł��B��̓��d�h���͒�R���Ⴍ�ƂĂ����肵�Ă��邽�߁A
�v�����g��̏C���Ɏg���邻���ł��B��Ă��܂����p�^�[�����Ȃ�����A
�ꕔ�p�^�[����ύX�������Ƃ��ȂǁA�ׂ��M�Ŋ�]�̃p�^�[�������������ł悢
�Ƃ��B���ہA�^���[�J�[�������s����������p�^�[���̏C���p�ɑ�ʂɔ����t
�������Ƃ������������ł��B
�@���̂ق��ɂ��A�l������낢�뗘�p���铹�����肻���ł��B�Q�`�R�̃A�C
�f�B�A������̂Ŏ����Ă݂����ł��B
(2003.01.25)
��back to top
�@
�t�B���K�[�s�b�N
�@�f���炵���t�B���K�[�s�b�N���������̂ł��m�点�������܂��B
Guptill Music��ProPik������ł��B
�w�Ɋ������������A�]�����炠��V���O���̂��̂ƁA�ӂ��ɕ����ꂽ
�X�v���b�g�^�C�v������܂��B�������̂̓X�v���b�g�^�C�v�̂��̂ł��B
�����ɒ��߂��Ȃ��Ă��t�B�b�g�������ɂ悭�A����������Ȃ��ł��B
�T���s�b�N����ς悢�ł��B
�f�ނ̓u���X�ƃj�b�P���V���o�[�̕��Ƃ�����܂��B�o���Ƃ��d�グ������
�悭�A�����ł��B���̓u���X�̂ق�����_�炩�߂ł��B
�@�T�C�Y��`��Ɋe�킠��A�S���łT�O��ނ��炢����悤�ł��B
���j�[�N�Ȃ͍̂ŋߔ��\���ꂽ���f���ŁAFinger Tone�Ƃ������̂ł��B
�w�̕����ł�悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��āA�����Ύw�Ń~���[�g���邱�Ƃ�
�ł���悤�ł��B
�@���i��$2.50�̂��̂��������A���̂ɂ����$3.50�̂��̂�����܂��B
�e�`�w�ŃI�[�_�[�������āA�P�T�Ԉȓ��ŕi�����͂��܂����B
���ς͂u�h�r�`�J�[�h�ł����Ȃ��܂����B���i��̑��ɃV�b�s���O��
�n���h�����O��$8.00�����Z����܂��B
�ڂ�����
http://www.guptillmusic.com/
��K�₵�Ă��������B
�Ȃ��A�ƂĂ��悭�������O��Propick�Ƃ����Ƃ��������܂��B���������^����
�s�b�N������Ă��܂����ʕ��ł��B�ς�����t���b�g�s�b�N������Ă��܂����A
�t�B���K�[�s�b�N�͂���܂���B�Ԉ��Ȃ��悤�ɁB
(2002.03.09)

��back to top
�@
����I�u���b�W�����ɂ��Ă̍l�@
�u���H�I�u���b�W�����i�����Łj�v���f�ڂ��܂����̂ŁA��������������������B
���H�I�u���b�W�����i�����Łj(2004.05.16)
��back to top
�@
���c�m�̂o�n�c�Q�f�[�^�@�ꕔ���J
�@���낢��ȕ�����u���c�m�̂o�n�c�Q�v�̃f�[�^�����J���ė~�����Ɨv������
�Ă��܂��B�l�Ƃ��Ă��G�f�B�b�g�̎Q�l�Ƃ��Č��J�������ƍl���Ă��܂����B
�������A����ړ��Ăɐ��i���w�����ꂽ��������������킯�ł����A���ׂĂ�
���J����Ƃ����킯�ɂ͎Q��܂���B�����ŁA�T�E���h�����R�[�f�B���O���Ƒ�
�k�������ʁA�l�̃G�f�B�b�g���@�̊�{�ƂȂ肻���Ȃ��̂S�v���O������������
�J���āA�Q�l�ɂ��Ă����������Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
�@������J����͎̂��̂S�v���O�����ł��B
�@������������i�̉���ڎw���Ƃ��������G�f�B�b�g�̃A�C�f�B�A���킩���
���������Ƃ����ϓ_�����������̂ł��B���ۂ̎g�p�ł̓v���Z�b�g�̉����̂�
�܂Ƃ������Ƃ͏��Ȃ��A���炩�̃G�f�B�b�g���{���Ǝv���܂����A���̎��ɎQ
�l�ɂȂ�Ƃ����C�����ł��B�ǂ̃p�����[�^�[���ǂ������ω����y�ڂ�������
���Ă���������ΐ����Ƃ�����ł��傤�B
�@�`�b�R�O�s�a�@�P�P�Q�@�@�@�@������ɂ�����Ɠ���������N���[���N�����`
�@�l�`�s�b�g�k�d�r�r�@�P�P�Q�@�O�҂��f�B�X�g�[�V�����ɋ߂��c��
�@�a�`�r�r�l�`�m�@�P�P�Q�@�@�@�ቹ���̘c�ݕ��������I
�@�i�s�l�S�T�@�P�P�Q�@�@�@�@�@�ቹ���̍r�ꂽ�c�ݕ���_���Ă݂܂���
| �g�p�X�s�[�J�[�@Vox Blue 112 |
|---|
| �@ |
Air�@ |
Drive |
Bass |
Mid�@ |
Tre�@ |
Pre�@ |
Vol�@ |
Boost |
Bright |
Dist |
Prese |
Comp |
| AC30TB�@ |
26 |
29 |
50 |
57 |
40 |
- |
63 |
- |
- |
- |
on |
2 |
| Matchless |
11 |
27 |
46 |
45 |
58 |
42 |
41 |
on |
- |
- |
on |
2 |
| Bassman |
35 |
38 |
39 |
38 |
47 |
8 |
43 |
on |
- |
- |
on |
3 |
| JTM45 |
15 |
59 |
35 |
49 |
36 |
32 |
30 |
on |
on |
- |
on |
2 |
��������������������������������������������
�@�ݒ�菇�@�@--- SoundDiver���K�v�ł��B---
���܂��A���v�^�C�v��I�����܂��B
�����ɃX�s�[�J�[��I�т܂��B
���`�h�q�l�����܂��B�ꉞ�l�͖̂ڈ����x�Ɨ������Ă��������B�g�p����
�����Ē������Ă��������B
���d�p��c�q�h�u�d��u�n�k�͎g�p�M�^�[�ɂ��킹�Ă��D�݂Œ������Ă��������B
���o�q�d�r�d�m�b�d�̃X�C�b�`�͂���̃p�����[�^���Ȃ��Ă��n�m�ɂ��Ă��܂��B
����ʼn��F���ς��悤�Ɋ����Ă��܂��B
���R���v���l�̒��ł͕K�{���ڂł��B���̃p�����[�^�[�Ƃ̊W�������Ƃ��Ē���
��Ί������ł��B
�����i�ł͂��̕\�ȊO�̃p�����[�^���ݒ肵�Ă��܂����A���ɂ��킹�Đݒ肵��
���������B
�@
�@�o�n�c�Q�ō��܂����̂ło�n�c�P�œ����ɂȂ邩�ǂ����s���ł��B
�@�ȑO�ɏ����܂������|�[�g���Q�Ƃ��Ă���������ƍK���ł��B
�@���ӌ������z�@���҂����Ă��܂��B
(2002.01.22)
��back to top
�@
War Resisters League�̐����Ɖ��y�W���[�i���X�g����̃��|�[�g
����̃e���Ɋւ��āA������ꎁ���A�T�q�̉p���V���̕����瑗��ꂽ�j���[�X�ƁA
���鉹�y�W���[�i���X�g����̃��|�[�g���A�]�����Ă���܂����B���������������
�Ƃ��낪�������e�ł��B
�F����Ɍ�ǂ݂���������K���ł��B
�i�]�ڋ����Ă���܂��j
(2001.09.18)
����������������������������������������������������������������������
�@�č��ւ́u�e�����Y���v�ɂ��āA�č��̔�\�͕��a��`��NGO�A�푈��R�ҘA��
�iWar Resisters League�j���������o���܂����B�ȉ������ٖ̐�ł��B
�N�����F
�푈��R�ҘA���iWar Resisters League�j�̐���
�Q�O�O�P�N�X���P�P��
�j���[���[�N
�@�킽������������������Ă��邢�܁A�}���n�b�^���͕�͍U�����Ă���悤��
��������B���ׂĂ̋��A�g���l���A�n���S��������A����l�A�����l���̐l�X��
�}���n�b�^���암����k�ւ����������Ă���B�����푈��R�ҘA���̎������ɂ����
�Ă��āA�킽���������܂��z�����Ƃ́A���E�f�ՃZ���^�[�̕���Ŗ��𗎂Ƃ�������
�l���̃j���[���[�J�[�̂��Ƃł���B�V�C�͉����ŁA��͐��B�������A����̉���
���I�̎R�̒��ł��т����������̐l�X�����B���̒��ɂ́A�r���̕���̂Ƃ�����
��ɂ����������̋~�}�������܂܂�Ă���B
�@�������킽�������́A���V���g���̗F�l�E�����������A�y���^�S���ɃW�F�b�g�@
���˓������Ƃ��Ɋ����Y���ɂȂ�����ʎs���ɂ��đz���Ă��邱�Ƃ�m���Ă���B
�����Ă킽�������́A���̓��n�C�W���b�N���ꂽ��s�@�ɏ���Ă������̍߂��Ȃ���
�q�����̂��Ƃ�z���Ă���B�����_�ŁA�킽�������͂ǂ�����U���������̂��킩��
�Ȃ��B
�@�킽�������́A���T�[�E�A���t�@�g���U����������Ƃ͒m���Ă���B�����Ə�
����܂ŁA�ڂ������͍͂����T���邪�A����������̂��Ƃ͖��炩�ł���B�u�b
�V�������̓X�^�[�E�E�H�[�Y�v��ɖc��Ȏx�o�����邱�Ƃ��c�_���Ă��邪�A���ꂪ
�ŏ�����ł���߂ł��邱�Ƃ͂͂����肵�Ă���B�e�����Y���͂����Ƃ���ӂꂽ��
�i�ł���Ȃɂ��₷���U�����邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�@�킽�������́A���O���c��ƃu�b�V���哝�̂ɑ��āA���̂��Ƃ����߂�B���ꂩ
��č����ǂ̂悤�ȑΉ�������ɂ��Ă��A�č��͈�ʎs�����^�[�Q�b�g�ɂ��邱�Ƃ�
���Ȃ����ƁB��ʎs�����^�[�Q�b�g�ɂ��鐭��������Ȃ鍑�̂��̂ł���F�߂Ȃ���
�ƁB�����̂��Ƃ��͂�����F�߂Ăق����B���̂��Ƃ́A�C���N�ɑ��鐧�ل�����
���l���̈�ʎs���̎��������炵�Ă��鄟������߂邱�Ƃ��Ӗ�����ł��낤�B����
���Ƃ͂܂��A�p���X�`�i�l�ɂ��e�����Y���݂̂Ȃ炸�A�C�X���G���ɂ��p���X�`
�i�l�w���҂̈ÎE��A�C�X���G���ɂ��p���X�`�i�Z���ɑ���}���A���݂���уK
�U�n��̐�̂����邱�Ƃ��Ӗ�����ł��낤�B
�@�č����Nj����Ă����R����`�̐���́A���S�����̎��������炵���B����́A�C��
�h�V�i�푈�̔ߌ�����A���Ă���уR�����r�A�̈ÎE�����ւ̍��������A�����ăC��
�N�ɑ��鐧�ق�ȂǂɎ���B�č��͐��E�ő�́u�ʏ핺��v�������ł���B��
�����������镺��́A�C���h�l�V�A����A�t���J�܂ŁA�ł��������e�����Y��������
���Ă���B�A�t�K�j�X�^���ɂ����镐�͒�R���x�������č��̐��A���ǁA�^���o
���̏����ƃI�T�}�E�r���E���f�B�������肾�����̂ł���B
�@���̏����������悤�Ȑ�����Ƃ��Ă����B�킽�������́A����܂ŁA�`�F�`�F����
�����郍�V�A���{�̍s����A��������уo���J���ɂ����镴�������҂̑o���̖\�͂�
�ǂ���Ă����B�������A�č��͎��Ȃ̍s���ɐӔC���Ƃ�ׂ��ł���B����������
�܂ŁA�킽�������͍������ň��S���Ǝv���Ă����B�����̓��A���N���Ă݂āA�č���
�ő�̓s�s����͍U������Ă���̂�m���āA�킽�������́A�\�͓I�Ȑ��E�ɂ�����
�͒N�ЂƂ���S�ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��v���N�������B���\�N���̊ԁA�č����Ƃ炦
�Ă����R����`���A���܂����I��点��ׂ��ł���B
�@�킽�������́A�R�g�ƕɂ���Ăł͂Ȃ��A�R�k�A���ۋ��́A�Љ�`�ɂ����
���S���ۏႳ���悤�Ȑ��E���߂����ׂ��ł���B�킽�������́A���傤�N�����悤
�ȁA����l���̈�ʎs�����^�[�Q�b�g�ɂ���U���������Ȃ闯�ۂ��Ȃ��ɔ���B
�������Ȃ���A���̂悤�Ȕߌ��́A�č��̐������̈�ʎs���ɑ��ė^���Ă���
�C���p�N�g��z�N��������̂ł���B�킽�������͂܂��A�č��ɏZ�ރA���u�n�̐l�X
�֓G�ӂ������邱�Ƃ���A������`�Ԃ̕Ό��ɔ����Ă����č��l�̂悫�`��
���v���N�����悤���߂�B
�@�킽�������͂ЂƂ̐��E�ł���B�킽�������́A�s���Ƌ��|�ɂ��т��ĕ�炷��
���A����Ƃ��\�͂ɑ��镽�a�I�ȃI���^�i�e�B���Ɛ��E�̎����̂������ȕ��z��
�߂����̂��B�킽�������͎���ꂽ�����̐l�X�𓉂ށB���A�킽�������̐S�����߂�
����̂́A���Q�ł͂Ȃ��a���ł���B
��������������
�@����͐푈��R�ҘA���̌����̐����ł͂Ȃ����A�ߌ����N��������ɏ����ꂽ�B��
����R�ҘA���̑S�������ǂ̃X�^�b�t�Ǝ��s�ψ���̃����o�[���������āA���\����
��B
�Q�O�O�P�N�X���P�P��
asif ullah
Carmen Trotta
Chris Ney
David McReynolds
Joanne Sheehan
Judith Mahoney Pasternak
Melissa Jameson
�i�N�����F��j
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�m�l�E�F�l�̊F���܁A���y�W�҂̊F����
��T�j���[���[�N�ŋN�������������������ɁA���ANYC�̒n���̃A�[�`�X�g�B�͐푈
�̖u�����ƂĂ��S�z���Ă��܂��B���n�̐l�X�ɂƂ��Ă̓e���ɑ���{������A�A
�����J����������������ɐ푈�Ɍ��������Ƃ���������Ă��܂��B�ނ�͍��A�u�ǂ�
���푈�����͋N�����Ȃ��ł��������v�ƁA�z���C�g�n�E�X�̐l�X��c���̐l�X�ɁA���[
���ŒQ�肵�Ă��܂��B���{�̊F���܂��A�ǂ����A���L�̃A�h���X�ɁA�uPlease don't
go to war!�v�̈ꌾ�����ł����܂��܂���B�푈���������Q��̃��b�Z�[�W�𑗂�
�Ă�����������K���ł��B
president@whitehouse.gov
vice.president@whitehouse.gov
senator@schumer.senate.gov
senator@clinton.senate.gov
senate@mailbot.com
house@mailbot.com
first.lady@whitehouse.gov
��Ў҂ł���}���n�b�^���̐l�X�́A�e���ւ̕��߂��݂̉������Ƃ͎v���Ă���
����BBush���A���u�����ɎӍ߂��Ăł���������A�ߋ��̃A�����J�̔��F�߂Ăł��A
�푈��������Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�ǂ����A���̔ߌ����N����O�ɁA���{�����
�ł��邾�������̕��X����̃��b�Z�[�W�𑗂��Ă�����������Ɗ肢�܂��B
���̎����̂��߂ɁA����A�j���[���[�N�i���ɃW���Y�N���u���W������_�E���_�E��
�n��j�̉��y�V�[����������Ă��܂����Ƃ��A�ƂĂ��S�z���Ă��܂��B���łɁA�q��
�@�̖��Ńc�A�[�̒��~��R���T�[�g�E�t�F�X�e�B�o���̒��~�A�O���ւ̂b�c�A�o��
���̐����ȂǁA�~���[�W�V�����̐����ɂ��e�����o�Ă��܂��B�������A�ނ炪����
�Ԉ����Ă����v�s�b�����̂悤�Ȍ`�Ŕj��A���������ƂɁA�[���߂��݂��o����
���܂��B
����͂���ɁA�ό��q�̌����ɂ��A�}���n�b�^���̃W���Y�N���u�̒���Ȃǂ��\�z
����܂��B
����Q�C�R�N�͋ꂵ���Ȃ�ł��낤�j���[���[�N�̃~���[�W�V�����B�̊�����������
���x���ł���悤�ȁu�A�[�`�X�g����v�̂悤�ȕ���������A�ډ���悵�Ă��܂��B
���̍ۂɂ́A���{�̃W���Y�G���e���A����у��W�I�Ȃǃ��f�B�A�̕��X�ɂ��A���ЁA
�ǎ҂�X�i�[�̕��X�ɌĂт����Ă�����������Ǝv���܂��B
NYC�̃~���[�W�V�����B���疈���A�߂��݂̃��[�����͂��A�S��ɂ߂Ă��܂��B�ǂ�
���A�ނ�̐S�ɍĂѕ��a���߂���������K���悤�A�F���܂�����F���Ă���������
��Ǝv���܂��B
���y�W���[�i���X�g
���ԗT�q
������������������������������������������������������������������������
������ꂳ��̃T�C�g�w���y�Ȃ�Ɋy�x�͂����灨
http://www.makigami.com/
��back to top
�@
�n���_�@����Ȃ���
�ȑO�\�����܂����n���_�e�X�g�̒��ԕł��B
�n���_�ɂ�鉹�F�̍����e�X�g����Ƃ����Ă��Ȃ��Ȃ���ؓ�ł͂����܂���B
�ǂ����̃n���_���������Ă��A���F�̍��͋L�������ɗ��邱�ƂɂȂ肪���ł��B
�܂��ǂ��n���_���g�����Ƃ����v�����݂����f����点�邱�Ƃ����邩��
����܂���B�����`�Ɏc����悢�̂ł����E�E�E
�Ƃ����킯�ŁA�l�������Ƃ��M������}�X�^�����O�G���W�j�A�A
�\�j�[�E�~���[�W�b�N�E�G���^�e�C�������g�̓c������ɋ��͂����肢���܂����B
�c������ɂ͂������낢�닳���Ă��������Ă��āA�l�̎t���̂悤�ȑ��݂ł��B
�ܘ_�}�X�^�����O�œ��{�̑��l�҂ł��B
����l���p�ӂ����̂͂S��ނł��B����ƃ\�j�[�E�~���[�W�b�N�E�G���^�e�C��
�����g�ŏ��L���Ă����S��ށA���킹�ĂW��ނ̃n���_�̃e�X�g�ɂȂ�܂����B
�e�X�g�Ɏg�p�����n���_
�@�@�A���~�b�g�P
�@�@�A���~�b�g�Q
�@�@�A���~�b�g�R�i�ԍ��͖l������ɂ������̂ł��B�g���䗦���قȂ��Ă܂��j
�@�@�J���_�X
�@�@�Z���W�����^��
�@�@�q���[�}���M��
�@�@�����_�[�\���_�[
�@�@�v�a�s
�e�X�g���@�͓c������̃}�X�^�����O�p�@�ނ�����ł���P�[�u���̂�����
�P�ӏ������낢��ȃn���_�Ŏ����Ƃ������̂ł��B
�}�X�^�[���R�[�_�[����e��@�ނ��o�Ăt�}�`�b�N�̃��R�[�_�[�ɓ���킯�ł����A
���̂����̂P�ӏ������Ńe�X�g���Ă݂悤�Ƃ����킯�ł��B
�܂��A����P��ނ̃n���_�Ńn���_�t�����āA���R�[�_�[�����A���Ԃ�����
��~�߂āA�n���_���z������ĕʂ̃n���_�ł������āA�܂����R�[�_�[��
���āE�E�E�Ƃ����J��Ԃ��łW��ނ��L�^����܂����B�����Ȃ��W��^�������
���邱�ƂɂȂ�܂��B
�e�X�g����͂��ׂēc�������l�ōs���܂����B�߂�ǂ������e�X�g��������
���Ă��������Ċ��ӊ����ł��B
���̌�t�}�`�b�N���Đ����ăn���_�ɂ�鉹�̍����`�F�b�N�ł��B�`�Ƃ��Ďc��
�Ă���̂ʼn��x�ł������Ȃ����邵�A�ςȐ���ς����@�ł��āA�e�X�g�Ƃ��Ă�
�Ȃ��Ȃ��ǂ����̂��Ǝv���Ă��܂��B
���ܖl�̂Ƃ���ɂ��ꂩ�������b�c������܂��B���ʂ́E�E�����܂����B
���̈Ⴂ�͂Ȃ�ƕ\�����ėǂ��̂ł��傤�B�t���[�Y�̐����͂┧�G��Ƃ�����
�悤�Ȃ��̂�����ĕ�������̂ł��B�����ɕ��ʂ̐l����v���܂ŁA���l���̐l
�ɕ����Ă��炢�܂����B�F���ꂼ��̌��t�ňႢ��������Ă���܂��B
�u�L���L�����Ă���v�u�ǂ����肵�Ă���v�u�y��̃o�����X�����ꂼ��ň�
�Ȃ��ĕ�������v�u���[�̐L�т������˂��v�u���������ł܂�Ȃ����v�u�N��
���[�œ�����������v�u������Ƃق����Ȃ��v�u���������ĉ���������v�u����
���Ɠ������x���H����������������Ȃ��v�ȂǂȂǁE�E�E
�ǂꂪ�ǂ��Ƃ������Ƃ͂����ł͏�����������܂���B�܂��������̏�Ԃ�����
�ł��B�e�n���_�̉��F�ɂ�������ӌ��Ɉ��̌X�������邱�Ƃ͖����Ȃ�ł����A
����������Ǝ��Ԃ����������B�܂��܂Ƃ߂���Ă��܂���B
�������A�l�Ɠc������Ƃ̊Ԃł́u�]�܂������̃n���_�v�̖ڐ��������C����
�Ă܂��B�c������ɂ͓��ɍD�݂ɂ������n���_������悤�ŁA�V��̃e�X�g�b�c
�ł̓P�[�u���T�{���P�O�ӏ��̃n���_������ɂ��ă}�X�^�����O�������̂���
�^����Ă��܂��B�������ǂ��ł��B
�u�n���_�@����Ȃ���v�ł��B�n���_�ɂ�鉹�̍��@���͑������肻���ȕ���
�C�ł��B
�����Ă��������Ȃ��̂��{���Ɏc�O�ł��B���������E�E�E
�܂����|�[�g�������Ǝv���Ă܂��B�������������ĕł���悤�ɂ����܂��B
�i�e�X�g���s���A���������ҁj
(2001.08.26)
��back to top
�@
�ꂽ�o�t���C������
�Ƃ��ǂ��ꂽ�o�t�ɂ��Ď���������܂��B
�X�g���g�^�C�v���ɂƂ��āA����I�ȏC�����@���q�ׂĂ݂܂��B
�ȉ��̕��@���x�X�g�ł��邩�ǂ����́A�킩��܂���B���A�������̐ꂽ
�o�t���C�����āA���܂��ɖ�肪�Ȃ��Ƃ��������ƁA���\�����Ă�̂��Ȃ�
�v���Ă܂��B
�f�����C������ƌ����Ă��R�C���̒��Ő�Ă�����̂̓v���ɏC����C����
���傤�B�Â�����̒m�l�ł���^�o�t���[�J�[�̌������ł��A�܂��������t
�t���Ă��܂��B��ʓI�ɂ̓��y�A�V���b�v�Ɉ˗����āA�������炵����ׂ��Ƃ�
��ɑ����Ă܂��������Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�o�t�f���ɑ������Ă������Ȃ��Ƃ́A�����čQ�ĂȂ����Ƃł��B�Q�Ă��
�������L�������ł��B
�l�̌o���ł́A�f���͂����Ă��n���_�t��������n�g���̎��ӂŋN�����Ă��܂��B
�R�C���̒��̒f���ɑ�������̂͂܂�ł��B���S�ɉ����łȂ��Ƃ��̓n�g������
���^���Ă��������B�R�C���Ȃ��ł̒f���́A���V�e�ʂ���āA���[�̂Ȃ��J��
�J���ȉ����o�邱�Ƃ������ł��B
���[�h����ʂ̂��̂Ɏ��ւ��悤�Ƃ��ăn���_�t������ƁA�n�g���̎��ӂŐ�
���ꍇ������܂��B�ǂ����A�M�ł�������c�����������A�₦��ɂ���������
���k����Ƃ��ɐ��悤�ł��B���̏ꍇ�n���_�t������̃`�F�b�N�ł͖��Ȃ�
�̂ɁA���炭���Ċ��S�ɗ₦����ƒf�����Ă���Ƃ����A���҂ł��B
�����ؒf�ӏ����m�F���遖��
�f���s�b�N�A�b�v�́A�܂��ǂ̕ӂ���Ă��邩�m�F���܂��B
�Q�̃n�g���̎��ӂ��悭����ƍׂ������R�C���̕����炫�Ă���̂��������
�v���܂��B���̂ǂ��炩�����X�I�ɑI��ŁA�J�b�^�[�̐n��ł����Ɛ��̏�
�Ɋ|�����Ă��郏�b�N�X����菜���܂��B���̈ꕔ���I�o������A����ɃJ�b�^�[
�̐n��ŃG�i�����₻�̑��̔핢���͂����܂��B����͐��̂����ꕔ�����ʂ�
�����ԂɂȂ�悢�̂ŁA�����ł����̒n�������������łn�j�ł��B����
�����ɂQ�{�̃e�X�^�[�_�Ăē��ʂ����Ĕ핢���͂���Ă��邱�Ƃ��m�F���܂��B
���ɂ��̕����ƃn�g���̊Ԃ̓��ʂ����܂��B���ʂ���������瑤�̐��͂n�j
�ł��B�������ʂ��Ȃ�������A�������f�����Ă���킯�ł��ˁB
����ɂ��̂͂����������Ɣ��Α��̃n�g���̊Ԃ̓��ʂ��`�F�b�N���܂��B�����
�R�C���̒�R�l�������A�f���͂����瑤�̈�ӏ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
����������ʂ��Ȃ���A�O�̂��߂�����x���ʃe�X�g���ŏ������蒼���܂��B
�J�b�^�[�ł͂����������ւ̃e�X�^�[�_�̓��ĕ����ǂ��Ȃ��̂�������Ȃ�����
�ł��B���邢�̓n�g���Ƀ��b�N�X���������Ă���̂�������܂���B���̂���
��𒍈ӂ�������x�e�X�g���Ă��������B
��͂藼���Ƃ����ʂ��Ȃ��ꍇ�A�����Е��̃R�C�����炫�Ă�������A��قǂ�
�����悤�ɃJ�b�^�[�̐n��ŏ������܂��B
���ʃe�X�g����قǂƓ����菇�ł��B�͂����������ǂ����ł̓��ʃe�X�g�ŁA
����̒�R�l���������Ƃ��m�F���Ă��������B���������T�j�I�[������V.�T�j�I�[��
�̊Ԃł��傤�B�i�N���o�t�ʒu�ɂ���Ă��낢�날��܂��j
�͂����������ƃn�g���ł͓��ʂ������āA�͂����������ǂ����œ��ʂ��Ȃ��Ƃ��A
����́A����Ɠ�������i�R�C���̒��Ƃ��j�Ő�Ă��鋰�ꂪ����܂��B
�ǂ����Ă�������g�������Ƃ��͂����̃��y�A�V���b�v�ɑ��k���Ă݂Ă��������B
�����C�����遖��
�ؒf���m�F���ꂽ���̃n�g������z���ƃn���_����菜���܂��B�n���_�z������
��\���_�[�E�B�b�N�Ȃǂ����܂��g���Ă��������B�n�g���̌����ђʂ���悢
�̂Ńn���_�����X�c���Ă��Ă����Ȃ��ł��B
���Ƀn�g���̌���ʂ��čׂ��������������܂��B
������r����̒��g�ׂ̍����Ȃ����p�ł��܂��B����������]����
�����͐�Ȃ��ł����āA�n�g���Ƀn���_�t�������܂��B
���̗]�����������قǔ핢���͂����������ɂ����Ƃ̂��āA�ʒu�W���m�F
���܂��B���̕����ɂ��炩���߃n���_���b�L�����܂��B
�핢���͂����������ɂ��n���_���b�L�����܂��B�܂����Ԃb�N�X�̒��ɖ��v
���Ă��܂��Ǝv���܂��̂ŁA�₦�Ă���A�ŏ��ɂ�����悤�ɃJ�b�^�[�̐n���
���b�N�X����菜���ăn���_���b�L����I�o�����Ă����܂��B
�����n���_�t������
�n���_���b�L�����Ƃ���ǂ������d�˂Ē������m�F������]���Ȑ��͐��č��
�����₷�����܂��B����͌�Ő��Ă��ܘ_�n�j�ł��B�v����ɂ��₷����
���ɂ���Ă��������B
�n���_���b�L�����Ƃ�����d�˂Ă����ăn���_���ĂĂ܂��B
�\���₦�Ă���e�X�^�[�œ��ʂ��m�F���܂��傤�B
�n�j��������z�����n�g���Ƀn���_�t�����܂��B
���̌�ɂ��A���x�͔z���̐�[�œ��ʃe�X�g���āA����̒�R�l���m�F���Ă��������B
�����ŏI�m�F����
�z�������ɖ߂��ăM�^�[�ɑg�ݍ��݁A�����m�F���܂��傤�B
���Ƃǂ���ɂȂ��Ă�����A�߂ł����E�߂ł���
(2001.06.03)
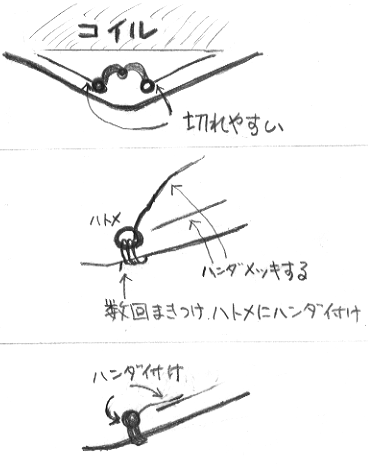
��back to top
�@
�M�^�[�����̔z���Q
�@�t�r�`�ɔ������Ă����⃀�N���ƃR���f���T�[�A�n���_���͂��܂����B
�@�⃀�N���͂b�`�q�c�`�r�А��łQ�O�����ł��B����Ƀe�t�����̐≏
�`���[�u�����Ԃ��Ďg���܂��B�����M�^�[�̍ŏI�A�E�g�̔z���Ńe�X�g���Ă�
�܂����B
�@���ʂ͂ƂĂ��悢�ł��B�ȑO���ʂ��ǂ�������b�L���Ƃ̔�r�ł́A�n�C
�G���h�A���[�G���h�͎��Ă��܂����A������̏[�������Ⴂ�܂��B����̂b�`
�q�c�`�r�̕����c�����������܂��B�����̃M�^�[�Ŏ����܂������A���̌X����
�ς��Ȃ��悤�ł��B
�@�P�̂Ŏg�p����ꍇ�̌X���͂킩��܂����̂ŁA���Ƀp�������������Ă݂�
�����B����͈�ؓ�ł͍s���Ȃ��悤�ł��B�e���L���X�^�[�ŋ�b�L���ƃp
���ɂ��Ă݂܂����B�����͂Ȃ�̂ł����A�����f���łȂ��Ȃ����C�����Ă܂�
�⃀�N�������ɂ��܂����B�M�u�\���E�u���[�X�z�[�N�ł͋�b�L���Ƃ̃p��
�������ǂ������ł��B
�@�X�̃M�^�[�ɂ���đg�ݍ��킹���l����K�v���L�肻���ł��B�g�ݍ��킹
�̐��͖c��ɂȂ�܂��̂ŁA������x�X�����i�荞�܂Ȃ���Ύ��E�����Ȃ�
��������܂���B
�@�M�^�[�ɋ⃀�N�����g�p������ԂŁA�R���f���T�[�̃e�X�g�����Ă݂܂����B
����w�������R���f���T�[�́A�����I�[�f�B�I�p�[�c������ɂ���u�����h�i�H
�T��ނł��B�e�ʂ͂������0.02�t�߂̕��ł��B
RELIABLE TFT�@�@ Exotica Teflon & Tin Foil
RELIABLE RTX�@�@ MultiCap Film & Foil Polystyrene
RELIABLE RT�@�@�@Polystyrene & Tin Foil
WONDERCAP�@�@�@�@Polystyrene Film & Foil
HOVLAND MUSICAP�@Film &Alminum Foil Polypropylene
�ł��B
�@�ʔ������ƂɁA�⃀�N�����g�p���Ă���Ƃ���ʼn������܂��Ă��܂�����
�������悤�ŁA�R���f���T�[�ɂ�鉹�̕ω��̊��������Ȃ��Ȃ�����ۂ���
��܂��B�����̂Ƃ��̂悤�ȁA�R���f���T�[��������ƃK���b�ƈ�ۂ��ς�
��Ƃ������Ƃ����܂肠��܂���B����ł������̍��͂���܂��̂Ŗʔ���
�ł��B
�@�ł����A���̃N���X�ɂȂ�Ƃ��ꂼ��D����������A����ɍD�݂̖��
�Ȃ̂��ȂƂ��������ł��B
�@���̂Ȃ��ł͂q�s�w��������D�݂ł����B���i�I�ɂ��[���ł�����̂�
�Ǝv���܂��B�i�q�s�w�́��T�`�U���炢�ł��j
�@���ɂ��n���_���R��ލw�����܂������A����̃e�X�g�͂��Ȃ����ł��B
���Ȃ莞�Ԃ������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����ɂ͌��_���o���܂���B
CARDAS Solder
Wonder Solder
WBT�@�@Solder
���A����p�ӂ������̂ł��B
�@�⃀�N���ƃR���f���T�[�̃e�X�g�ł͂v�a�s�А����g�p���Ă��܂��B��
�̂��̂����������e�X�g���āA�܂��������ł��B
�@�����I�ɍ���̓����z���Ŕ��ɖ����ł��镨�ɂȂ��Ă܂��B
�܂�����ɕʂ̂̃M�^�[�ł������Ă݂����ł��B
�w�������Ƃ���FMichael Percy Audio
�@�@�@�@�@�@�@�@
http://www.percyaudio.com/
(2001.04.14)
��back to top
�@
�T�E���h�A���h���R�[�f�B���O
���c�m�̂o�n�c�Q�Ɋւ���
��̃R�����g
���������̂�
�u�n�w�X�s�[�J�[�łW��@�}�[�V�����X�s�[�J�[�łW��@�v�P�U�ł��B
�����������̉�����遖����
�@���̒��ɖ��@�ƌĂ��A���v�͂�������܂��B�����āA�L���v���C���[����
�����@���g���Ĕނ�̃T�E���h������Ă����܂����B�������A�ނ�̃A���v������
���ăX�g�b�N��Ԃł͂Ȃ��A�J�X�^���ł��������Ƃ͂��܂�m���Ă��܂���B
�@�Ⴆ�U�X�N����̃W�~�w�����}�[�V�������g�p�����̂͗ǂ��m���Ă��āA����
�̓X�[�p�[���[�h�P�O�O�ƃx�[�X�p�̃L���r�ł������ƌ����Ă��܂��B�ł͂����
�̓��[�J�[�����삵���X�g�b�N��Ԃ̂��̂ł��������Ƃ����ƁA�����ł͂���܂���B
�����܂ŃW�~�w���̊�]���鉹���ł�悤�ɉ������ꂽ���̂Ȃ̂ł��B
�@�o�͊ǂ͂d�k�R�S����A�ꕔ�A�����J�d�l�Ŏg���Ă����A�U�T�T�O�Ɍ��������
�����B�W�~�w���͂��̃`���[�u���ƂĂ��D���������炵���A�f���A���V���[�}������
��ɑւ��Ă��������ł��B�T�E���h�͂��n�[�h�ŃN���[���Ȃ��̂ɂȂ��������ł��B
�@�{�g���Ɋւ��Ă̓x�[�X�p�̃L���r�ł��������ǂ����肩�ł͂���܂���B����
�}�[�V�������������Ƃ����͊m���ŁA�X�s�[�J�[���j�b�g�͂u�n�w�̃X�[�p�[�r�[�g
���Ɏg���Ă����Z���b�V�����ɂ킴�킴�t���ւ��Ă��������ł��B������̂ق���
���D�݂ɂ����Ă����̂ł��傤�B
�@�܂��A�ق��̗�ł́A�G���b�N�N���v�g�����u���[�X�u���C�J�[�Y����ɁA�S�T
���b�g�̃}�[�V�����P�X�U�Q�i�Q�w�P�Q�j�r���g�C���A���v���g�p���Ă����̂͗L��
�ł��B�������A������J�X�^���d�l�Ȃ̂ł��B�p���[�ǂ��j�s�U�U�ɑւ��āA����
�����ꂽ�~�b�h�����W�ƃN�����[�ȃg�b�v�G���h�Ă����ƌ����Ă��܂��B
�@���̂悤�Ɏ����̉��y�ɂ��킹�ăA���v���`���[�j���O���Ď������g�̉�������
�����̂́A�����Ă݂�Γ��R�̂��Ƃ����m��܂���B�ł����A���ۂ̃A���v��������
�ƂȂ�Ƃ��܂��܂ȍ���t���܂Ƃ��܂��B���̂k�h�m�d�U�o�n�c�Q�ł͎��ۂ̃A��
�v���݂Ƃ͂����܂��A������x�̃J�X�^�}�C�Y���\�ł��B���������@�[�`����
�Ȃ̂ł�����Ɗ�Ȃ��Z�b�e�B���O�ł����S���Ď��s���邱�Ƃ��o���܂��B
�������u�n�w�@�P�w�P�Q��炷������
�@����̂ЂƂ߂̃v���O�����O���[�v�͑ϓ��͂̏������X�s�[�J�[���ق��̃w�b�h
�ł���炻���Ƃ������̂ł��B���ڂ����͖̂{���u�n�w�̂`�b�P�T�Ƒg�ݍ���
����Ă���Z���b�V�����̂f�P�Q�ł��B�U�O�N��Ə�����Ă��܂��̂ŁA�����炭�u
���[�̂P�T���b�g���̓^�C�v���Ǝv���܂��B
�@�`�b�P�T�͍ŏ��O�b�h�}���̃X�s�[�J�[���g���Ă����̂ł����A�r������Z���b
�V���������ڂ����悤�ɂȂ�A�U�O�N��͂u�n�w�p�Ƀ`���[�����ꂽ���̒ʏ́u�u
���[�v���g���Ă����Ǝv���܂��B���̃X�s�[�J�[�͖����ȍ��ϓ��͂̎�@���Ƃ��
�Ă��Ȃ����ߔ\�����ǂ��A�����f���炵�����̂��Ǝv���Ă��܂��B�������ϓ��͂���
�قnj����܂����悤�ɂP�T���b�g�ƒ�߂Ȃ̂ł��B
�@�l���������͈͂ł́A��̃p���[��������ɂȂ��Ă���̃X�s�[�J�[�͂Ƃ���
�u���v�����u�ƂȂ����Ɓv���ŗD��ɂ��ꂽ�悤�ȋC�����āA�ǂ����D���ɂȂ�
�܂���B�A���v�̏o�͂������o�͂ɂ�����������M�ɕς��Ď̂ĂĂ���̂ł͂Ȃ�
���A�ƁA�v���Ă��܂��̂ł��B�Z���b�V�����ł͂��������R�O���b�g���́i��{�ɂ�
]���j���炢�܂ł̂������������Ǝv����ł����ǁE�E�E
�@�P�T���b�g���͂̂f�P�Q�ꔭ�������ȃA���v�Ŗ炵�Ă݂悤�A�����Ɨǂ�����
����ɈႢ�Ȃ��ƍl����킯�Ȃ�ł����A���ۂ̃A���v�ł͂��ƂԂ��т��т�����
����炳�Ȃ���Ȃ�܂���B���̓_����͑S�����S�ł��B�X�s�[�J�[���u�Ƃԁv
�S�z�͊F���Ȃ�ł�����B
�������}�[�V�����@�S�w�P�Q��炷������
�@�Z�p���[�g�^�C�v�̃w�b�h�Ń}�[�V�����̃{�g����炷�̂́A�悭�s���Ă���
��@�ł��B���������ӂ��߂̃v���O�����O���[�v�́A�R���{�^�C�v�̃w�b�h�ł�
�������Ă݂悤�Ƃ������̂ł��B�X�^�W�I�ł̘^���ł͂���قǒ��������Ƃł͂�
���̂ł����A�o�n�c��łǂ��Ȃ�̂�����Ă݂܂����B
�@�l�̍D�݂ŃR���{�^�C�v�ł͂Ȃ����̂��܂܂�Ă܂�����ڂɌ��Ă��������B�{�g
���̃Z���b�V�������B���e�[�W�R�O�͍ŋ߂̊y��p�X�s�[�J�[�̒��ł͂ƂĂ��悭�o
���Ă���ƒ�]������܂��B�I�[���h�̂f�P�Q���ƂĂ��悭�ӎ����Ă��āA���B��
�e�[�W�̖��ɒp���Ȃ����̂��Ǝv���܂��B
�������N�����`����f�B�X�g�[�V�����܂Ł�����
�@���͂�����ƃN�����`���炢����f�B�X�g�[�V�����܂łł��B�S���̃N���[���͎g
�p�y��Ƃ̃}�b�`���O���d�v�Ɏv���܂��̂ŁA����͂��܂����Ă���܂���B�v��
�O�����̏�ł̗v�_�͂`�h�q�̗ʂ����[�J�[�v���Z�b�g��茸�炵�Ă���Ƃ�������
�ł��B
�@���[�J�[�Ƃ��Ă͂`�h�q�̌��ʂ�F�����Ăق����Ǝv���Ă���̂����m��܂���B
�l�͑S�̂ɑ��߂Ɋ����Ă��܂��܂��B�y�Ȃ�A�����W����Ƃ����Ƃ��������̂ł�
���A�`�h�q�ō����u���h�ȁv�ቹ���ז��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����邩��ł��B�M
�^�[�����Œe���Ă���ƐL�т₩�ŖL���ŋC�����������̂ł����A�ق��̊y��Ƃ̍�
������ő��肷���邱�Ƃ�����܂��B����ƁA�l�̍D�݂ł͂��������߂��Ŗ��Ă�
�ꂽ�ق����������̂ł��B�ŏI�I�ȃo�����X�̒��ŋ�������t�������Ă����̂͊y��
�����A���߂��炻���Ƃ���Ɣ�r�I�߂�ǂ�������ƂɂȂ��Ă��܂��Ƃ�������
������܂��B
�@�i������Ǝv������ł����ǂo�n�c�Q�ł͂`�h�q�̉������ύX����Ă��邩���m��
�܂���B����G�f�B�b�g���Ă݂ĈȑO�̂o�n�c�قǑ���Ȃ��Ȃ����悤�Ȋ���������
���B�S�̂̉���肪�����n�C���փV�t�g����Ă���̂���ۂ�ς��Ă���̂����m��
�܂���B�j
�@�`�h�q�����܂��Z�b�g����Ƃd�p��ق��̃G�t�F�N�g�Ƃ̌��ˍ�������Łu����
��v�̊������o����݂����ł��B�ł�������Ɠ���B
�@�G�t�F�N�g�͑S�ăR���v/�f�B���C�݂̂ɂ��Ă܂��B�ق��̃G�t�F�N�g�Ƌ����ł���
�Ƃ��ǂ��̂ł����B���̕ӂ͉��ǂ̗]�n������̂����m��܂���B�f�B���C�͋���
�ł���̂ł��̃��[�h�ɂ��Ă݂܂����B
�@������Ԃł̓f�B���C���x�����O�ɂ��Ă���܂��B�s�`�o�������Ȃ���l�h�c����
���ƃ��x���̒������o���܂��B���l�ɂs�`�o�{�a�`�r�r�Ńt�B�[�h�o�b�N�ʂ̒����A
�s�`�o���x�������ƂŃf�B���C�^�C���̒����ł��B���͂s�`�o�������Ȃ���
�s�v�d�`�j���ƃf�B���C�^�C����ݒ�ł��܂��B�R���v�̐[���͂s�`�o��������
�ɂs�v�d�`�j���ƕς����܂��B�S�̂ɃQ�[�g�����Ă���܂��B�X���b�V���[
���h�̐ݒ�͉��ɂ���ĕς��Ă���܂��B�g�p���ɂ���čĐݒ�̕K�v�����邩��
�m��܂���B
����������������������������������������������������������������������������
�U�`�@�a�t�c�c�`�@�P�P�Q�@�@�@�@�@�X�g���[�g�ȃN���[���N�����`
�U�a�@�`�b�R�O�s�a�@�P�P�Q�@�@�@�@������ɂ�����Ɠ���������N���[���N�����`
�U�b�@�l�`�s�b�g�k�d�r�r�@�P�P�Q�@�O�҂��f�B�X�g�[�V�����ɋ߂��c��
�U�c�@�a�`�r�r�l�`�m�@�P�P�Q�@�@�@�ቹ���̘c�ݕ��������I
�V�`�@�c�d�k�t�w�d�@�P�P�Q�@�@�@�@����̘c�ݕ��ɓ������������܂���
�V�a�@�i�s�l�S�T�@�P�P�Q�@�@�@�@�@�ቹ���̍r�ꂽ�c�ݕ���_���Ă݂܂���
�V�b�@�i�b�l�W�O�O�@�P�P�Q�@�@�@�@��Ԓ��̒�ԃA���v�A����̂Ђ�Ђ肷�邩��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���o�Ă�ΐ�������
�V�c�@�r�k�n�@�P�P�Q�@�@�@�@�@�@�@�c�݂܂����Ă�����Ȃ��֊s�Ɣ{���̑����A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�C�ɓ����Ă܂�
�W�`�@�a�n�n�f�h�d�@�S�P�Q
�W�a�@�`�b�P�T�@�@�S�P�Q
�W�b�@�`�b�R�O�s�a�@�S�P�Q�@�@�@�@��r�I�N���[���ȉ�������Ă݂܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�͂̏����ȃM�^�[�ł͘c�܂Ȃ������E�E
�W�c�@�l�`�s�b�g�k�d�r�r�@�S�P�Q�@�f���ɐL�т�I�[�o�[�h���C�u
�X�`�@�c�d�k�t�w�d�@�s�n�m�d�@�S�P�Q�@��i�ȃI�[�o�[�h���C�u
�X�a�@�c�d�k�t�w�d�@�S�P�Q�@�@�@�@�����ȃf�B�X�g�[�V����
�X�b�@�c�t�l�a�k�d�@�S�P�Q�@�@�@�@�q�X�e���b�N�Șc�ݕ�
�X�c�@�q�d�b�s�h�e�h�d�q�@�S�P�Q�@�{�����Ԃ��肠���f�B�X�g�[�V����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������Ɖ��܂��������̋�C�͓Ɠ��ł�
����������������������������������������������������������������������������
(2001.03.11)
��back to top
�@
�x�������l�h�w�s
����P�T�Ԃ���x�������ɍs���Ă��܂����B
�Ґm���N���x�������f��ՂɐV����o�i�����̂ŁA���̂��łɃx��������
��������낤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B���傤�ǒҌN�������������V�o��
�h�̃��R�[�f�B���O���ŏI�i�K�ɓ����Ă����̂ŁA�l�h�w���Q�Ȃ�����
���ƂɂȂ�܂����B
�X�^�W�I�̓f�B�y�b�V�����[�h��q�J�V���[��f�r�b�g�{�E�C�����������
���L��n���U�g���X�^�W�I�ŁA�L���ɂ̓S�[���h�f�B�X�N�i�S�[���h���[���H�j
���ׂ��ׂ��Ɖ����������Ă���܂����B
��͂r�r�k�̂S�O�O�O�d�ŁA�R���s���[�^�[�ɂf�𓋍ڂ��Ă���Ƃ����A
���{�ł���������^�C�v�̂��̂Ȃ̂œ��ɂȂ�̈�a�������S���Ȃ��A����
�Ɏd�����Ă��܂����B�l�s�q�}�X�^�[�͂R�R�S�W�ł����A���̃X�^�W�I�ł�
��݂��Ă���܂��B����͊C�O�̃X�^�W�I�ł͒������ȂƎv���܂����B
�d���̊ւ��Ă͋@�ޖʂœ��ɕς�����Ƃ�����Ȃ����{�ł��̂Ƃ�����
���܂��A�ׂ����Ƃ���ɏK���̈Ⴂ��l�����̈Ⴂ�������Ėʔ�
�������ł��B
���{�ō�Ƃ��Ă���Ƃ����炸���Ƃm�g�j�̃h�L�������^���[�̎�ނ�
�����Ă܂����̂ŁA�Ђ���Ƃ�����A��ʂ̕Ћ��ɂł��ʂ��Ă��邩��
����܂���B
�x�������̊X�͂ƂĂ��D�������Ă܂����B�܂��s���������A�o����ΏZ
��ł݂����Ƃ����v���܂����B�Ȃ�ƌ������A�X���D�����ł��B
�l�͔ɉ؊X�����l�����ۂɏZ��ł���Ƃ���ɋ���������܂�����A����
���o�X�A�n���S�A�ߍx�d�Ԃ𗘗p���ĕ������܂����B�ʂ���u�ĂďZ���
����l�B�̐l�킪����Ă�����A���X�̓��e������Ă�����A�܂��悭����
���Ƃł����A�y���������ł��B
�y��Ɋւ��邱�Ƃ��������Ǝv������ł����ǁA�c�O�Ȃ���y�퉮����ɂ�
�s�������炸�A�a�̎s�Ő��{�̃o�C�I�����ƊNJy������������ł��B���x�s��
�Ƃ��͂����ƒ��ׂĂ݂Ă��悤�Ǝv���Ă܂��B�h�C�c�̓d�C�y��͂Ȃ��Ȃ�
�ǂ��ł�����B
(2001.02.19)
��back to top
�@
�M�^�[�����̔z��
�@�M�^�[�����̔z���ɂ��Ă̎������ʂ����X�B������Ă��鉹�̈�ۂ͂����܂Ŗl
�������������Ƃ������̂ł��B���Ɋւ��铯�����t�ł��A�l�ɂ���ẮA�����̈�
�������ɂƂ��邱�Ƃ��L��܂����A���̊�����`����͓̂���ł����A�����炩
�ł��`���Ί������ł��B
�������d�h������
�@�M�^�[���E���O������̃m�C�Y�����炷���߂ɁA���܂��܂ȃV�[���h���@���l����
��Ă��܂��B�A���~���⓺�����g������A�J�[�{�����܂��d�h�����g������Ƃ�
���̂���ʓI�ł��B�ꎞ���̃M�u�\���̂悤�ɐ�p�̃V�[���h�a�n�w���g�p���Ă���
�ꍇ������܂��B�ǂ̏ꍇ���������A�[�X�ɗ��Ƃ����ƂƃV���[�g�ɋC�����邱��
���K�v�ł��B�����̃V�[���h�ɂ��āu���ʂ��Ȃ��A�C�̂����v�ƌ����l�����܂�
���A�l�̎����ł͌��ʂ���ł��B�ł�����A�قƂ�ǂ̏ꍇ���炩�̃V�[���h���{��
�悤�ɂ��Ă܂��B
�@�V�[���h�����ɉe�����y�ڂ��H�@�m���ɂ����ł��B���Ƀs�b�N�A�b�v�̃L���r
�e�B�[�ɂ܂ŃV�[���h���{���ꍇ�A���V�e�ʂɂ���ăn�C�G���h���A�[�X�ɓ����Ă�
�܂��̂��A������Ɠ��ɒu���Ă����������悢�Ǝv���܂��B���̂��Ǝ��̂������Ƃ�
���̂ł͂Ȃ��āA�����������ʂ��L��ƒm������ŁA�ǂ������Ɏg���Ă�����
���ƍl���Ă܂��B�Ⴆ�n�C�G���h�̃R���g���[�������̃V�[���h�ʼn\�ȏꍇ����
��Ƃ������Ƃł��B�m�C�Y��肾���ł͂Ȃ��āA�S�̓I�ȉ����̒��ŃV�[���h���l
����悤�ɂ��Ă��܂��B
�������ނ́H����
�@�ǂ�Ȑ��Ŕz�����邩�l�������Ƃ͗L��ł��傤���H�@���̍ގ���`��ʼn��̏o��
�������ɕς��悤�ł��B�s�̂̃M�^�[�ň����̃V�[���h�����g�p���Ă�����̂��L
��܂����A����͏o����Ό������ĉ����r���Ă݂邱�Ƃ��������߂��܂��B���̂�
����Ȃ��r�j�[���핢�������l�ł��B���ɃA�E�g�v�b�g�W���b�N�ɍs���Ă���z����
�ʂ̕��Ɍ�������Ƃ����Ƌ����ω�������ꍇ���L��܂��B
�@�l�͍��̂Ƃ��됔��̃��C���[��p�ӂ��āA���̃M�^�[�̐��i�ɍ��킹�Ďg������
��悤�ɂ��Ă��܂��B
�@�P�j�I�[���h�̃E�G�X�^���G���N�g���b�N�̃��C���[
�@�Q�j��߂�����
�@�R�j�P���̑ϔM��
�@�S�j�Q����̑ϔM��
�@�T�j���̑����낢��
�Ȃǂ��g���C�A���h�G���[�Ŏg���Ă܂��B
�@�P�j�ŋ߂��Əo����Ă܂��B����ɓ���������悤�Ńs�b�L���O�̃j���A���X��
�悭�`���܂��B���̂������v���C�ɉ��s�������o�܂��B�g�ݍ��킹��s�b�N�A�b�v��
����Ă̓X�S�`�`���a�������ɂȂ�܂��B�Ȃ�ƌ������A���������ł܂��B�p�r����
���܂����A����̕҂ݐ��ō�����X�s�[�J�[�P�[�u���̓_���g�c�ɉ����ǂ��ł��B
�@�Q�j�H�t���œK���ɔ������߂����Ń��[�J�[�Ƃ��悭�킩���Ă��܂���B�n�C�G��
�h�̏o�����C�ɓ����Ă܂��B�����ƑO�ɍ����ȋ�����������Ƃ��́A�s�v�ȉ�������
���ăC����������ł����A�������߂����̓��b�L�ŁA���������Ɉ�����������
�������i�H�j���傤�Ǘǂ������ł��B�J�b�e�B���O�Ȃǂ̂Ƃ��̉��̂��낢���⋿��
�����C�����悢�ł��B
�@�R�j�I�[�f�B�I�}�j�A�̊Ԃł��ƕ]���̗ǂ����̂ł��B���[�J�[�̎���@�Ȃ�
�̓����z���Ō������邱�Ƃ��L��܂��B
�@�P�j�Q�j�R�j�����͂�������Q����ł͂Ȃ��P���ł��B�ǂ������킯���w�i�w�i
�̔Q����͉����ӂ₯�����������܂��B�Q����ł����鎞���̃M�u�\�����g���Ă���
�悤�Ȃ�����ƍd�߂Őc���̖{�������Ȃ����͉̂����ǂ��悤�Ɋ����܂��B�C�ɂ���
�Ďg���Ă���W���[�WL's�̃V�[���h�P�[�u���̐c�������Ȃ�d���ł��B�ŋߓ��肵��
�E�G�X�^���G���N�g���b�N�̔Q��������Ȃ�d���āA�Ȃ��Ȃ��ǂ��������܂��B
�@�S�j�͎�ŐG�������G�͂���قǍd���͗L��܂��A�����Œ�]������̂ł��B
�@�E�G�X�^���G���N�g���b�N�Ƃ͂܂�������Ӗ��Œ�����ɓ������ł܂��B���܂���
�l�̃e���L���X�^�[�Ɏg���Ė\��������傤�Ǘǂ������ł��B�E�G�X�^���G���N�g
���b�N�̒P���ɂ���ƈӐ}�Ƃ͈Ⴄ�����ȉ��ɂȂ��Ă��܂��āA�l�̃M�^�[�̃o��
�G�[�V�����̒��ł̋��ꏊ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
�@�o������{����ʂ̃e���L���X�^�[�̓z�b�g���ɃE�G�X�^���G���N�g���b�N�̔Q��
���A�A�[�X���ɃE�G�X�^���G���N�g���b�N�̔Q����Ɓ@�Q�j�̋�߂������̃p������
�ŁA���傤�Ǘǂ������ɂȂ�܂����B�p
�@�T�j���̂ق��ɓ��̒P���e���A�C�ɓ����Ă���V�[���h���C���[���甲�����c��
�Ȃǂ������Ă��܂��B�x���f���̋�߂�������I���C�f�̃��b�c���Ȃǂ��ǂ�������
�̂Ŏ��p���Ă܂��B
�@���b�c���́A�l�̍l�����ł̓p�������g�p�̋��ɂ̎p�Ȃ̂ŁA�������܂��g������
�Ȃ����̂��͍����Ă܂��B����\�͔��ɗǂ��ł��B�ǂ����Ă�����Ǝ��ė]���悤
�ȂƂ��������܂��B�R�[�h���c�q�ɂȂ肪���ȃs�b�N�A�b�v�Ƒg�ݍ��킹��
��E�E�E�Ȃǂƍl���Ă܂��B
�@�x���f����߂������Ɓ@�Q�j�̋�߂��������p���Ŏg���ƁA���ł͓����Ȃ��u�p
�L�b���v�H�������ɂł܂��B������ǂ̃M�^�[�Ŏg�����E�E�E�Y�݂͂��܂���B
�@�ǂ̐��ނ��ǂ��̂����_�͂܂������łĂ��܂���B�������ނ��{�҂ݍ��킹��
�g���Ă݂���A�ʂ̐��ނƃp�������Ŏg���Ă݂���A���̎����̎��ŁA��肻�̃M
�^�[�炵�������ł���̂��n�j�Ƃ��Ă��܂��B������Ɨ��������ƁA�v���f���[
�T�[�̂s���̃M�^�[�i�X�g���g�^�C�v�j�̓E�G�X�^���G���N�g���b�N�A�v���f���[
�T�[�̂m���̃��X�|�[�����E�G�X�^���G���N�g���b�N�A�M�^���X�g�r���̂r�f�̓E�G
�X�^���G���N�g���b�N�Ƌ�߂������̃p���������g�p���Ă݂܂����B
�@�l�����L���Ă���M�^�[�̓����͐獷���ʂł��B�قƂ�ǂ������p�̃M�^�[�݂���
�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���̂ɂ���Ă͈�T�Ԃ��Ƃ��炢�ɕς���Ă����肵�܂��B���̓p��
�����̊��G���C�ɓ����āA���X�Ɋ�������܂��B��{�I�ɂ͒P���̂ǂꂩ�ŏ���
�Ă����ŕ�����Ȃ��Ƃ��Q����Ɉڍs���Ă����܂��B�p�������̑g�ݍ��킹���l��
�Ď����Ă����ƉʂĂ��̂Ȃ���ƂɎv���Ă��܂��B���A�]�݂̉�������ꂽ�Ƃ��ɂ�
�{���Ɋ������Ȃ�܂��B
�@�A�[�X���̔z������L�̐��ނ��g���C�A���h�G���[�ł�����͂������肵�āA�x
�X�g�}�b�`��T���Ă��܂��B�������ؓ�ł͂����܂���B�z�b�g���Ɠ������ނ��x
�X�g���Ƃ����ƁA����Ȃ��Ƃ������悤�ł��B �z�b�g���Ƃ̔����ȃo�����X�Ƃ�����
�̂��L��悤�ł��B
�@�ǂ��炪�킩�猈�߂Ă����̂��ǂ��̂��A���s���낵�Ă܂��B����ł̓A�[�X����
�ǂ���Ǝv�����̂Ɍ��߂Ă��܂��č�Ƃ�i�߂Ă܂����A�ŏI�I�ɂ܂��A�[�X���C��
�ɖ߂���������Ă܂��B
�@��L�̔z����ŁA�M�^�[�̒��̔z���S���ɂ��̐��ނ��g���Ă���Ƃ����킯�ł͂�
��܂���B���������W���b�N�����珇�Ɋ����Ă����āA������x�̉��ɂȂ����Ƃ���
�łƂǂ߂Ă���܂��B�ł�����A���̂ɂ���Ă̓A�E�g�̔z�������������Ă�����A
�قƂ�ǂ��ׂĂ������Ă�����A���낢��ł��B�A�[�X���͂قƂ�ǔz�����Ȃ�����
���������ł��B
�@�Ƃ�Ƃ߂��Ȃ��A���͂��o���Ă��Ȃ��̂ł��܂�Q�l�ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂����A�g
�p������ނʼn����ς��\�������邱�Ƃ����́A�m���Ă����đ��͂Ȃ��Ǝv����
���B
�����Q����͑ʖڂȂ̂��H����
�@�ǎ��ȃP�[�u��������Ă���I�[�f�B�I�N�G�X�g�Ђ̃p���t���b�g�͂ƂĂ��Q�l��
�Ȃ�܂��B�Q����̖���P���̑����̉e���ɂ��Č��y���Ă��܂��B���Ђ��ŏI�I
�ɍ̗p���Ă���̂̓��b�c�\���̂��̂Ȃ̂ł����A���̗��R���q�ׂĂ���܂��B��
���A���l�ɑf���炵���P�[�u��������Ă���J���_�X�Ђ̃p���t���b�g�����܂��ƁA
�u�I�[�f�B�I�N�G�X�g�Ђ��قȂ����o�H�����ǂ�Ȃ��瓯���l���ɂ��ǂ蒅�����v��
�����悤�Ȃ��Ƃ������Ă���܂��B�܂藼�ЂƂ���{�Ƀ��b�c�\����������Ă�
��Ƃ������Ƃł��B
�@���������ςɌ����āA�����ł͔Q����͍D�ӓI�ɂ͌���Ă��܂���B���镔���l
�������v���܂��B�������A�l�͔Q���������قǐ�]�I�ɂ͌��Ă��܂���B�M�^�[��
���̔z���Ƃ������ƂɌ��肵�čl����A���ʓI�Ȏg����������������̂ł͂Ȃ���
�Ƃ�������ł��B���傤�ǃM�^�[�V�[���h�̃J�[���R�[�h�̑��݂݂����Ȃ��̂ł��B
�J�[���R�[�h���I�[���}�C�e�B�[�Ɏg����Ƃ͌����Ďv���܂��A����łȂ����
�łȂ������m���ɂ���܂��B����䂦�ɑ��݉��l�������������Ƃ��o���܂��B
�@�Q������A���܂��g���ǂ��낳������Ό��I�ȃT�E���h�����o����̂ł͂Ȃ�
���Ǝv���āA�������Ă��܂��B���ہA��ɏ����܂����悤�Ɉꕔ�̃M�^�[�ŗǂ�����
���o���Ă��܂��B
�����n���_�H����
�@�n���_�̎��ɂ���ĉ����ς��悤�ł��B����͂܂�����ނ��������Ă��܂���B
�e�Ђ��獂���ȃn���_�����\����Ă܂����A�����Ȃ̂ƍ�Ƃ��߂�ǂ������̂ƂŁA
�Ȃ��Ȃ��e�X�g�ł��܂���B���̂������Ȃ���Ƃ͎v���Ă܂����E�E�E�E�܂���
���������܂��B
�����L���p�V�^�H����
�@�g�[����H�ɓ����Ă���R���f���T�[�ł��B����������ĉ����ς��H�@�^�Ђ���
�o�Ă���{�Ȃǂ�����Ɓu�C�̂����ł́H�v�Ə����Ă���܂��B�ł����������Ă݂�
�Ɩ{���ɕς��݂����ł��B���܂łɃR���f���T�[���������~���[�W�V�����������A
�ٌ������ɕω�������܂��̂ŁA�C�̂��������Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B�l����
��������Ǝv���Ă܂��B�X�^�W�I�̃R���\�[���̃R���f���T�[��ʂ̂��̂Ɋ������
�����ω����܂��B�I�[�f�B�I�}�j�A�̉�b�ł��u���̗ǂ��R���f���T�[�v�ɂ��Ă�
�l���o�ꂵ�܂��̂ŁA����͂�͂�{���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�قƂ�ǂ̃M�^�[�̃g�[����H�̏ꍇ�A���̃R���f���T�[�Ɖϒ�R�Ƃɂ��t�B
���^�[���Ԃ牺������ςȂ��ł��B�ł�����R���f���T�[�̓����̈Ⴂ�ɂ���č���
�ł�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H���݂ɂ��낢��ȃ^�C�v�̃R���f���T�[�����Ă݂�
�ƁA�g�[���S�J�̏�Ԃł������[�ɂȂ�����A�V�����V���������o����A�r��C����
�Ȃ����肵�܂��B
�@�Ƃɂ����g�[���̃R���f���T�[�͑I�ԉ��l�����肻���ł��B�R�[�l���_�u���[PM�ƑO
�q�̔z���ރE�G�X�^���G���N�g���b�N��g�ݍ��킹��ƁA�{���ɏa�������ȃT�E���h
�̃M�^�[�ɂȂ�Ƃ�����ۂ��L��܂��B�i�R�[�l���_�u���[�ɂ����낢�날���āA��
�ꂼ�ꉹ�������ɈقȂ�܂����B�j
�@�����ЂƂC�ɓ����Ă���̂̓q���[�}���E�M�������̃X�v���O���u�I�����W�h
���b�v�v�ŁA �ŋ߂̉��y�ɂ��������ȋC�����Ă܂��B����̓|���G�X�e���t�B�����R
���f���T�[�������ł��B
�@�|���v���s������X�`���[���̂��̂��D�݂ɍ����悤�ŁA�e�X�g���ł��B �ɂ�����
���Ă͏H�t���Ŋe��R���f���T�[���w�����Ĕ�r�������Ă܂��B�|���v���s�����ł�
�d�q�n���Ɛ_�h���ł͉����Ⴂ�A�X�`���[���ł������̂��̂͂܂�����āA�����ɂ�
�Ȃ肻���ł��B
������҂����Ă��܂�����
�@���̂Ƃ���A�l�̓Z���~�b�N�����܂�g����������܂���B�����ȊO�̃����b�g��
�Ă����ł��傤���B�t�F���_�[�͏����̃y�[�p�[�i�I�C���H�j�R���f���T�[�̂�
�ƁA�U�O�N�ォ�炸���Ԃ����ƃZ���~�b�N���g���Ă܂������A�������炩�g��
�ꏊ�ɂ���ă}�C���[�����݂����Ă܂��B�}�C���[�̕������i�I�ɍ����̂ŁA������
�v�f���Ȃ�����������ύX�͂Ȃ��Ǝv���Ă܂��B�͂����肵�����R���������̕���
������Ⴂ�܂��H
�@�M�u�\���͏����̕��̓y�[�p�[�i�I�C���H�j�ŁA��͂�U�O�N�ォ��Z���~�b�N��
�嗬�ɂȂ����悤�ł��B�������l�������Ă���V�O�N��̕��̓Z���~�b�N�ł͂Ȃ���
�ŁA���̂ɂ���Ďg�������Ă����̂��ȂƂ��v���܂��B
�@���ЂŎg�p����Ă���R���f���T�[�̃��X�g����肽���Ē������ł��B���̂�����
�̎������������̕��A�R���f���T�[�ɏڂ������A���Ѓ��[�����������B
�X�������肢�������܂��B
(2000.12.29)
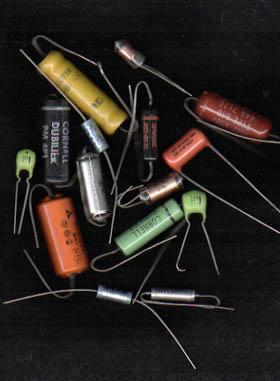
�R�[�l���_�u���[�A�X�v���O�AERO�A�_�h�A���̑��e�Ђ̃R���f���T�[
��back to top
�@
�����i�X�`�[�����j�͕�������̂��H
�@�M�^�[��x�[�X��e���Ă���Ƃ��ɋP�����Ȃ��Ȃ��Ă��āA������A��
������ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B���̎���ł��܂��̂ł��傤�B
�@�ЂƂɂ͌��Ƀt���b�g�ɂ�鏝���t���āA���ꂢ�ɐU�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����
���l�����܂��B����̓t���b�g���̊y��ł��邢���傤�������Ȃ����Ƃł��B
�@�����ЂƂɂ́A������J�������邱�Ƃ��L��܂��B����������ɂ��Ă�
������Ɣ[�������˂镔�������X�L��܂��B�ƌ����͓̂����悤�Ɍ����U������s�A
�m�ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ�����ł��B���ہA�s�A�m�̌��̎����͋����قǒ�
���A���������������킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��قǂł��B���������āA�P�Ȃ������
�J���ɂ͎���������Ă��܂��̂ł��B
�@�s�A�m�Ƃ̈Ⴂ���l����ƁA��̎w�Œ��ڌ��ɐG���āA���������Ă��܂��Ƃ�����
�Ƃ��L��܂��B���M���Ċ��������Ă��܂��悤�ȉ��t�������Ƃ��ɂ́A���ɂ���ʂ�
����肠�������邱�ƂɂȂ�܂��B����̉e���͑����L��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���Ɋ������̏ꍇ�A���̊��̊Ԃɑ����ȉ��ꂪ���荞�݁A�����~���[�g���Ă��܂���
�Ƃ��l�����܂��B�Ȃ�Ή��炩�̕��@�ł��ꂢ�ɂ��Ă݂���ǂ��ł��傤�B
�@�����Ԃ�̂���A������������ɂ͂����Ŏς�悢�A�Ƃ����̂��L���
���B�n�R�o���h�̂Ƃ��͂��ꂾ���ɂƂǂ܂炸�A���܂��܂ȍĐ�������������������
�ł��B�����������C�O�̎G���ł��ς�悢�Ə����Ă���̂��݂��������Ƃ��L��
�܂��B�ς�Ή���͌��\���������ł��B
�@�����ŁA����g���Â��̃x�[�X�����g���āA�ς邱�ƂŌ�����������̂��ǂ���,��
����x�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�l�̃X�g�b�N�̒��ɂ̓~���[�W�V������������
���Â������e�킠��܂��B����͌Â����̉����ق�������ȃ��R�[�f�B���O�̂Ƃ���
�g����悤�Ɋm�ۂ��Ă�����̂ŁA�Ȃ�ׂ������������̂������c���Ă���܂��B
�@�̂̋L���ł́A�����ς������ł͂���قǐ����Ԃ�Ȃ������L�����L��܂��B����
�͉�������Ƃ������Ƃ����ɂ��Ă���̂ŁA�d�������ĎςĂ݂邱�Ƃɂ��܂�
���B����͓�Ȃ̉�������̂ɏd�������ʓI���Ƃ����L�����ǂ����Ō����悤
�ȋC�����Ă�������ł��B
�@��ɓ������Ċe��x�[�X�����ۂ߂ē������ݏd�������Ă݂܂����B����ƁA
�łĂ���͂łĂ���́A���ꂪ�o�[���ƖA�ɂȂ��Đ�����Ԃł��B���̂܂܂P�O����
�炢�ςČ������o���܂����B���C���悭���Č���L���Ċ������܂����B�悭��
���Ă���X�v���[�I�C���������Ƃӂ������Ċ������z�Ő@�����܂����B
�@�����x�[�X�ɒ����Ď����Ă݂�ƁA�Ȃ�Ɗe�팷�Ƃ��A���Ȃ蕜���ł��B��͂茷
�̊��̒��ɓ����Ă������ꂪ�����ɂ̌����������C�����܂��B
�@�ς�ƔM�̂����Ō��������Ԃ�Ƃ��������L��܂����A���X�P�O�O�x�ŋ����ɂ���
�Ȃɉe�����L����̂Ȃ̂ł��傤���H�ȑO�ςĂ݂��o�����炷��Ɩl�̂Ȃ��ł͉���
�����L�͂ł��B
�@�����y��ɒ������܂܂Ŋ����ɃN���[�j���O������@������A���Ȃ茷���ɂ�
�h�����Ƃ��ł����ł͂Ȃ����낤���Ǝv���Ă܂��B�����ǂ����@�͂Ȃ����̂��낤
���E�E�E
�@�������̂̓X�`�[���̊����݂̂ł��B�v���[�����͂ǂ��Ȃ�̂��肩�ł͂���
�܂���B�܂��i�C�������͂ǂ�������悢�̂��܂������s���ł��B�i�C����������
������Ă��ǂ����̂Ȃ̂ł��傤���H�i�C�����͂P�O�O�x�̔M�̉e��������Ɏ�
���ł����B�茳�Ɏ����ޗ����Ȃ��܂������Ă݂Ă܂��A���̂����Ì����W�߂Ă�
�낢�����Ă݂悤�Ǝv���Ă܂��B
�@���������v���̃h���}�[��,�h�����w�b�h���h���C���[�ŔM����ƃX�e�B�b�N�ŏo
�������ڂ݂��C������Ă͂肪�߂�A�ƌ����ă��R�[�f�B���O�̍��ԂɃh���C���[��
�����Ă���̂��݂����Ƃ�����܂��B����͖{���ɂ����Ȃ�܂��B�������������͂�
�܂���B��͂�A��x�f�R�{�R�ɂȂ����Ƃ���́A�܂��f�R�{�R�ɂȂ�Ղ��悤�ł�
���B
�@�������݂�Ȃ悭�H�v���Ă܂��ˁB�����ǂ��H�v�����Ă�����A�m���Ă��������
�����Ă��������B���ւ肨�҂����Ă��܂��B
(2000.11.26)
��back to top
�@
�s�b�N�ɂ��Ă̍l�@
�@�@�y�퉮����ɂ����Ɗe�푽�l�ȃs�b�N�������Ă���B
�@�g�p����s�b�N�̑I���͂ǂ�������悢�̂��낤���B�X�^�W�I�Ńv���~���[�W�V��
���̎g�p�s�b�N������ƁA�|���V�[�������Ă���ƌ�����l�ƁA�����ł��Ȃ�
�l������݂������B
�@�C���^�r���[�ŃA�[���E�N���[�������Ă���Ƃ���ɂ��ƁA�Ƃɂ����y�퉮����
�ɂ���s�b�N�����ׂĈꖇ�������Ă��āA�����ɂ������̂�I�ׂƓ����Ă���B
�@��������̂����z�����A���ۖ��Ƃ��Ă����������Ȃ��B�����ŁA�l�����܂Ŏg��
���s�b�N����Љ�Ă݂悤�Ǝv���B
������ꈍb���ō�������
�@�܂��ގ������A�_���g�c�ɗǂ��̂�ꈍb�i�{���j�ł���B�G���Ă݂Ă����������
���Ɏv����������Ȃ����A�e���Ă݂�Ɓu������v�����ɂ悭�ӊO�ɂ�����������
�Ȃ��B���̗��������ǂ��A�R�[�h�X�g���[�N�A�P���e���ǂ�����ǂ��B���ɗ��҂���
�݂��Ă���悤�Ȓe�����̂Ƃ��A�P���e�����キ�Ȃ��Ă��܂����������Aꈍb�s�b�N
�ł͂��̗��������Ȃ��B�ق��̃s�b�N�ł͂��Ȃ�s�b�L���O�ɒ��ӂ��Ȃ��Ɨǂ��o��
���X�ɂȂ�Ȃ��Bꈍb�Œe���Ă����Ƙ^�����͂Ƃ��Ă��y���o����B���ɓI���R��
������R���v/���~�b�^�[�E�d�p�̗ʂ����Ȃ��o����B�i�ϋɓI���R�ł�����R���v/
���~�b�^�[�E�d�p�ɂ��ẮA���̌���ł͂Ȃ��j
�@�G���N�g���b�N�A�A�R�[�X�e�B�b�N�Ƃ��ɍD���ʂ����҂ł���B��ɓ���Â炢��
�Ƃƍ����ł���i���P�O�O�O�`�P�T�O�O�H�j���Ƃ��ʂ���ł���B�ꎞ�A��������
�~�ɂȂ����Ƃ̘b�����������ǂ��Ȃ낤�H���V���g�����̏���������ē`���
�����̂Ȃ낤���B���݂ł�����ł���X�͂���̂ŁE�E�E
�@�I�ԍۂ̒��ӂƂ��ẮA�������u�����́v�ꖇ�������Ⴄ�̂ŁA�������e�����
�āA�D�݂̂��̂�I�ׂ悢�B�����Ȕ����S��̈Ⴂ������݂������B�`������[
�J�[�ɂ���ĂȂ̂�������Ȃ����A�������Ⴂ������B
�@���܂茸��Ȃ����������Ԏg����̂ŃR�X�g�p�t�H�[�}���X�͗ǂ��̂��������
���B�̕��̃M�^���X�g�̘b�ł́A�w�̔M�ƈ��͂ł������Ɏ����̎w�ɂ҂����荇����
���ɕό`���Ă��āA�����g���Ύg���قǒe���₷���Ȃ��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B
�������N���C�g���̔������͂Ȃ��Ȃ��ǂ�������
�@���ɂ����߂Ȃ̂��N���C�g���Ђ́uꈍb���v�Ƃ������O���t�����s�b�N�i���b�N
�X�͔�������ꈍb�͗l�ł͂Ȃ��j�ł���B�N���C�g���Ђ���͔����ۂ��f�ނ̂��̂�
�łĂ��邪�A����ł͂Ȃ��B
�@ꈍb�̃s�b�N�����̏�Ȃǂɗ��Ƃ��Ă݂�ƂƂĂ��������ǂ���������̂����A�N
���C�g���́uꈍb���v���ƂĂ��悭�����ǂ���������B�e���Ă݂�ƁA�����ɓ���
�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���̌X�����ƂĂ��悭���Ă���B
�@�����͂T��ނ��炢�����čD�݂ɍ��킹�đI�ׂ�B�ǂ̌������A�N�j���N�j������
�肠�邢�͕ςɃS�c�S�c�����肷�邱�Ƃ������A�ƂĂ��e���₷�������������ǂ��B
�l�i�̓A�����J�̃V���b�v�ŕ��ʂ̃s�b�N�̂R�{���炢�̒l�i�Ŕ����Ă���̂ŁA
������ƍ��߁A�Ƃ����Ƃ��낾�낤���B���{�ł͂��܂茩�����Ȃ����A�ꉞ�A���㗝
�X�����܂��Ă��Ĉ����Ă���͂��Ȃ̂ŁA����Ƃ���ɂ͂���̂��낤�B�l�͏����X
�Ō����������Ƃ��Ȃ��̂ł�����̒艿�����Ă��邩�m��Ȃ��B
�@�l�̒��Ԃ����Ńe�X�g���Ă݂ĂƂĂ���ǂ��̂ŁA�F�l�̉�Ђł��P�N�قǑO��
�爵�����ƂɂȂ����B�v���~���[�W�V�����Ŏg�p���Ă���l�������Ă������A�قƂ�
�ǂ��̗F�l�̂Ƃ���œ��肵�Ă���Ǝv���B
�������f���������͂��ƍD�����ȁ�����
�@�e�Ђ���f���������̃s�b�N���e��łĂ���BJIM DUNLOP��FENDER�Ȃǂ����
�Ă���J���t���ȉ��̂���s�b�N�ł���B���̑f�ނ͊��肪�ƂĂ��ǂ��݂����Ō���
�s�b�N���������Ă��鎞�Ԃ��Z���A�u������v�����ꂢ���Ǝv���B�A�^�b�N���ɕς�
�U���������N�����Ȃ����炾�Ǝv���̂����A�����̗ǂ����ꂢ�Ȋ����̉�������B��
���̃s�b�N�ɂ�鉹�̕��͑O�q��ꈍb�E�N���C�g���قǍL���͂Ȃ��Bꈍb��N���C�g
���uꈍb���v�́A���̓s�b�N�̌���������قǑI�Ȃ��B�ǂ���g���Ă�����Ȃ�
�̒e���₷���Ɖ�������B�f���������͂����͂����Ȃ��݂����Ȃ̂ŁA�e���������
�낦�Ďg��������Ɨǂ����낤�B�l�i�͕��ʁi���P�O�O���炢�j�A���Ƃǂ��̂��X
�ɂ������Ď�ɓ���₷���B
�@�ꕔ�̃��[�J�[�Ŏd�グ���r���ăo���̂悤�Ȃ��̂��łĂ�����̂�����B�����
�C�ɂ��Ďg��Ȃ��l������̂����A������̂����Ηǂ���������̂ōH�v���Ďg����
���ǂ��Ǝv���B�H�v�Ƃ����Ă��A�i�C�t�Ōy���o���������邾���ł���B�i�C�t��
�n�p�ɋ߂����Ăč����悤�ɂ���ƊȒP�ɂł���B����ނ��̂₷���p��
���č���Ďd�グ�Ă��ǂ����A������ƍH��̒m�����Ȃ��Ƃ��ꂢ�Ȋ��炩�Ȏd�グ
�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�������Ėʓ|��������Ȃ��B
�@�i�C�t�Ńo����肷����łɁA�|�C���g�̌`��p�x���e�����Ă�����Ȃ��o
���G�[�V�����������ĕ֗����B�l�͂Ƃ������̂Ƃ��ۂ߂̂��̂Ƃ��ɂȂƂ��ɍ�
�肽�߂Ă���B
�������s�n�q�s�d�w�����͍D���Ȃ��ǁ�����
�@JIM DUNLOP����łĂ���A�������C���̃G�b�W���������ƃX�N�G�A�ȃs�b�N��
����B���������Ă�����ɂ����A�x�[�X�Ɏg���Ă��D��ۂ��B���͓݂����Ȍ�������
�芣������������B�����̃Z���~�b�N���ۂ���ۂ���l�͎����Ă���B
�@����d���ł́A�M�^�[�e�N�j�V�����̉��̎�͊e������̂s�n�q�s�d�w�s�b�N
�������B���ꂮ�炢����ɍ��ꍞ��ł���l������B�f���͗ǂ��B
�@�����ЂƂ��P�ł��Ȃ��̂��ȂƎv�����Ƃ͔����Ă���s�b�N�������邱��
�ł���B���߂̕��͗ǂ��̂����A�����Ȃ�ɂꔽ���Ă�����̂������Ă���B����
�u�ځv�̂悤�Ȃ��̂�����݂����ŁA������ɓ��ނ���悤���B������ɂ��Ă���
�x���z����Βe���ɂ����B
�@�l�i�͂�͂聏�P�O�O���炢�ŁA�ǂ��̂��X�ł�������悤���B�A�����J�ł̒l�i
�͑O�q�̃N���C�g���͍����ĂU�O�Z���g�A�f�������͂P�T�Z���g�A���̃g�[�e�b�N�X
�͂Q�O�Z���g���炢���B�i���V�O�`���P�V���炢�B�����I�j
�@���{�Ŕ����s�b�N�͍����B�s�b�N�������Ȃ瑗���͈����̂ŁA�l�͂����ς��
�̂ł܂Ƃ߂Ĕ����Ă���B������ɓ��ꂽ���̂Ȃ̂Ń~���[�W�V�����ɂ��e�X�g�p��
�C�y���v���[���g���Ă���B�ꖇ���P�O�O�ȏ�Ȃ�ƂĂ������͂����Ȃ��Ǝv���B
�������i�C�����s�b�N�Ƌ����s�b�N������
�@�i�C�����s�b�N�͂��鎞����r�������̂����A�l�͍��͓���ȏꍇ�ɂ����g���
���B�A�^�b�N�̂�������D������Ȃ��ꍇ����������B�������A�e�Ђ��瑽���̃��f
�����o�Ă���Ƃ������Ƃ́A���ꂾ�������Ƃ������Ƃ��낤���B�i�C�����s�b�N��
�g���ƁA�܂��A���܂����ɕ������ċC�������ǂ��A�Ƃ������Ƃ͗L�邩������Ȃ��B
�l�ɂ͂��ꂪ�A�^�b�N�̞B�����ɕ������Ă��܂��̂����B
�@�����̃s�b�N�͌������Ƃł鉹������Ă߂炤�B�ȑO����X�e�����X���ۂ��f
�ނ̂��̂��������ƋL�����Ă��邪�A�ӊO�ƃ\�t�g�ȉ��F�ŋ��������Ƃ��L��B�s�b
�N�e�b�N�Ƃ����t�@�C�o�[�̃s�b�N���J�����Ă��郁�[�J�[�ŁA�����s�b�N�����삵
�Ă����B�l���t�@�C�o�[���̂��̂ɋ��������蒼�ژA�����Ă����W��A�����̂�
�łɎ���i��i�����ꂽ���̂����Ă���Ă����B�A���~�̂��̂ō�����ς�
�Ă݂���A�h����ς��Ă݂���A��������ς��Ă݂���A�������H��ς��Ă݂���A
�^�J���ɂ��Ă݂���A�������Ă݂���E�E�E��������������Ƃ͈���āA������
�������F�ŁA�����ɍD���������肷��B�Ƃ��ɂ��イ�̂��̂͏d�����ӂ��߂Ă�
�݂̂��ȁE�E�E
�@�ꕔ�̂��͕̂��ʂɔ�����Ǝv���B���X�ɂ͕���łȂ���������Ȃ��̂ŁA���[
�J�[�ɘA�����Ƃ�̂������葁����������Ȃ��B�����A����͊��ɕ��ʂł͂Ȃ�
���B
�@�����Ƃ����ƈ�ʂɉ��̂����۔������L��B�����Ɍ������Ƃ��L���L�������
���E�E�E�ł������Ă݂����ʂȂ̂��ǂ����E�E�E�E
�@�t�B���K�[�s�b�N�̑����͋����ō���Ă��āA�ׂɖ��Ȃ��g���Ă���B�܂�
�R�C���Œe���Ă���v���~���[�W�V�����̘b�͂悭���ɂ���B���ɓ��{�̂T�~�ʂ�
�s�b�N�Ƃ��Đl�C������B���J���ł���Ƃ������ƂŊ��Ŋ���ɂ����g���₷���炵
���B����������ɃM�U�M�U���Ȃ��āA�ƂĂ���ǂ��炵���B�����̍ۂɑ�ʂɎd��
��Ă����Ƃ����b�������Ƃ�����B
�@�b�̂��łɁA�t�B���K�[�s�b�N�ł̓i�V���i������Ԃ��낤���ǁAJIM DUNLOP
�̂Q��ނ̑f�ނƁA�L�x�ȃQ�[�W�̎�ނɂ͈��|�����B�O���[�o�[�͎̂d�グ�
�ƍd�������܂ЂƂC�ɓ���Ȃ��B������D�݂ł����B
�������s�b�N����Ȃ����ǁE�E������
�@�s�b�N����Ȃ����ǃo�C�I�����̋|�ŃM�^�[��e���Ƃ����̂�����B�W�~�[�E�y�C
�W�̓��ӋZ�B���̋|������Ə��������Ďw�ɂ��Ēe���H�悤�ɂȂ��Ă���̂���
��B�s���j�A�Ƃ������O�݂����ŁA���̊G���`���Ă����āA���̌��Ɏw�����݂���
��B�������������ɂ��邪�E�E�E����B�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�ł��ق����ȒP
�ŁA�\���b�h�̃G���N�g���b�N�ł͂Ƃ��Ă�����B�����Ǝg���Ă�l����������
���Ȃ��E�E���āA�����Ă�l�ɏo��������Ƃ������B�@����ɔ�ׂ�Ƃd�[�a�n�v��
�傢�Ɏg����B�����̗R���̓G���N�g���b�N�E�{�E�Ƃ������Ƃ��낤���B����ƂƂ�
�ɂR��ނ��炢���łĂ���悤�ŁA�ǂ���g���čD���ʂĂ���B
���������K��p�s�b�N������
�@���K��p�̃s�b�N���L��B����ނ��L��̂�������Ȃ����A���܂Ō������̂͂���
����s�b�N��[���ɕςȏo������������悤�Ȃ��̂ŁA�s�b�N�̂��������������
�����������Ēe���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����Ă݂����ǂ��Ȃ����B
�@���Ǝv���Ǝw�ɂ��Ēb����Ƃ����I�����������Ă��Ēi�K�ɉ����ĉ���ނ��L��
�悤���B�܂������Ȃ�ƌ����Ă悢���E�E�E���`�`��A�����Ă݂����I
�������e�B�A�h���b�v���g���C�A���O����������
�@�`��ɂ��Ă͂ǂ��Ȃ낤�B�l�̓e�B�A�h���b�v�i�X�^���_�[�h�j�̂ق����D
���Ȃ̂����A�d���ŏo��l�B�͖X�̂悤���B��ʓI�Ƀo���[�ŃR�[�h��������
�āA�R�[�h�X�g���[�N�ő����̌���e���A�ƌ����X�^�C���̐l�Ƀg���C�A���O������
���݂������B
�@���ɃR�[�h���Q�`�R�������ŁA�P���ɂ��v���C�������l�̓e�B�A�h���b�v���D
�ނ݂������B�����ƒe����ǂ���ł��ǂ����ǁA������ƋC�ɂȂ�B
�@���ꂩ��s�b�N���������Ƃ��̎�̂Ђ�̌`���A���{�l�͂��ƊJ���ď��w��
�ǂ����ɒ����Ă����肷�邱�Ƃ������B���E�I�H�ɂ͂��̃X�^�C���͂ނ��돭���h
�ŁA�y����̂Ђ����Ă���l�̂ق��������炵���B
�@�s�b�L���O�̃X�s�[�h�Ƃ������ƂŌ��Ă݂�ƁA�l�̊ώ@�͈͂ł́A�y�������Ă�
��ق����X�s�[�h�������݂������B�X�g���[�N�A�P���Ƃ��ɉ��̗����オ�肪�ǂ��B
�s�b�N�̂��������������̂ق������z�I�ȏ�ԂɂȂ�₷���悤�ł���B�ƌ���
���A�s�b�N�̂�������������ƃR���g���[���ł��Ă���ƌ����ׂ���������Ȃ��B
����J������Ԃł͂ǂ����Ă����̓����������������悤���B
�@���������̃X�^�C���Œe����l��������A����ӎ����ė����̉��̈Ⴂ�ƃs�b�L��
�O�X�s�[�h�i�����e���|�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�e�s�b�L���O���̂��̂̃X�s�[�h�j��
�ω��������Ă݂Ăق����B
�@���������Y��Ă���C�����邯�ǁA�܂����x�B
(2000.10.20)
 �s�b�N���낢��B
�s�b�N���낢��B
��back to top
�@
�M�^�[�A���v���f���[�̔�r�e�X�g
�@���b�g�[�~���[�W�b�N�́u�T�E���h�����R�[�f�B���O�v����
�˗��ɂ��A�����郂�f�����O�A���v�̔�r�e�X�g���s��
�܂����B�M�^���X�g�̓����iDr.K�j����Ƃ̋�����ƂŁA
Dr.K studio�ōs�Ȃ��܂����B�e�X�g�����͎̂��̂U�@��ł�
�����A���ۂ̋L���ł͏��Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
POD2(LINE6),J-station(johnson),Sans Amp classic(TECH21),
GM-200(ZOOM),vg-88(Roland),DG-STOMP(YAMAHA)
�@LINE6��johnson�͂������ɗǂ��o���Ă��܂��B
SansAmp���A���f����������Ȃɋ����ӎ����Ȃ���A
�\���Ɏg���܂��B
�@�L���ł͐G��Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A�ڂ������L���Ă���
SansAmp�͂��������^�ŁA���s��classic�Ƃ͉�H��p�[�c��
�قȂ��Ă��܂��B���̔�r�����Ă݂܂������A���炩�ɈႢ�܂��B
�ǂ��炪�ǂ��Ƃ͈�T�ɂ͌����܂���B�܂��A�D�݂ɂ���ĂƂ���
�Ƃ���ł��傤���B�L�����Ō��y����Ă���̂́A���s���f���ł��B
�@�܂��AMorley����o�Ă���W�F���[�E�h�i�q���[�v���A���v���A
�Q�l�̂��ߎ��Q���܂����B����͓��{�ł͂قƂ�ǒm���Ă��܂��A
���傤��SansAmp�̂悤�Ȋ��o�Ŏg������̂ł��B
��������͂Ȃ��Ȃ��ǂ��ł��B��{�I�ȃT�E���h�������ɂ�
�W�F���[�E�h�i�q���[���Ńt�@���Ȃ��ɗ~�����Ȃ�v���A���v�ł��B
���i�I�ɂ������₷���l�i�ł��B���{�ɂ��邩�ǂ����͕s����
���B�l�͊C�O�̃V���b�v�̒ʔ̂Ŕ����܂����B
���̃e�X�g�͋@��ɂ������ȃm���̍����킩���āA�ƂĂ��A�ʔ��������ł��B
�ڂ����́A�����̃T�����R�i2000�N10�����j�����Ă�������
(2000.08.20)
��back to top
�@
�S�A�Ђ̌�
�@�S�A�Ƃ����̂́A���̃S�A�e�b�N�X�ŗL���ȉ�Ђ��B
�������A�Ȃ��M�^�[�A�x�[�X���Ȃ̂��H�悭�킩��Ȃ���
�Ƃ������A������ƕς�������\���Ă���B
����͊����ɓ���ȃR�[�e�B���O���{�������̂ŁA�����ɏ��Ȃ���
���������ɂȂ��Ă���B
�M�^�[�p�A�x�[�X�p�e��o�Ă���킯��������̓M�^�[�p���e�X�g���Ă݂��B
���肽�Ă̊����́A������A�����ɂ��u�V�������ł��v�Ƃ����s�[���Ƃ���
���������Ȃ��B���ʂ̌����Đ����o������Ƃ����������B
���̂�����Ɨ��������������͈����Ȃ��B���ꂪ�ǂ��܂Ŏ������邩���B
���݁A�͂��Ă���T�P�����o�߂��Ă��邪�A�͔��ɏ��Ȃ��B
�Ŕʂ�̐��\�Ƃ����邾�낤�B
������ƍ��߂̉��i�ݒ肾���A�g���r�ɂ���Ă͔��ɑ��݉��l�̂������
�Ƃ�����B
�a�߂̃T�E���h���D�݂̕��ɂ́A�T�E���h�A�ϋv���̖ʂŃI�X�X���ł���Ǝv���B
(2000.08.03)
�S�A��http://www.goremusic.com/
��back to top
Copyright(C)1993-2004 Jin TERADA, All Rights Reserved.


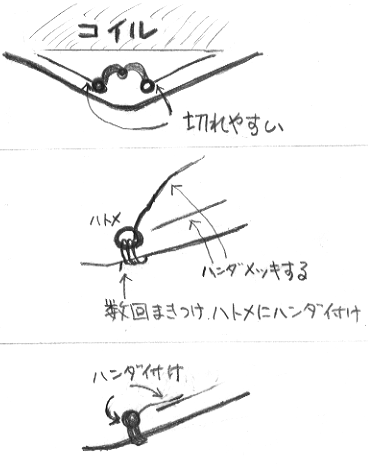
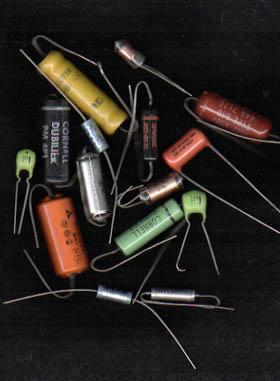
 �s�b�N���낢��B
�s�b�N���낢��B